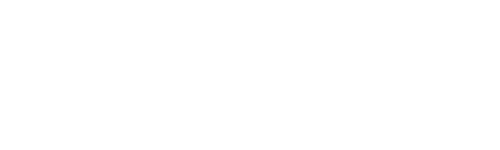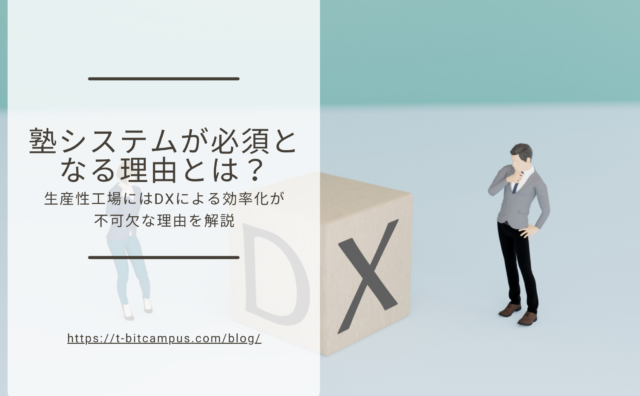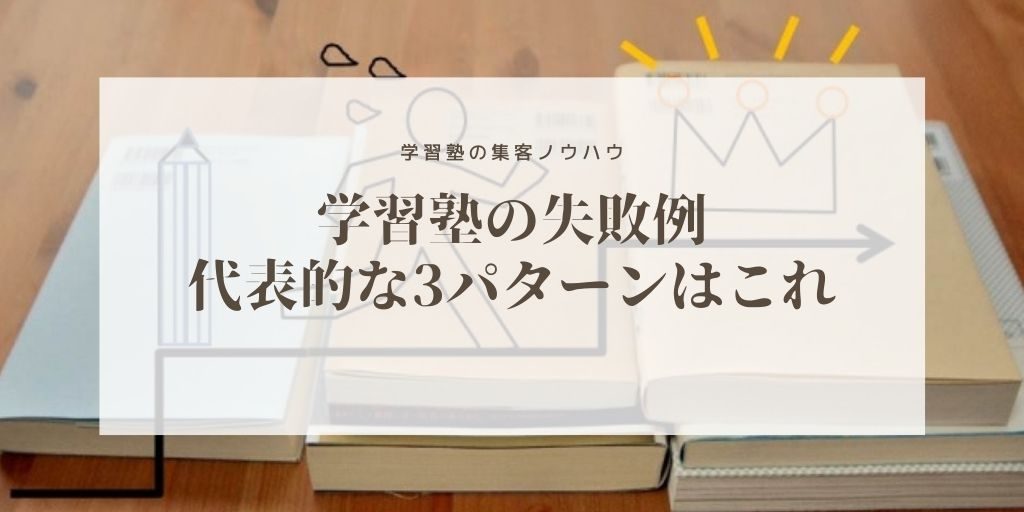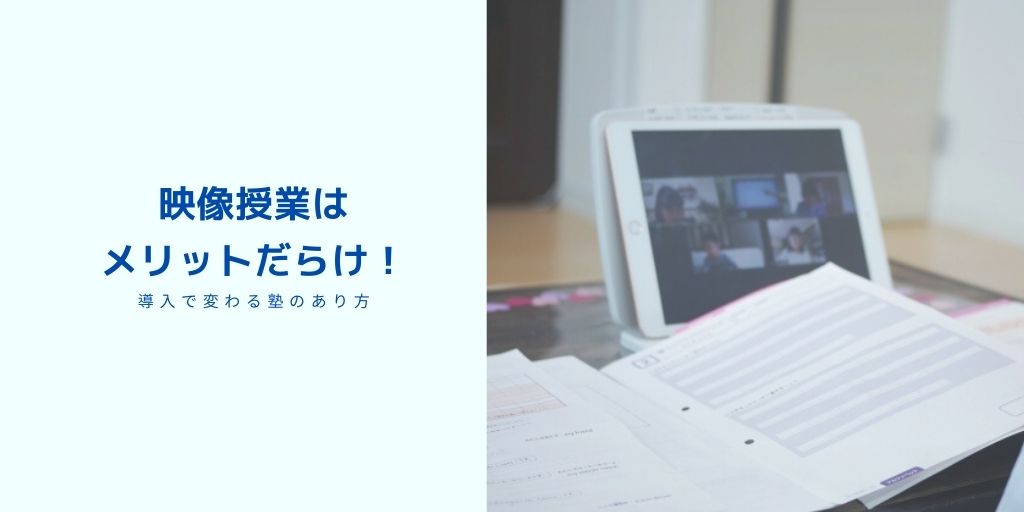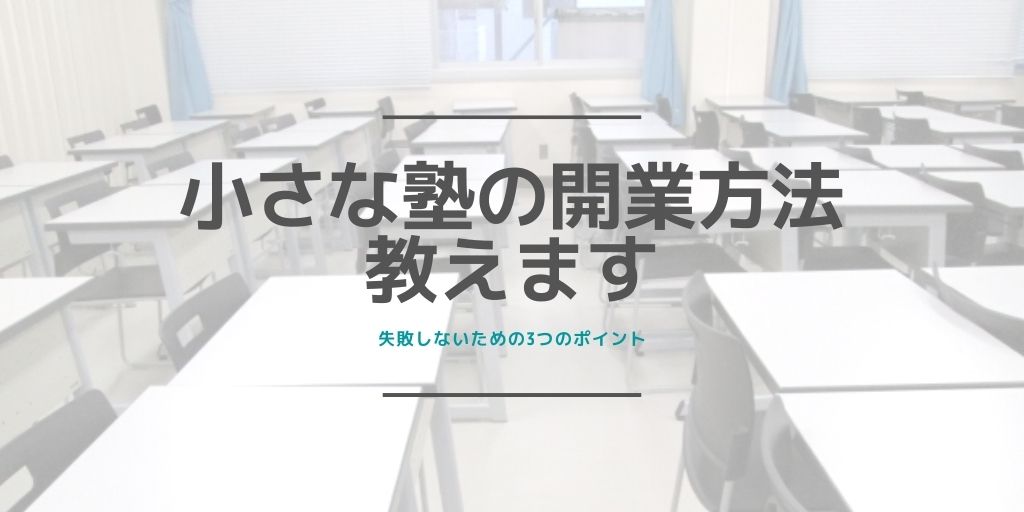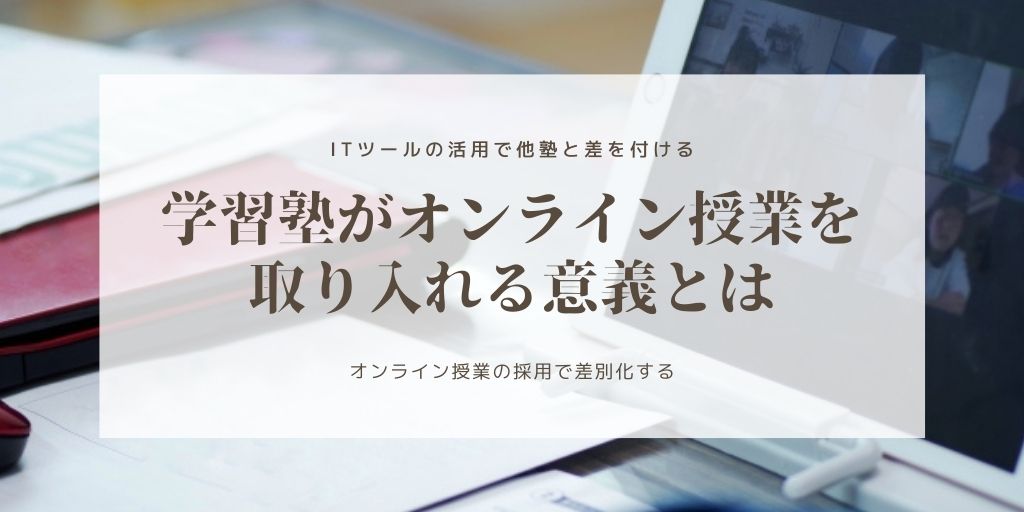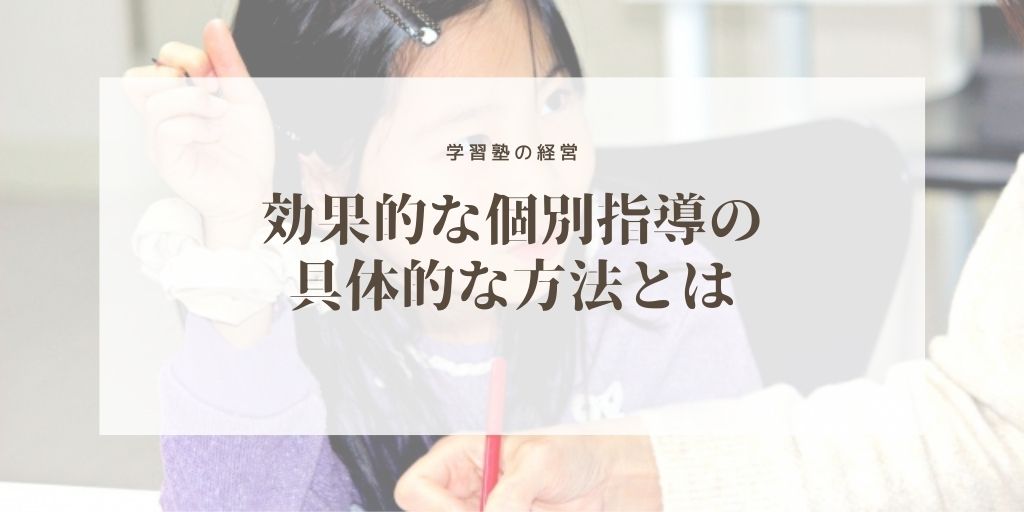塾といえば初期投資が少なく開業しやすい業種の1つです。
しかし多くの塾が乱立しているため、塾経営に失敗するケースも多く見られます。
「人気講師として塾で働いていた人でも、独立後に生徒を集められない」
こうした失敗の事例は枚挙にいとまがありません。
失敗しないためには、失敗するパターンを理解したうえでの対処が必要です。
\ビットキャンパスの詳細はこちら/

塾は開業しやすい一方で廃業も多い
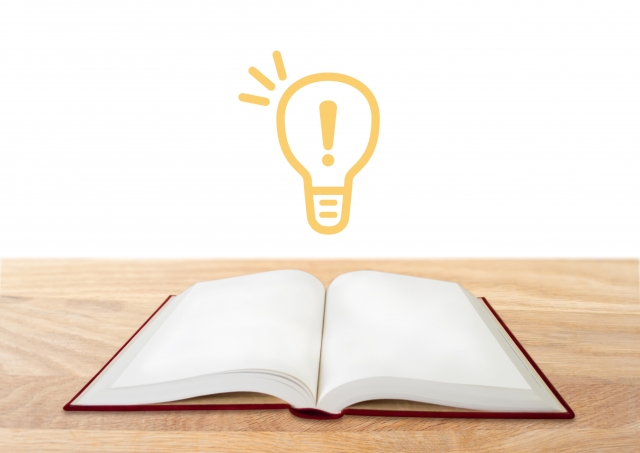
塾は他業種に比べて開業がしやすいことが特徴です。
つまり参入障壁が低いのです。
少額の資金でも開業でき、教材と教室、机、椅子などの備品があればすぐにスタートできます。
しかし開業は簡単であっても、塾経営が成功するとは限りません。
- 塾の倒産件数
- 参入障壁が低い弊害
最低限知っておくべき知識としては、上記の2点が挙げられます。
年間の倒産件数は60〜90件で推移
塾業界の年間の倒産件数は60~90件で推移しています。
倒産する塾には大手塾やFCの強豪塾も含まれており、とても競争が激しい業界です。
少子化が倒産理由として挙げられますが、それだけではありません。
ニーズの多様化はもちろん、サービス品質の低下により生徒が集まらないケースも多く見られます。
一方で順調に業績を伸ばし続けている塾もあり、現在の塾業界は勝ち組と負け組がはっきりしている状態だと言えます。
また2020年に発生したコロナウイルスの影響で、塾業界もITを取り入れる時代になりました。
これが塾業界の競争に拍車をかけることが予想されます。
過激化する競争に勝ち残るには、厳しい時代に突入するのです。
参入障壁が低ければ低いほど競争が激しくなる
初期投資がしやすく、教材や教室管理のシステム化も進んでいるため参入障壁が極めて低い塾業界。
手軽に稼げられると考え独立する方が多く塾は乱立状態です。
加えて少子化の流れもあるため、減る顧客のパイに対して塾は増え続けているため、競争が激化するのは当然と言えるでしょう。
総務省の「人口推計」調査によると、15歳未満の人口は2020年に15,032千人、2021年に14,784千人、2022年に14,503千人とわずか3年で5%近く減少しています。
一方、経産省「特定サービス産業動態統計調査」によると、学習塾業界の事業所数は、2020年に11,602か所、2021年に11,337か所、2022年に11,558か所、と増減がほとんどありません。
この中で勝ち抜いていくには差別化戦略による事業展開を考える必要があります。
- 明確な教育理念
- システム
- 立地
- 差別化
自塾の方向性はもちろん、こうした未来を見据えて準備する必要があります。
特に失敗パターンの把握は成功のためには欠かせません
塾経営の失敗①大手塾と同じ戦略をとる

大手塾がとるのは、資本力のある強者の戦略です。
広告宣伝費だけでも、何百億の売上額から5~10%もの額が市場に投下されます。
大手塾の戦略をとると、あなたの塾の強みが活かせず競争に勝つことは難しいでしょう。
- 弱者が強者の戦略をとると必ず負ける
- 弱者には弱者の戦略と戦い方がある
- 大手塾に対し徹底した差別化戦略をとる
以上の3点を意識した事業計画を考えるべきです。
弱者が強者の戦略をとると必ず負ける
強者の戦略は豊富な経営資源を活かした全方位戦略です。
経営資源が脆弱な弱者が模倣すれば経営資源の分散を招き必ず負けます。
大手の塾は知名度があり高い集客力を持ち、同じことをしても小規模塾では対抗できません。
ですが大切なのは、徹底した差別化を図り、小さな市場でリーダーとなることです。
大手塾とはいえ、地域ごとに出店している教室単位で見れば個人塾と同じで、教室長対塾長の競争です。大手の教室長に負けなければいいのです。
特定の小さな市場で特定のニーズに合ったサービスを提供することで、顧客の支持を得られる可能性は十分にあります。
弱者には弱者の戦略と戦い方がある
弱者の戦略とは経営資源の「選択と集中」です。
ランチェスター戦略などが有名ですね。
全方面に経営資源を投下できる大手に対し、特定の領域に経営資源を集中させ、効率的に経営することで対抗します。
大手には何でもできる資本力がある反面、機動力に欠け容易に戦略を変更できないという弱みがあります。
例えば、地域の学校の授業進度が遅く、試験範囲すら間に合わずに学力が低い層が増えだした場合、大手塾では採択教材の本部縛りがあることが多く、増えた学力下位層用の教材に柔軟に対応することが難しいことがあります。
全体最適を優先するため、顧客の小さなニーズに対しては応えることが難しいのです。
ですが小規模な塾であれば機動力があり、さまざまなニーズに対応できます。
大手塾に対し徹底した差別化戦略をとる
大手塾が対応できない顧客の持つ小さなニーズや不満を突き、徹底して差別化を図りましょう。
そうすることで小さな市場でも競争優位性を獲得することができ、特定の層のニーズに深く刺さり支持を得られます。
ある個別指導塾では、徹底して1:1の指導形態にこだわっているところがあります。
近隣の大手塾もできなくはないのですが、全教室で1:1の指導形態を打ち出すことは、講師不足もあってできません。
1:1の良い点は、先生が生徒の問題解答過程を細かく観察でき、保護者への報告もより具体的になり、指導への保護者の信頼度が高まります。その為、きめ細かい指導を求める保護者のニーズに合致し、生徒数は少なくても高単価なので、ある程度の売上を維持できるのです。
小さな市場を選択することで、顧客数の少なさに不安を感じる経営者もいるかもしれません。
しかしその心配は必要ありません。
なぜなら特定の層へ深る刺さることで評判が評判を呼び、顧客が顧客を呼ぶ好循環を招くからです。
これこそが小規模な塾が大手との競争に勝つための王道のセオリーなのです。
塾経営の失敗②生徒が集まらない場所を選択してしまう

塾経営の失敗には「立地の悪さ」が原因となることもあります。
立地が悪いと、どれだけ素晴らしい授業でも生徒は集めるうえで不利になります。
場所選びの失敗は取り返しがつかないので、出店前に熟考しましょう。
- 塾経営は立地が大切
- 小規模塾だから選択できる場所を探す
- 出店前に徹底的な分析をする
ここでは、上記3点についてご紹介します。
塾経営は立地が大切
学校での日頃の勉強や、近隣の学校を志望する生徒が多い学習塾では、地域の学校に通う子ども達の通学圏を意識して立地を決める必要があります。
一方、プログラミング教育や探究系の塾には、意識の高い保護者が興味を示しますので、多少自宅と離れていても塾に通わせてきます。都市部であれば交通アクセスの良い駅近くの立地、地方であれば駐車場スペースを多く用意できる立地が適しています。
また、一人親家庭が増えている地域、共働き家庭が増えている地域では、家庭事情に配慮して送迎サービスを導入することも必要です。
子供も親も入塾を希望しているのに、送迎ができずに諦めるケースは意外にも多いです。
立地条件で生徒の数は決まります。
費用との兼ね合いにもなりますが、生徒が集まる、通いやすい立地にこだわりましょう。
小規模塾だから選択できる場所を探す
大手の塾は、宣伝広告費や人件費が多くかかりますが、塾のブランドで生徒を集められます。
そのため、駅前や大通りなど、立地条件がいい場所で営業していますよね。
そうした土地は塾乱立の状態となり、生徒獲得競争が激化していくのです。
小規模の塾は、高い借賃で契約をするのはやめましょう。
生徒が集まらなかったときのリスクが大きすぎるからです。
ここでポイントになるのは、生徒が獲得しやすい場所を選ぶこと。
家賃の高い駅前でなくても、住宅街で集客している小規模塾は、複数の学校から通える立地を選んでいます。
また、駅前から多少離れていても、大手塾が立ち並ぶエリアに塾を構えれば、大手塾の宣伝効果で「塾はあのあたりに多い」という保護者の意識を活用できます。大手塾を退塾した生徒の受け皿となることもできます。
出店前に徹底的な分析をする
分析する点としては、管轄の学校の人数は必ず把握しましょう。
小規模の塾であれば、学年人数の1割が取れれば、十分順調と言えます。
次に通塾のルートをしっかりと戦略に組み込むことが大切。
地元の方しか知らない抜け道もあるため、土地の周辺調査は必ず行くようにしましょう。
その際、街灯や交通量も注意して見てください。
今では遅い時間でも自転車や徒歩で通う生徒もいますから、この点も配慮しましょう。
さらに、地域の学習塾の調査です。
大手だけでなく、個人でやってる小さな塾にも競合はいます。
塾生人数やサービス内容などの情報を把握し、差別化を図れるようにしましょう。
他にも情報は1つでも多い方が勝つ理由になります。
ニーズや家族層、平均的な収入なども大切な情報になります。
大手検索サイトの地図サービスには、様々な情報を盛り込んだCSVファイルを読み込み、地図上にプロットしてくれるものもあります。
デジタルツールを使って出店検討地域を視覚的に把握することも大切です。
負けないためにも、些細な情報をキャッチできるよう、アンテナを張りましょう。
塾経営の失敗③価格競争で対抗する

大手をはじめ、他塾と生徒の取り合いになると巻き込まれやすいのが低価格戦略。
体力のある事業規模であれば耐えられますが、小さな塾では安易に乗ってしまうと命取りです。
価格競争に巻き込まれないための事業戦略を立てるべきです。
- 資本力がある大手に価格で戦わない
- 中小企業は質の高いサービスで差別化する
この2点のポイントが重要です。
資本力がある大手に価格で戦わない
大手の塾の場合、一つの教室で結果が出なくとも企業全体で収益のバランスを取れます。
価格を下げたことで一つの教室で赤字が出ても、収益の高い教室で補完が可能。
こうした大手の戦略に追随すると、リスクの分散が困難な中小企業の体力は持ちません。
あなたの塾が持つ強みを最大限活かして、価格ではなく質の高いサービスで戦うべきです。
小規模な塾は低価格よりも質の高いサービスで戦う
塾業界に限らず価格競争に巻き込まれる問題はかならず発生するものです。
繰り返しとなりますが、価格競争で勝ち抜くポイントは「質の高いサービス提供で差別化する」です。
仮に月料金5,000円高くとも、顧客のニーズに適合した質の高いサービスがあれば生徒は集められます。
- よく見てくれる
- しっかり対応してくれる
- 信頼できる
- 話しやすい
- テスト対策や自習などが充実している
など大手にできない小回りの利くサービスを提供するかがが大切です。
5,000円ほど高くても、質の高いサービスにならお金を払いたいと考える家庭は少なくありません。
現に少子化が進んでも1人あたりの教育費は増加傾向にあります。
ある個人塾の経営者は、個人経営が生き残る戦い方は高単価しかない、と言われていました。
「月1万円で100人の塾生を指導するより、月10万円で10人の塾生を丁寧に指導する方が理にかなっている」という考え方です。
価格を下げるのではなく、逆にいかに付加価値を付けられるか。
これが小さな塾が生き残るために必要な考え方です。
まとめ

独立し塾を開業する際には、この厳しい競争市場の中でいかに生き残るかを考える必要があります。
どれだけ厳しい環境下にあっても、自社が生き残れるだけの収益を生み出すことは十分に可能です。
そのためには失敗のパターンを理解し、大手や競合に対して徹底的な差別化を行い「この塾にならお金を払いたい」と感じてもらうサービスを提供することがポイントです。
>>他塾よりも15倍問合せを得る!ポスティング術事例ダウンロード
>>入塾率向上!塾に問合せのあった見込み客の成約率を上げる方法とは?
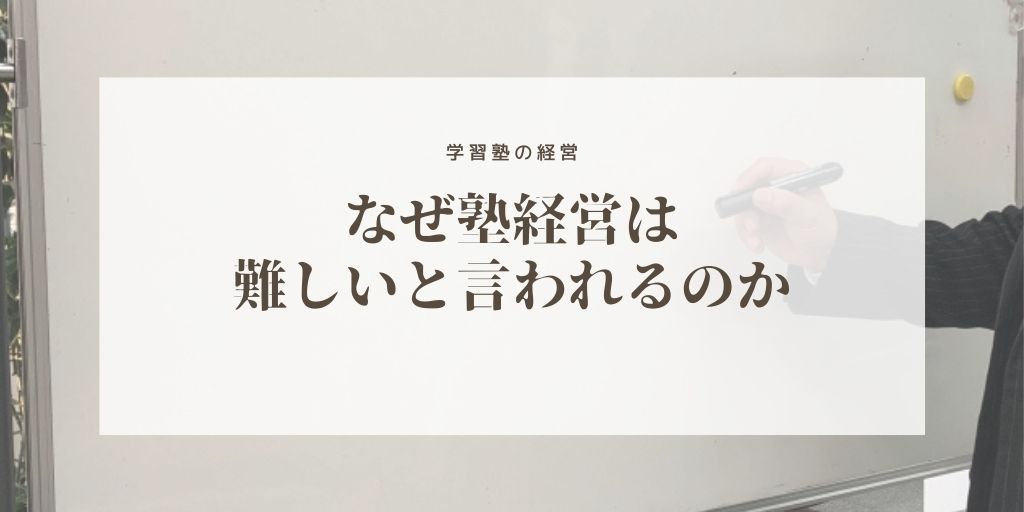
\ビットキャンパスの詳細はこちら/