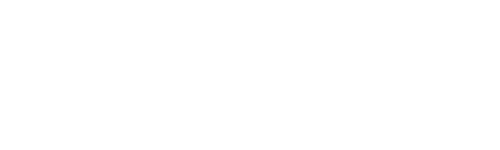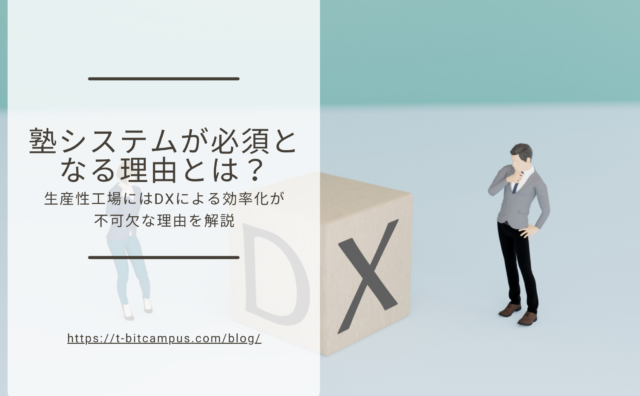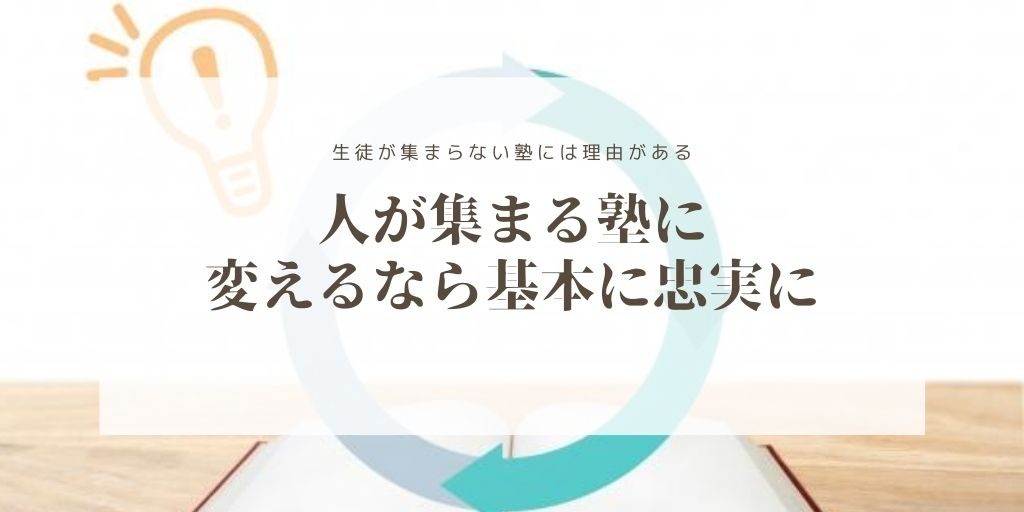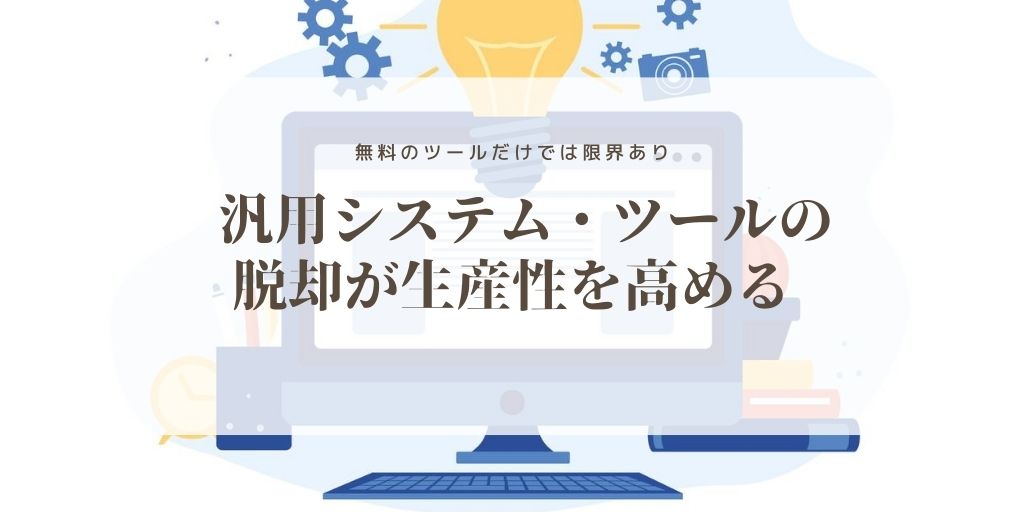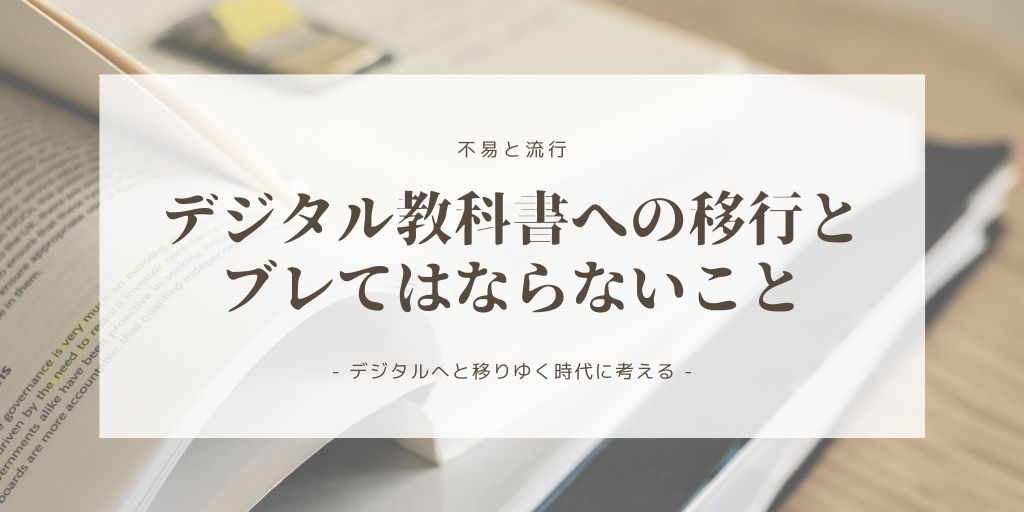塾の経営に携わる方であれば、誰もが生徒たちに一生懸命授業を提供し、保護者の方々とのやり取りにも力を入れていますよね。
でも、時には「もっと多くの生徒を引きつけたいな」と感じることもあるでしょう。
そう思っているのは、私たちだけではありません。
実は、多くの塾で同じような悩みを抱えているんです。
ただ、「生徒が増えないなぁ」と嘆いているだけでは、何も変わりませんよね。
特に今のように変化が激しい時代には、現状維持は後退を意味することも。
だからこそ、生徒が増えない原因をしっかり分析し、具体的な対策を練る必要があります。
ただ、すぐに効果が出る魔法のような方法はないのが現実です。生徒を増やすためには、
- 増えない理由をクリアにする
- どのように改善するかを具体的に決める
- 生徒を増やすための行動計画を立てる
この3ステップをしっかりと実行することが大切です。
それでは、それぞれについてもっと詳しく見ていきましょう!
\ビットキャンパスの詳細はこちら/

塾に生徒が集まらない理由
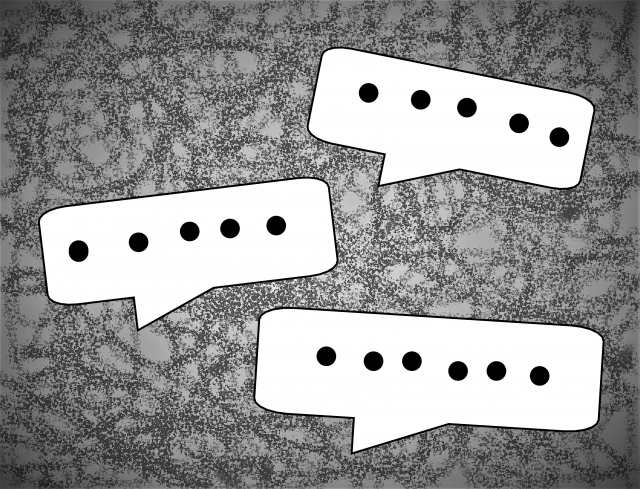
さて、生徒がなかなか集まらない時、よく言われるのが「講師の力が足りない」ですよね。
確かに、それが原因の一つであることもあります。
ですが、講師だけに頼るのではなく、塾全体としての成長や繁栄を考えることも大切です。
講師のスキルだけに焦点を当てるのではなく、「成績の向上」をどう実現し、その成功を市場にどう伝えるか、この二つのポイントが非常に重要です。
効果的なシステムを構築することが、ここではカギとなります。
生徒が集まらない原因は大きく分けて3つ。
- 授業内容が評価されていない
- 悪い口コミが広まっている
- 強引な売り込みが逆効果になっている
これらの問題点は、短期的に改善できるものもあれば、時間をかけて取り組む必要があるものもあります。
自分たちの塾にどれが当てはまるか、一つずつ確認してみてくださいね。
それでは、それぞれの問題にどう対処するか、見ていきましょう。
授業内容が評価されていない
塾業界では、授業の質がすべてです。
ここが優れていないと、塾としての評価も望めません。
授業が高く評価されるためには、以下の3つが重要です。
- わかりやすさ
- 楽しさや面白さ
- 生徒のやる気を引き出すこと
これらが揃っていれば、生徒や保護者からの評価は自然と上がります。
もし授業内容が評価されていないなら、これらの要素の一つか全部が欠けている可能性が高いです。
一般的な授業評価方法としては「生徒満足度調査」のようなアンケートがありますね。
ただし、子どもたちは先生の気持ちを考え、本音とは違う答えを選ぶことがよくあります。
そのため、アンケートの質問の仕方を工夫することが大切です。
例えば、「先生の授業はわかりやすいですか?」ではなく、「あなたは授業を理解できていますか?」といったように、生徒自身の感覚に焦点を当てた質問をすることが効果的です。
さらに、これらのデータを校舎ごと、学年ごと、クラスごと、担任講師ごとに分析し、定期的に評価する仕組みを作ることも重要です。
学習指導は塾の核となる活動ですが、今の時代、生徒の満足度が塾の評価に直結しています。
そのため、授業内容だけでなく、サービス全体の充実にも目を向けることが求められます。
少しの工夫で大きな変化が見込めるので、これらは短期的な改善に非常に適しています。
悪い口コミの広まり
もし生徒が増えない、あるいは減少の兆しを見せている場合、まず考えるべきは口コミの影響です。
良い評判は広がりにくい一方で、悪い評判はすぐに広まる傾向があります。
特に、退塾した生徒の意見は重要です。
「1人の退塾者の周りには7人の退塾予備軍がいる」と昔から言われていますからね。
成績の伸び悩みや授業に対する不満を持つ生徒や保護者には特に注意が必要です。
これを防ぐためには、成績や面談の記録を定期的にチェックし、管理するシステムの構築が欠かせません。
定期テストの前後で成績がどのように変動したかを把握し、成績が下がった生徒にはすぐに面談を設け、対策を練り、それを保護者にも共有する必要があります。
塾全体での成績管理システムの導入が、これを効率的に行うための鍵となります。
また、異変を感じた時には、以下のような対策が効果的です。
- 面談の頻度を上げる
- 生徒とのコミュニケーションを強化する
- 職員間の情報共有を促進する
さらに、地域内での塾の評判を調査し、根も葉もない噂が流れていないかチェックすることも大切です。
こうした情報を集め、必要に応じて改善策を講じることが、中長期的な成果につながります。
次に、売り込みが強すぎることが生徒減少の原因になっていないかを考えてみましょう。
売り込みの強さによる敬遠
売り込みが強すぎる塾は、地域社会で敬遠される傾向にあります。
個別指導や映像授業(オンライン講座含む)、受験対策授業で、生徒に無理に多くの授業を受けさせる姿勢はリスクが伴います。
多くの生徒や保護者は、本当にその授業が必要かどうかわからない状態です。
そうなると、「お任せ」の選択が多くなり、結果が出ないと「高い」「売り込みが強い」という印象を持たれがちです。
職員の説明能力による影響はありますが、最も重要なのは、提案が子供たちの最善の利益を考えたものであるかどうかです。
日々の授業で生徒の心を掴み、保護者との密接なコミュニケーションを取れていれば、売り込みは自然と抑えられます。
また、データに基づく提案も重要です。
例えば、過去のデータを基に「この時期にこの偏差値であの高校を目指していた生徒の合格率」などを提示し、追加の授業を提案すると営業色が薄れ、生徒のためを考えた提案になります。
信頼関係があれば、保護者も提案を受け入れやすくなります。
相手が必要ないと感じる授業を強要することは、顧客にとって不快に感じるものです。
利益を出すためには、生徒一人一人と真摯に向き合うことが必要です。
営業は悪ではありませんが、事前の準備と適切な提案が肝心です。
こうしたアプローチを通じて、生徒数を増やすための戦略を練りましょう。次に、生徒を増やすための具体的な戦略を考えてみましょう。
>>理想の塾の集客方法は?媒体を組み合わせた効果的な生徒の集め方
塾の生徒の集め方・増やし方

生徒を集め、数を増やすための方法は実はシンプルです。
新しい商品開発や革新的なアイデアに頼る必要はありません。重要なのは以下のポイントです。
- 授業の見直しと改善
- 塾内環境の整備
- SNSやブログを活用した集客
- 良い口コミの創出
これらを順に見ていきましょう。
授業の品質を見直す
まず、授業の品質の見直しです。授業は塾の命です。
ここが不十分なら生徒が集まることはありません。
講師は学力が高い方が多いですが、それだけでは不十分です。
重要なのは、「わかりやすく教える」ことはもちろん、生徒にやる気を与えることです。
生徒にやる気を与えるためのポイント
- 成功体験の提供
- 生徒との信頼関係の構築
- 授業でのきっかけづくり
これらがない授業は生徒を引き付ける力を持ちません。
問題の解説の技術は講師歴があれば身につくものですが、大切なのは「どう生徒の心をつかむか」です。
授業内容の評価は単に「教え方」ではなく、以下のような細かい配慮が必要です。
- 躓くポイントでの解説の工夫
- 長い解説を端的に行う
- 生徒を当ててほめるポイントを明確にする
- 生徒の理解が足りない部分を把握する
- 誤答から生徒の状態を読み解き、適切な解説を行う
これらの点を踏まえた上で、優れた指導技術を持つ講師を採用し、授業を担当する講師の研修を定期的に行うことが重要です。
次に、塾内環境の整備について見ていきましょう。
>>塾の指導・授業は変えるべき?スタイルを変更するメリットとデメリット
塾の環境を見直す
塾の成功において見落とされがちなのが、塾内環境の整備です。
教室を清潔に保つのは基本中の基本ですが、さらに一歩進めて、教室の「色」にも配慮してみませんか。
「人は見た目が9割」とよく言われますが、視覚が大きな影響を及ぼすことは明らかです。
特に視覚の大部分を占めるのが「色」です。
色には、心地よさを与えたり、勉強に集中させたりする効果があります。
教室内の壁やカーテン、掲示物の色に一貫性を持たせ、塾のイメージカラーとの調和を考えることが大切です。
また、季節ごとの装飾や掲示物を通じて、新鮮な印象を与えることも効果的です。
生徒の笑顔や努力を称える展示物は、生徒と保護者にとって喜ばしいものです。
例えば、生徒の努力をトロフィーで表彰し、歴代受賞者の名前を教室に飾るなど、生徒の達成感を高める工夫が有効です。
また、合格体験記を掲示する際には、インタビュー映像を流すなど、インタラクティブな要素を取り入れるのも良いでしょう。
他にも以下のような工夫を試してみてください。
- 机の間隔を少し広げることで、生徒がより見やすくなります。
- 異学年の生徒が座るレイアウトを作ることで、中学生が高校生の努力を見て刺激を受けます。
- クリスマスやハロウィンなどの季節の飾り付けで、生徒の喜びや家庭での会話を促進します。
- 送迎サービスを充実させることで、地域へのアピールや生徒とのコミュニケーションを強化します。
これらの工夫は比較的簡単に実施でき、塾の雰囲気や評判に大きな影響を及ぼすことができます。
次に、SNSやブログを使った集客について考えてみましょう。
SNSやブログを活用する
現代のサービス業界では、インターネットを活用した集客方法が非常に重要です。
特に、SNSやブログを通じた情報発信は、新規顧客獲得に非常に効果的です。
保護者が塾を選ぶ際、もはや電話で資料を請求する時代は過ぎ去り、最初にWEBで情報を収集することが多いです。
しかし、多くの塾のWEBページは似たような内容で、保護者が「自分の子に合った塾はどこか」を見つけるのは難しいのではないでしょうか。
定期的なホームページの更新よりも、日々の活動や変化を発信するSNSやブログの方が、保護者に信頼を与えやすいです。
先生やスタッフの人柄、教育方針、日常の出来事、質問対応の様子、合格祝いの様子など、塾の雰囲気を伝えるのにSNSやブログは最適でしょう。
例えば、YouTubeでシリーズ化されたブログ記事を公開したり、塾長の生の声を映像で伝えたりすることで、保護者や生徒に対してよりリアルな塾のイメージを伝えられます。
また、希望する生徒層に合わせたメッセージを発信することで、目指す生徒層を引きつけることが可能です。
これはDMやチラシなどの紙媒体と違い、常に最新情報を発信し、修正も容易な点が大きな利点です。
SNSやブログは、積極的に取り組む価値のある媒体と言えるでしょう。
最後に、良い口コミを生むための戦略について見ていきましょう。
>>低予算で塾の生徒を増やす方法とは?SNSやブログを最大限活用しよう
SNSの重要性の高まり
2022年のICT総研の調査から、ますますSNSの重要性が高まっていることが分かります。
日本国内では、SNSの利用者数が急速に増加しています。
2022年末の時点で8,270万人、2024年末には8,388万人に達すると予想されており、これはスマートフォンの普及により、若年層だけでなく高齢者層にも広がっている現象です。
ICT総研の2022年4月の調査によると、日本のネットユーザーのうちLINEを利用しているのは79.5%、YouTubeが62.0%、X(旧Twitter)が55.9%に達しています。
これは、今後の広告や認知戦略でSNSの活用が必須になることを示しています。
小さなステップから始め、継続することが重要です。
そして、生徒数の増加には口コミが非常に大きな影響を与えます。
口コミの源泉は、通塾中の生徒や保護者です。そのため、彼らの満足度を高めることが重要になります。
口コミで生徒が増える好循環へ
口コミは短期的には生まれにくいものであり、日々の活動を通じて徐々に形成されます。
「伝達→納得→感動」というプロセスを経て、最終的に口コミが生まれます。
継続と忍耐が必要です。
成績の向上はもちろん、それに伴う活動が別の口コミを生む可能性もあります。
例えば、自習席の設置や質問対応、提出物の管理、定期テスト対策などは、保護者から見れば「面倒見が良い」という評価につながります。
加えて、面白い授業、相談への対応、教育の質など、これらの要素も口コミに繋がります。
一人一人の生徒に真摯に向き合うことは、人々の心を動かし、強い塾、つまり生徒を集める塾へとつながります。
勉強を通じて心を通わせることができる塾は、今後も力強く成長し続けるでしょう。
>>塾の集客に紹介・口コミは欠かせない!在校生からの紹介が増えない理由とは?
塾を集める最適な時期・シーズン

塾の募集シーズンは明確なタイミングがあります。
講習会は特に効果的な機会で、多くの生徒が体験気分で参加します。
そのため、講習会の戦略をしっかりと練ることが重要です。
また、定期テスト直後や入学・進級時も集客に効果的な時期です。
それでは、これらのポイントについて詳しく見ていきましょう。
中間・期末テスト後のチャンスを活用する
中間・期末テスト後は、多くの塾が生徒対応で忙しい時期です。
特に成績が下がった生徒は退塾のリスクが高まります。
そのため、他塾の生徒が転塾を検討しているこのタイミングは、新規生徒を獲得する絶好のチャンスです。
成績の変動を早急にアピールすることが重要で、他塾よりも速く良い結果を保護者や教室内で公開し、SNSやブログで情報を発信しましょう。
入学・進級時の集客に注力する
春の新学年スタート時は、1年で最も多くの生徒が集まるシーズンです。
特に、私立中学や国公立高校を目指す生徒層はこの時期に狙い目です。
自塾がターゲットとする層に合わせた戦略を立て、推薦入試を目指す生徒や、新しい傾向の入試対策を必要とする生徒に焦点を当てることが大切です。
過去のデータを活用して、なぜこの時期に入塾する必要があるのかを保護者に効果的にアピールしましょう。
また、学年や学力層に合わせたターゲットを定め、既存の塾生の質や口コミ、クラス状況なども考慮しながら戦略を練ることが求められます。
これらの戦略を踏まえ、塾の生徒募集活動を計画的に実施することで、生徒数の増加につなげることができるでしょう。
>>理想の塾の集客方法は?媒体を組み合わせた効果的な生徒の集め方
まとめ
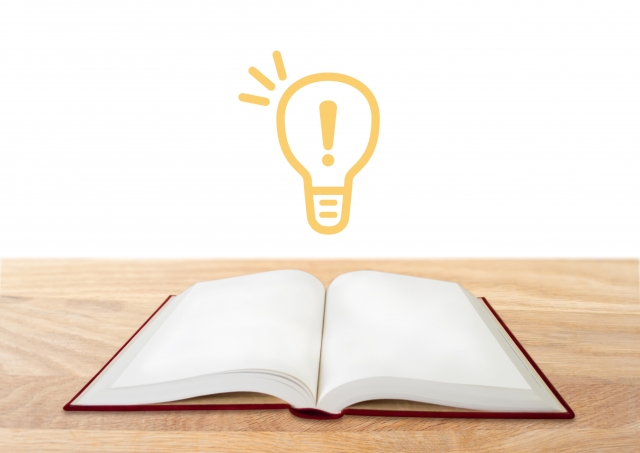
生徒が集まる塾に理由があるように、生徒が集まらないのにも理由があります。
決して講師の怠慢だけで募集が決まるものではありません。
どれだけ頑張っていても、生徒が集まらない時期はあります。
特に悪い口コミが流れているときは我慢が必要です。
長く塾を開いていると、様々なケースが訪れます。
- 塾生がたくさん集まる→いい口コミが起き、波が起きてる→サービス向上、募集拡大
- 大量の退塾が出る→悪い口コミが起きている&今後が厳しくなる→塾内整備、内部生を守る
- 入塾も多いが、退塾多い→良悪双方の口コミが混在している→新入塾対応強化、内部生を守る
このように、ケースによって対応も異なります。
生徒が集まらない理由は、決して1つではありません。
複数の要因が絡み合った結果、生徒が集まらなくなるのです。
それらの原因を探り、適切な対処をすることが、集まらないの改善、すなわち募集獲得ができる教室作りに繋がります。
小さな変化でも大きな結果が生まれるので、ぜひ1つ1つと向き合って、改善し、たくさんの生徒に、自分がいいと信じる教育、指導ができるようにしましょう。
>>他塾よりも15倍問合せを得る!ポスティング術事例ダウンロード
>>低予算で塾の生徒を増やす方法とは?SNSやブログを最大限活用しよう

\ビットキャンパスの詳細はこちら/