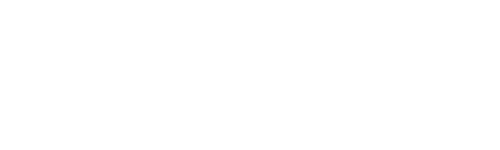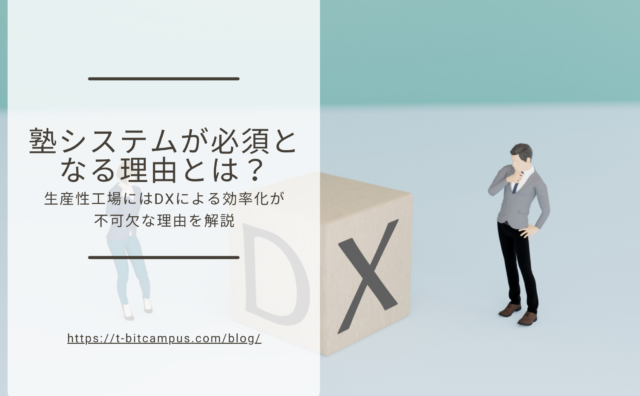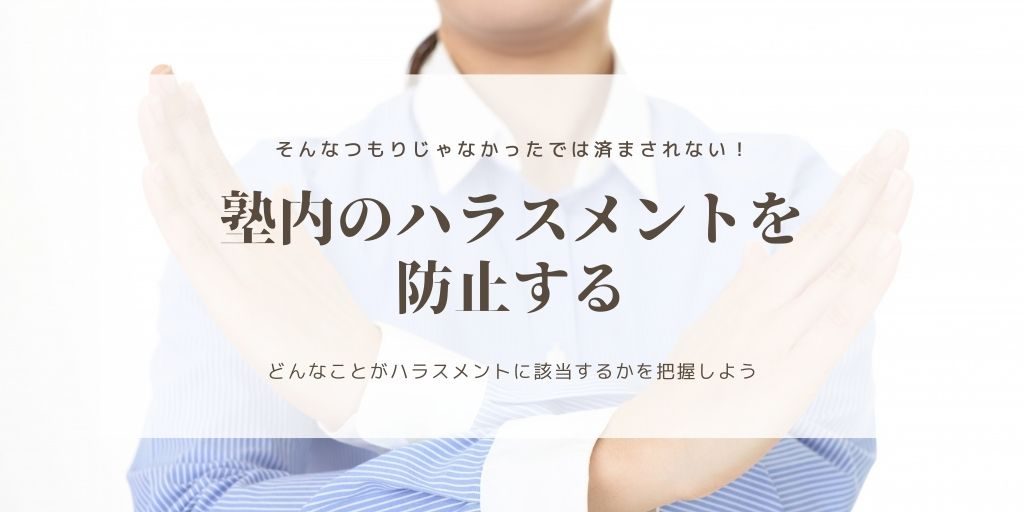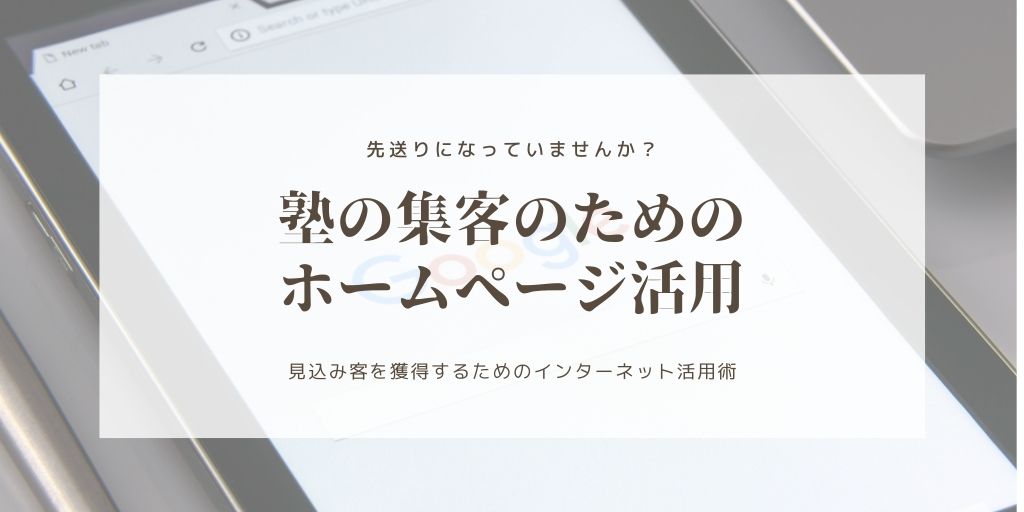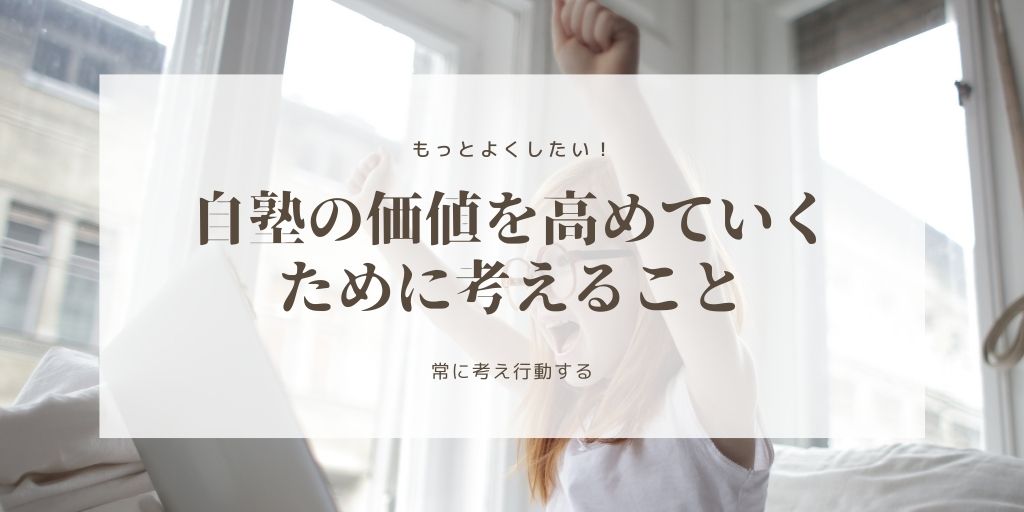社会問題として声が上がり始めてからどんどん増加するハラスメント。
代表的なものからあまり知られていないものまで、たくさんのハラスメントがあります。
学習塾では関わる「人」が多岐に渡るため、いつ、どこでハラスメントが発生してもおかしくありません。
そこで今回は、ハラスメントを防止するために知っておきたいことについてご紹介します。
ハラスメントのポイントや種類、予防の方法についてお伝えするので、ぜひ参考にしてください。
塾に限らずハラスメントに対して世間の目は厳しい
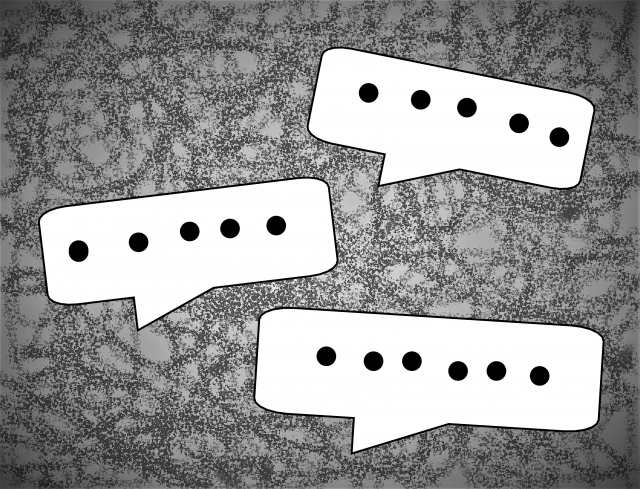
経営者の方であればご存じの方も多いでしょうが、ハラスメントに対する世間の目はとても厳しくなっています。
ハラスメントのつもりはなくても、一度噂が立ってしまうと取り返しがつかなくなりかねません。
塾でハラスメントに注意するポイントは以下の2つ。
- 関わるすべての人間が対象となる
- 相手が不快に感じればハラスメントが成立する
理不尽のように感じますが、こうした流れは変わらないでしょう。
塾で関わり合うすべての人が対象
学習塾は多くの人と関りを持って日々の仕事に取り組んでいます。
近いところでいえば、従業員(正社員、アルバイト講師)、生徒、保護者です。
他にも学校の先生や地域の住民、近隣の塾など、普段あまり関わらないところでもハラスメントに直結してしまう対象があります。
塾でのハラスメントで注意しなければならないのは講師の言動です。
冗談のつもりで発した一言が、地域に広がりハラスメントと受け取られてしまうケースもあります。
また対象が子供であると、ちょっとした気の緩みでハラスメントと取られる行動を起こしてしまう場合もあるのです。
子供と距離が近い講師は人気の出る講師ではありますが、距離が近すぎることで知らず知らずのうちにハラスメントとなっているケースもあります。
そのため、講師は常にハラスメントと取られない、常識的な目線での節度ある行動が必要なのです。
相手が不快に感じればハラスメントが成立
ハラスメントの厄介なところは、相手が不快に感じてしまえば成立する点です。
冗談半分で愛情を込めて「ばかだなぁ」と生徒に言ったとしても、相手が不快に感じたら立派なハラスメントになります。
また、言われた本人が気にしていなくても、周りで聞いている生徒がハラスメントと感じるケースもあるため、グレーな言動には細心の注意が必要です。
また、学校の先生に対して「テストの問題が難しすぎる」などのクレームじみた発言も問題となる場合があります。
ハラスメントが問題となった際、よく言われるのが「そんなつもりじゃなかった」という弁解です。
これはもはや通用しない言い訳と考えた方がいいでしょう。
自分がどう思ったかではなく、相手がどう感じたかが大切なのです。
逆を言えば、相手が不快に感じなければセーフとも言えます。
塾講師は生徒の心をつかまなければ成果を上げられない職業です。
時には厳しく、時には優しい言葉をかけてあげたり、冗談を言って笑わせたりすることが重要な職業です。
ハラスメントを恐れるあまり、何も話さないという過敏な姿勢をとるのはよくありません。
「あの先生はそんな人じゃない」と日頃から生徒に信頼してもらうことが大切です。
そのためには、日頃から生徒とのコミュニケーションを密にとり、生徒の心をつかんでおく必要があると言えるでしょう。
塾でのハラスメントは多種多様

従業員、生徒、保護者、学校、近隣住民と関わる人が多岐にわたる分、ハラスメントの種類も多種多様です。
一般的には下記の3つが多いのではないでしょうか。
- セクハラ
- パワハラ
- アルハラ
他にも様々な種類のハラスメントがあるため、経営者自身はもちろん、現場の講師もハラスメントに当たらないようにハラスメントの種類を把握しておきましょう。
セクハラ
アルバイト講師に対する「彼氏・彼女いないの?」や生徒の体に触れる行為、冗談半分での性的な発言など、塾講師の言動で最も多いハラスメントがセクハラです。
アルバイト講師とのコミュニケーションでも、異性交遊についての話題は危険といえるでしょう。
また、最も厄介なのが生徒に対するセクハラ行為です。
授業に集中している生徒が気づかずに、思いやりで起こした言動がセクハラになるケースもあります。
例えば以下のようなものは確実にアウト。
- 肩にゴミがついて取ってあげる/肩に手をかけて話す
- 長時間の勉強で疲れてる仕草をしたので肩を揉んであげる
- よくできたねと頭をなでる
- 教えるときに接近しすぎる
視野が広く、生徒を気遣える講師や、指導に熱中しすぎる講師がやりがちな行為ですよね。
特に異性への指導中にセクハラと取られやすいので、個別指導では担当講師の性別にも注意しましょう。
また、ゴミ等に気づいた場合は、絶対に手を出さず、生徒に口頭で伝えるように徹底する必要もあります。
対生徒だけでなく、社員間、講師間の付き合いにも注意しましょう。
例えば、仕事が終わって食事に行こうと異性を誘う場合、二人きりにならないように気をつける必要があります。
過敏になる必要はありませんが、常に相手が不快に感じないよう日頃から意識しておくことが重要です。
パワハラ
アルバイト講師に対して教え方を伝えたり、生徒に解き方を伝えたりする際に起こりがちなハラスメントがパワハラです。
講師経験の長いアルバイトや社員が、経験の浅い講師や理解の遅い生徒に対して「こんなこともわからないのか!」と必要以上に怒鳴るケースもあります。
そのためアルバイト講師や生徒に説明をする際、高圧的な態度を取ってしまうケースも多いです。
- こんな問題も解けないのか!
- さっき説明したじゃないか!
- 前と同じ問題なのになんでわからないんだ!
など、言葉に出さずとも態度に出てしまえばパワハラは成立します。
前述のとおり、相手がどう感じるかがポイントなのです。
人間関係における上下関係を前面に出し過ぎると、セクハラと同様に起きやすいハラスメントといえます。
根気よく常に優しい指導を心がけ、顔や態度、口調に出さない我慢強さが求められると言えるでしょう。
アルハラ
職員同士や教室単位でのアルバイト講師を含めた飲み会などで起きやすいのがアルハラです。
お酒が飲めて一人前と言われる時代もありましたが、現代では全く違います。
一気飲みの強要はもちろん、お酒を勧めるのにも注意しなければなりません。
相手が飲み会が楽しいと思えばセーフですが、無理矢理飲まされたと思われてしまえば立派なアルハラです。
塾以外でも同じことが言えますが、飲み会ではお酒を飲むことを目的にしてはいけません。
お酒はコミュニケーションを円滑にする手段と考えるのがいいでしょう。
手段であれば、強要も生まれませんし、飲ませようという言動も起きないでしょう。
また、飲みたい人だけお酒を飲むようにしたり、あえて食事だけで終わらせるのもいいです。
アルコールには個人差がありますから、お酒の席を設ける場合は、十分に注意しましょう。
その他こんなハラスメントも
現代ではたくさんのハラスメントがあり、塾内部でも起きやすいものも多いです。
室内の温度設定によるエアハラや、子供に対して年齢による差別的発言をするエイハラ、おとなしい生徒に対するコミュハラなど、塾の日常の中にも起こりやすいハラスメントは潜んでいます。
社会的な問題に対する発言もモラハラと取られる場合もありますよね。
他にも、男らしい女らしいなどの発言も子供に注意するときに使われがちですが、これもジェンハラに該当します。
細かく挙げたらキリがないほど、ハラスメントは日常の中に潜んでいるのです。
言葉を発せなければ成立しない塾講師のお仕事。
その一言がハラスメントと受け取られる危険性を特に職員は理解しておかなければなりません。
また、教室長にハラスメントに対する危機管理をきちんと理解させ、アルバイト講師の管理をさせるのも必要です。
一度ハラスメントと受け取られると取り返しがつかないので、十分に注意するよう指導しましょう。
ハラスメントで取り返しがつかなくなる恐れも

塾内でハラスメントが発生すると、塾の評判が落ちるのはもちろん、経営的にも大打撃を受けてしまいます。
一人の講師の些細な言動で、教室が潰れてしまうケースもあるのです。
そのため、経営者はハラスメントを発生させない管理体制を作らなければなりません。
ハラスメントを発生させないためには以下の2点が有効です。
- SNSを使ったコミュニケーション手段を導入しない
- 講師研修を行う
SNSを使ったコミュニケーション手段を安易に導入しない(記録が証拠として残る)
SNSは手軽に連絡が取れるツールですが、これがハラスメントの証拠として残る場合もあるので、利用は避けるようにしましょう。
もちろん、講師と生徒間のSNSでのやりとりを禁じている塾は多いです。
しかし、SNSは正社員とアルバイト講師で問題になるケースが多くあります。
例えば、個別指導時のシフト連絡です。
講師が都合つかなくなり、急に代わりの講師を探さなければならない時はよくあります。
こんな時、「明日、入れる人いませんか?」とSNSで無意識に連絡してしまうことがあります。
この行動自体は大きな問題ではありません。
しかし、早朝や深夜の場合は立派なハラスメントに該当します。
特に塾講師は夜遅い職業なので、時間感覚が麻痺してしまい、23時や24時過ぎなど、深夜でも遅いと思わない人もいるでしょう。
しかし、アルバイト講師にとっては、翌日朝から学校があるケースもあるのです。
これは一例ですが、事実として明確に残るSNSは裁判等でも有効な証拠となります。
バイトを辞めたり、職員が退社する際にSNSへの書き込みを消させる行為も、立派なパワハラとなるため、日頃からSNSを使わないように心がけた方がいいでしょう。
教室で先生研修をする・何がハラスメントにあたるのかのケーススタディを共有する。
各教室での講師への研修はハラスメント防止に有効です。
厚生労働省のホームページには、「職場におけるハラスメントの防止のために」という情報サイトがあります。
信頼できる公式サイトにある情報や資料をもとに研修を行うようにしましょう。
研修を行えば、講師も不安になることがあります。
「こんなことはハラスメントにあたるのか?」「こういうことがあったが今後はやめた方がいいのか?」等、研修参加者側からの質問にも真摯に対応し、過敏な不安感を解消する努力も必要です。
生徒の心をつかんでいれば、ほとんどの言動はハラスメントと受け取られません。
しかし、生徒の心をつかもうと軽はずみな言動を行うとハラスメントに該当してしまいます。これは講師間でも同じです。
塾の仕事は人間関係が非常に大切です。
日頃から些細な言動が相手にハラスメントととられないくらいの信頼を築き上げる必要があります。
このことを、講師全員がきちんと理解できるように伝える機会は、意図的に作る必要があると言えるでしょう。
まとめ

ハラスメントの厄介な点は、相手が不快に感じたらアウトなところです。
相手本位となってしまうため、軽はずみな言動が大問題に発展してしまうケースもあります。
現代ではハラスメントの種類も多いです。
一昔前までは当たり前のように行われていたことも、現代ではハラスメント行為と認定されてしまいます。
そのため、常識的な言動が塾講師はもちろん、社会人には求められています。
塾は様々な人が関り合う場所です。
そのため、ハラスメントと受け取られる言動は絶対に防がなければなりません。
もちろん、生徒と良好な関係が築けていれば、多少の言動はセーフになるでしょう。
しかし、アウトとなる講師の多くは、生徒と良好な関係が築けていると勘違いしているケースが多いです。
そのため、研修等を通じて、ハラスメントととられる言動を共有し、未然防止に努める動きはハラスメント対策として有効といえるでしょう。
公益社団法人「全国学習塾協会」のホームページにも、ハラスメント対応についての指針が公開されていますので、参考にしてください。
\ビットキャンパスの詳細はこちら/