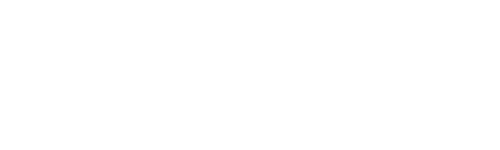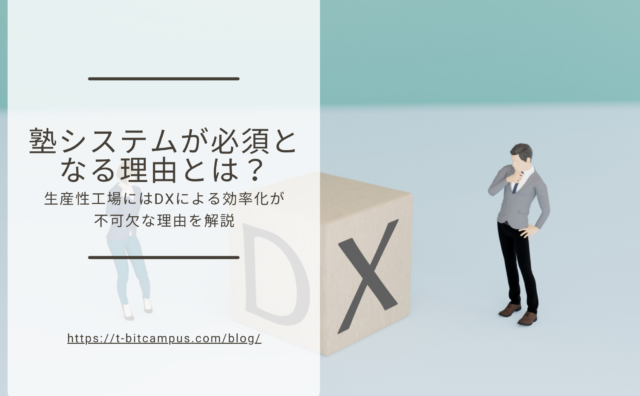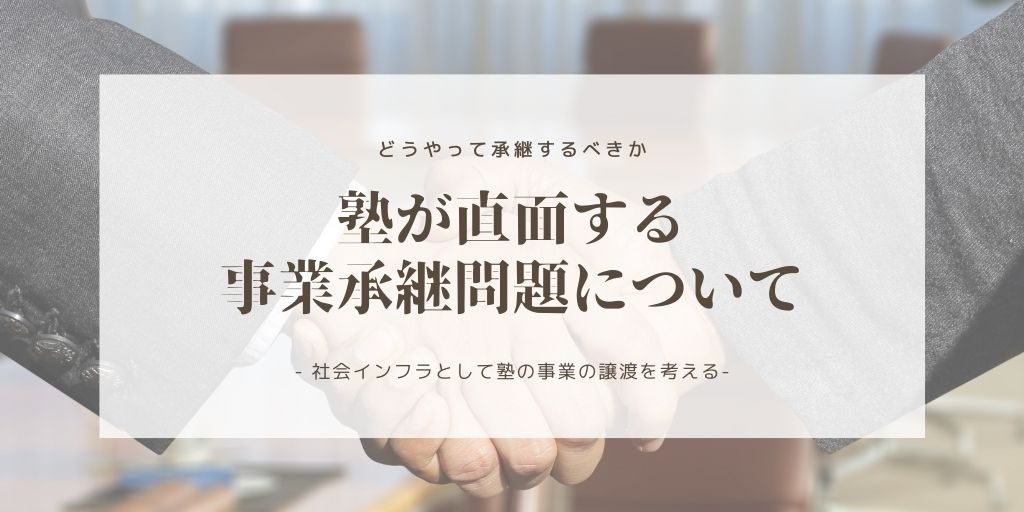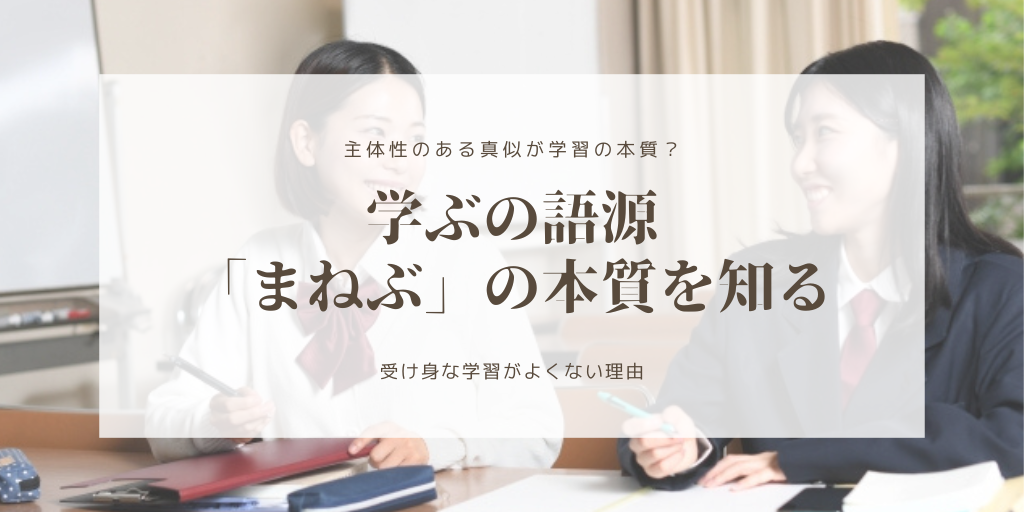どの業界でも企業を存続させるには、次の世代へと継承していかなければなりません。
すんなりと跡継ぎが見つかればいいですが、なかなかそうはいかないケースが多いです。
塾としての基盤を作り、地域に浸透させたのに、一代で終わらせてしまうのは本意ではありませんよね。
そこで今回は、塾の存続の手段についてご紹介します。
事業承継や事業譲渡などの方法論や、スムーズに後継するためのポイントをまとめました。
経営者の方は、未来を見据えてぜひ、参考にしてください。
事業存続に悩む塾経営者は多い

塾経営者が次の世代への事業継承に頭を抱えるケースは珍しくありません。
特に塾業界では「人」が事業の核となるため、特定の問題が顕著になります。
主な懸念事項としては、次の2つが挙げられます。
- 老舗塾の高齢化に伴う存続の課題:長年にわたり地域に根ざした塾も、経営者や主要スタッフの高齢化が進むと、事業の継続が困難になる場合があります。このような状況では、事業の存続と世代交代の計画が重要になります。
- 講師の不足による授業の拡大制限:塾においては、質の高い講師の確保が事業の成長と直結します。講師が十分に集まらない場合、授業の拡大や新しいコースの開設が難しくなるため、人材の確保と育成が大きな課題となります。
塾業界では、これらの問題への対処が事業の長期的な成功に直結しています。
経営者はこれらの課題を認識し、適切な戦略と計画をもって取り組む必要があります。
人材育成、世代交代の計画、そしてビジネスモデルの革新が、塾業界の未来を形作る鍵となるでしょう。
老舗塾の高齢化による存続・事業承継の問題が顕在化
老舗塾の経営者には、後継者問題が深刻な懸念事項として現れます。
これらの塾では、講師の数が多く、経営のキーパーソンとなる幹部クラスのスタッフの年齢層も高い傾向にあります。
多くの場合、現経営者は若い時に事業を立ち上げたため、当初は年齢に関する問題が顕在化していませんでした。
しかし、事業の継続を考慮すると、幹部スタッフの年齢が経営者に近いことが一般的です。
経営者が幹部に後継の座を譲る場合でも、次世代への移行までの時間は限られています。
若手スタッフは、多くが現場指導に従事しており、経営に必要なスキルや経験が不足しているケースが多いためです。
塾の規模が大きいほど、経営者には多角的な能力が求められます。優秀な講師でも、経営者としての資質は異なります。
このため、適切な後継者の選定が難しく、老舗塾は存続の危機に直面することがしばしばあります。
この問題を解決するためには、長期的な視点での人材育成と経営継承計画が不可欠です。
若手スタッフに経営経験を積ませる機会を提供し、適切な時期に経営のバトンを渡す戦略が求められています。
講師が集まらず、授業を増やしたくても増やせない。
塾業界では、少子高齢化の影響を受けて深刻な人材不足が生じています。
講師不足の問題は、次のような要因によってますます複雑化しています。
- 講師になる人の減少: 少子化の進行により、塾講師を目指す人の母数自体が減少しています。
- 新卒講師の高い離職率: 塾業界では、特に新卒入社後3年以内の講師の離職率が非常に高い状況にあります。
- 経験を積むと独立を志向: 塾講師として一定の経験やスキルを身につけた後、独立を目指すケースが増えています。
これらの課題に直面する中で、アルバイト講師を活用して授業を行うことは一時的な解決策に過ぎません。
塾の経営を安定させるためには、長期的な視点で社員の育成と定着を図る必要があります。
優秀な講師がいれば、授業数を増やすことが可能ですが、経験豊かな講師を育成するには、時間と労力が必要です。
子供の成長と同様に、講師の育成にも時間がかかります。
したがって、講師の確保と育成は、塾経営者にとって最優先事項の一つと言えます。
塾と事業承継

塾業界における事業の継続と発展の鍵となるのが事業承継です。
塾の事業承継には主に次の二つの方法が考えられます。
- 親族への承継: 創業者や現経営者の親族、特に次世代の家族メンバーへの事業の引き継ぎ。この方法は、家族経営の塾において一般的で、事業の理念や価値観を維持しやすい一方で、新しい風を取り入れにくい側面もあります。
- 幹部経営陣への承継: 塾の経営に深く関わってきた幹部スタッフや長年の経験を持つ管理職に経営を委ねる方法です。このアプローチでは、塾の現状をよく理解している経営陣が後継者となるため、スムーズな運営の継続が期待できます。しかし、新しい視点や革新的なアイデアを取り入れる機会を逃す可能性もあります。
これらの方法以外にも事業承継の選択肢は存在しますが、最も一般的なのはこれらの二つです。
事業承継を計画する際は、塾の将来的な方向性や継続性、革新性のバランスを考慮することが重要です。
親族への承継するケースが一般的
塾業界に限らず、多くのビジネス分野において、事業の親族への承継は一般的なアプローチとなっています。
親族間での承継は、同じ家庭で育ったことによる価値観の共有や、経営理念の継承が容易であるという利点があります。
このような背景から、次のような特徴が見られます。
経営者を親に持つ子どもが同じ道を選ぶことが多い
親が経営者である家庭では、子どもがその道を志すことが自然と増えます。
事業承継を前提としたキャリアプランニング
家族経営のビジネスでは、子どもが早い段階から事業承継を念頭に置いたキャリアを歩むことが一般的です。
内外部のスムーズな受け入れ
親族による事業承継は、社内外の関係者にも比較的納得してもらいやすい傾向にあります。
しかし、親族内での事業承継が必ずしも円滑に進むわけではありません。
承継者が十分な能力を持っているとの認識がない場合、社内の反発や承継者自身が異なる道を選ぶケースもあります。
このため、親族への事業承継を考える際には、親族以外のスタッフや関係者の意見や反応も考慮する必要があります。
幹部経営陣への事業承継(MBO)
近年、事業承継の方法として、マネジメント・バイアウト(MBO)の採用が増えています。
MBOは、会社の幹部や経営陣が自社の株式を買い取り、経営権を獲得する手法です。
MBOには以下のような目的があります。
- 経営体制の再構築:経営権を完全に取得することで、経営方針や体制の見直しが可能になります。
- 情報公開のリスク対策:上場企業ではなくなるため、情報公開に関連するリスクが減少します。
- 短期的な利益を求める株主からの独立:利益追求に集中する株主の影響を避けることができます。
MBOには意思決定の迅速化や社内意識の改革、機密情報の保護、買収リスクの軽減といった利点があります。
しかし、資金調達の必要性や現株主からの反対など、実行にはいくつかの課題も伴います。
親族への事業承継が難しい場合には、MBOが選択されることが多いです。
塾と事業譲渡
塾経営の継続に関しては、事業譲渡も重要な選択肢の一つです。
事業譲渡の相手として考えられるのは主に以下の3つです。
- 外部の起業家:新しいビジネスアイデアや経営手腕を持つ外部起業家に、事業の運営を委ねることができます。
- 他の塾:業界内の他の学習塾との統合や合併により、リソースを共有し、より大きな経営基盤を築くことが可能です。
- M&Aサイトの活用:ウェブ上のM&Aマッチングプラットフォームを利用して、適切な買収者や合併先を探すことも一つの方法です。
現代の塾業界では、老舗塾やフランチャイズチェーンに加えて、異業種からの参入も見られます。
これにより、事業の譲渡がさらに友好的で実行可能な選択肢となっています。
このアプローチは、新たな経営資源やアイデアを導入し、事業の継続や発展を図るのに役立ちます。
外部の起業家への事業譲渡
外部の起業家は、ビジネスチャンスを常に狙っている方が多いです。
別業界で様々な価値観に触れ、柔軟な発想と鋭い洞察力を持ち合わせています。
そのため、「学習塾」の枠に囚われない、斬新なアイデアで自塾をさらに大きな企業へと発展させる可能性が高いです。
直接的な現場指導ではなく、経営的なマネジメントが主となるため、経営方針や理念を継承させやすいメリットがあります。
自らが歩んできた思想の元での指導が現場で行われるため、職員への配慮も十分にできるでしょう。
競争が激化しているとはいえ、一定の顕在客のいる教育部門へ参入したいと考える起業家が多いのも事実です。
一家庭あたりの教育費も増加傾向にあるため、経営状態によっては有利に事業譲渡の話を進められる場合もあります。
他の塾への事業譲渡
塾業界の競争は年々厳しさを増しており、学生をめぐるエリア内の争いが激化しています。
その中で、存続を模索する際には、他の塾の事業を継承する選択肢が双方にとって大きな利益をもたらす可能性があります。
塾の名前が変わっても、講師が同じであれば、通う生徒たちにとっては混乱を避けることができます。
さらに、自塾の教育手法やコンテンツ、システムと相手の良い部分を組み合わせることで、更に優れた教育サービスを提供できるチャンスがあります。
他塾への事業譲渡を検討する際、相手方の経営者も同じ業界で経験を積んできた者です。
このため、以下のような点で共感を得やすく、Win-Winの関係を築きやすいというメリットがあります。
- 経営者としての共通の悩み
- 現場に対する深い思いやり
- 教育への責任感
- 子供たちへの愛情
これらの要素が、譲渡の話がスムーズに進む助けになり、相互理解に基づいた有意義な交渉が行える可能性を高めます。
WEB上のM&Aサイトでの事業譲渡
WEB上のM&Aサイトを利用して事業譲渡先を探す方法は、人脈を駆使する手法とは異なるメリットがあります。
このアプローチでは、交渉が始まるまで相手と直接顔を合わせることがなく、完全に新しい関係から信頼構築と商談を進めることができます。
この方法の主なメリットは以下の通りです。
- 新しい機会の発見:WEB上のサイトを通じて、様々な投資家や起業家と接触することが可能で、予想外の良い条件で合意に至る場合もあります。
- 条件の明確化:事業譲渡の条件を事前に明確に設定し、納得の上で権利を譲渡できるので、安心してプロセスを進められます。
- 信頼できる相手の選択:多くの候補の中から、自身が信頼でき、任せられると感じる相手を選ぶことができます。
- 断りやすさ:相手が信用できないと感じた場合、断りやすく、自分の本心と塾の将来を第一に考えることが可能です。
- 幅広い選択肢:M&Aサイトを通じて、多様な投資家や企業家とのマッチングが可能で、新しいビジネスの機会を発見するチャンスが広がります。
塾経営者が一生懸命築き上げてきた事業を、次の段階に移行する際、これらのメリットは重要な検討材料となり得ます。
M&Aサイトの利用は、事業譲渡を検討している塾経営者にとって、有効な手段の一つと言えるでしょう。
育てた塾を残すために

塾の存続と次世代への継承は、簡単なことではなく、計画的で継続的な努力が必要です。
事業承継や事業譲渡を考える際には、特に以下の二つの重要な要素に焦点を当てることが重要です。
- 地域での評判の維持:塾の成功は、地域社会での評判に大きく依存しています。良い評判は、新しい生徒や保護者の信頼を獲得する上で不可欠であり、これを維持し続けることが重要です。評判は一朝一夕に築かれるものではなく、日々の努力と質の高い教育サービスによって維持されます。
- 属人的な仕事を避ける:事業の成功が特定の個人や小さなグループに依存する状態は、長期的な存続には望ましくありません。全てのプロセスや業務は、誰でも理解し実行できるようにシステム化することが重要です。これにより、経営者や主要スタッフが変わっても、塾の日常運営に影響が出にくくなります。
これらの要素に注意を払いながら、次の世代への事業の継承や譲渡に向けて準備を進めることが、塾の存続と成長にとって不可欠です。
今後の計画においては、これらの点を早い段階から考慮に入れ、適切な戦略を立てていくことが成功への鍵となるでしょう。
地域の評判を維持しておく
塾の存続と繁栄にとって、地域社会での評判は不可欠な要素です。
良い評判は塾の生命線とも言え、これがなければ事業の継続が危ぶまれます。
地域で高く評価される塾は、事業承継や譲渡の際にも有利な立場に立つことができます。
引き継ぐ側も、評判の良い塾を望みますし、評判が悪い塾の立て直しは困難を極めることが多いです。
悪評があると、たとえ財務的に損益分岐点が低くても、事業譲渡の交渉は難航します。
反対に、地域での良い評判を維持している塾は、譲渡や承継の際により良い条件を引き出せる可能性が高くなります。
このため、事業の将来を見据えた場合、地域の評判を築き上げ、維持することは非常に重要です。
良い評判を持つ塾は、事業譲渡や承継の際にも、より強い交渉力を持つことができます。
そのため、地域での評判を勝ち取り維持する努力は、塾経営において常に優先されるべき事項です。
仕事を属人化せず標準化する
塾経営において、属人的な運営スタイルは様々なリスクを孕んでいます。
特定の講師に依存する状態では、その講師が退職や独立を決意した場合、教室運営に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。
特に塾業界では講師の独立が比較的頻繁に発生するため、一部の講師に過度に依存する体制は避けるべきです。
業務を標準化し、誰でも実施できるシステムを確立することは、事業承継や譲渡を円滑に行うために不可欠です。
これにより、日々の運営や経営の安定性にも肯定的な効果があります。
また、すべてのスタッフが貢献できる環境は、職員のモチベーション向上にも寄与します。
経営者やキーパーソンが変わることによる影響を最小限に抑えるためには、個々の責任領域を適切に分配し、チームとして協力し合う体制を構築することが重要です。
このような体制こそが、経営者の変更時にも揺らぐことのない、安定した企業の基盤を築く鍵となります。
まとめ

塾業界以外でも、事業の存続は非常に難しい問題です。
方法論としては、事業承継と事業譲渡の2つに分かれます。
どちらも準備をしっかり行わなければ、うまくいかないため、事前に事業を受け継ぐための準備を行っておきましょう。
地域の評判をよくすること、社内の業務、責任のバランスを分散させることはその最低限と言えます。
己の信念に従い、ここまでひたすら走りぬき、成功したからこそ直面する事業存続の問題。
次の世代にうまくバトンを渡せるよう、日々の経営から見直し、ステークホルダー全員が納得のい事業承継を成功させましょう。
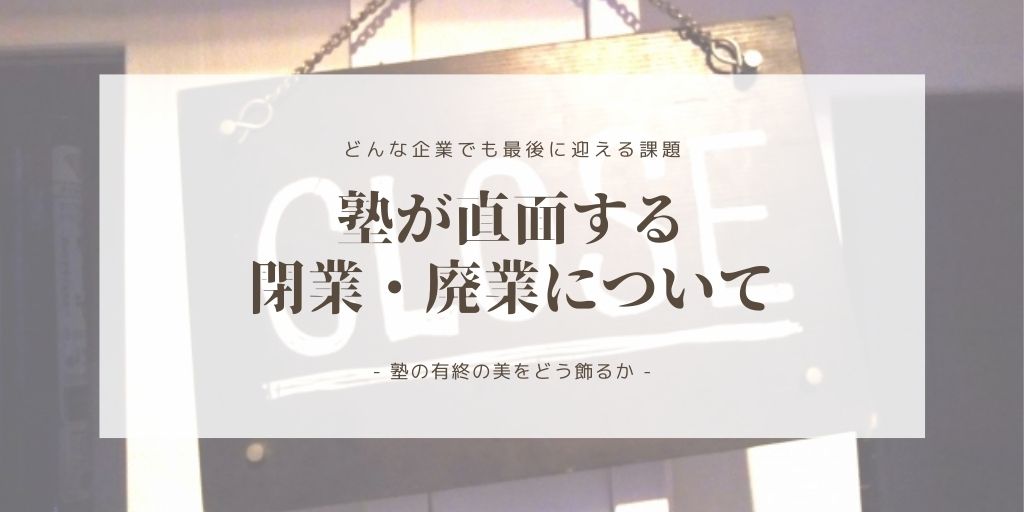
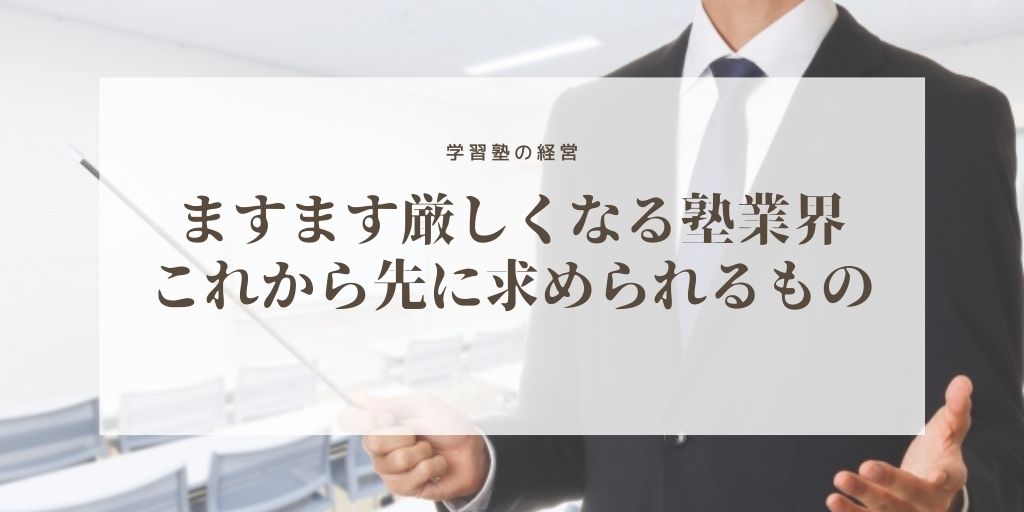
\ビットキャンパスの詳細はこちら/