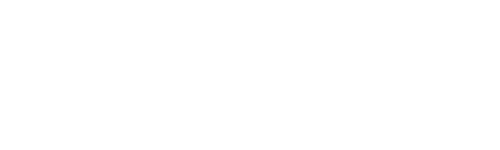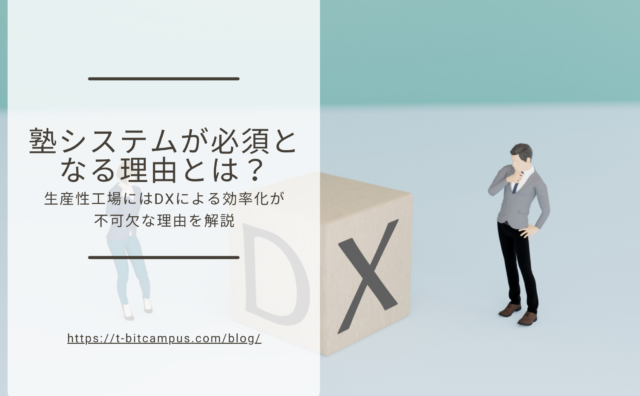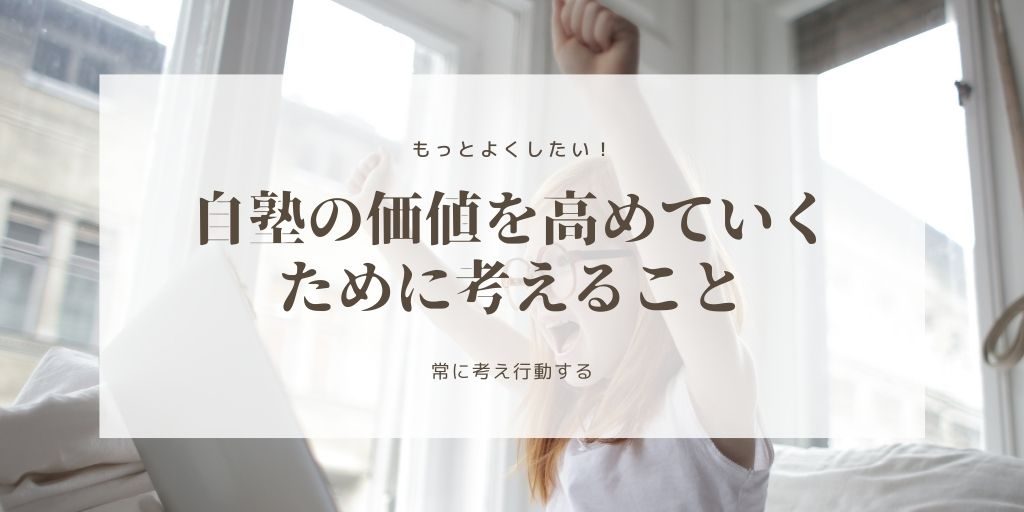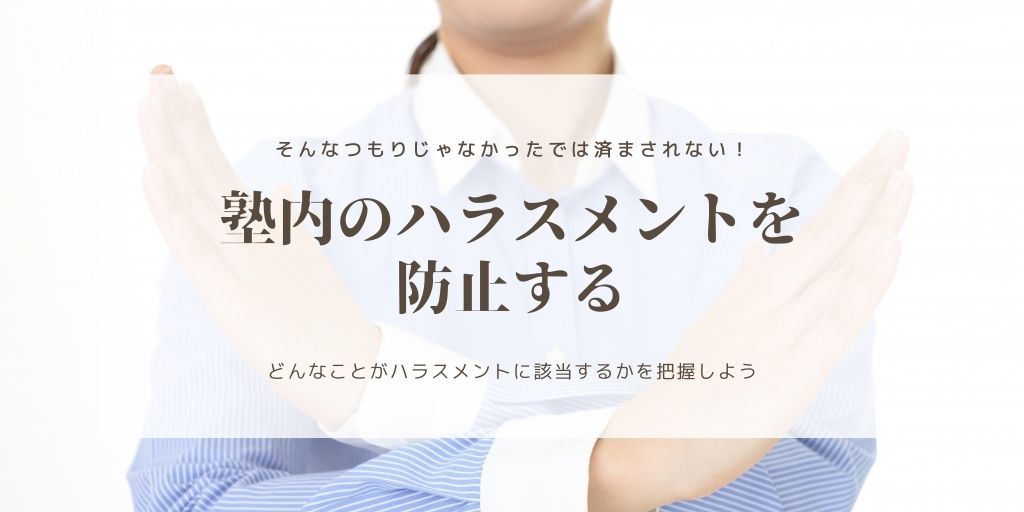競争が激化する塾業界では、よりよい教育を追求し、他塾と差別化を図らなければ事業の継続は難しい時代になっています。
つまり自塾の価値を高めるのは最重要課題と言えるでしょう。
そこで今回は、自塾の価値を高めるためにやるべきことについてご紹介します。
価値を高めるポイントや考え方、方法論についてお伝えしていくのでぜひ参考にしてください。
塾の価値を高めれば売上も増加しやすい

年々少子化が深刻になっており、塾の倒産件数も少しずつ増加傾向になっています。
しかし潰れない塾があるのも事実です。
潰れてしまう塾と潰れない塾との大きな差は、地域での塾の価値にあります。
地域からの価値が高ければ、いくら不況といえどそう簡単には潰れません。
逆に価値が高いと、不況時ほど売上を伸ばせる可能性もあります。
塾の価値を高めるときに大切なのは次の2点。
- 立地条件は変えられない
- 塾の価値は努力で高められる
変えられないものと変えられるものをしっかりと把握し、できることを1つ1つ行っていきましょう。
立地の条件は変えられない
塾は一度建てると立地条件はなかなか変えられません。
そのため塾の立地を決める場合は、収益を出せるかにとことんこだわらなければなりません。
- 学校から遠い
- 住宅街から外れている
- 周りの街灯が少ない
こうした立地条件は、塾を出す前から把握できるはずです。
そのため収益の悪さを立地条件のせいにするのは間違っているのかもしれません。
変えられないものせいにしても、改善には繋がらないのです。
ではどうすべきか。
仮に立地条件の選考に失敗した場合でも、本当に価値のある塾には生徒は集まります。
なかなか生徒が集まらないときは、自社でコントロールできない要因に責任転嫁したくなる気持ちにもなるでしょう。
確かに厳しい場合もありますが、そんなときほど前向きにやるべきことへ意識を集中したいものです。
塾の価値は努力で高められる
生徒の成績を上げることは塾に求められる価値の1つです。
しかし成績を上げる前段階で、地域から塾の価値として認知される点は、下記ようにいくつも挙げられます。
- やる気を与える
- 机に向かう習慣をつける
- 勉強に向かうきっかけを作る
大切なのは自塾でどの価値を上げていくかを明確にすること。
すべてをできるのが理想ですが、現場レベルで考えるとなかなかすべてを行うのは難しいです。
講師や教室の状況に応じて1つずつ目標を与え、乗り越えていく体制を整えましょう。
ぶれずに1つのことをやり抜いていく姿勢は塾の価値へと直結します。
現場の動きが子供や保護者に伝わり、地域に声として広がっていくのです。
塾の価値は努力で高められます。
たった1日では変わらなくとも、続けていけばそれが文化となり、その塾の色となるのです。
現場が一枚岩となって課題に取り組み、どの先生も生徒に同じ目線で向き合うことが塾の価値を上げる第一歩となります。
自塾のポジショニングを今一度考える

募集や成績効果など、思うように伸び悩み始めたときは、地域における自塾のポジショニングを今一度考える必要があります。
成果が出ないのは必ず理由があるのです。
その理由を初心に立ち返って俯瞰すると、突破口は必ず見えてきます。
ポイントとしては下記の3つが考えられるでしょう。
- 大手の真似をしない
- 小規模なら質を高めて単価を上げる
- 教育理念を中心に考える
自分の立ち位置を把握するのは、勉強でも経営でもとても大切なこと。
当てはまる点を精査して突破口を切り開いてください。
大手の真似をしない
原則としては大手の真似をしてはいけません。
大手と同じようなことをしていても大手に敵わないからです。
大手には資金力・講師数・校舎数など、中規模~小規模塾にはない強みがあるため強者の戦略を取れます。
例えば価格を下げること。
大手は単一校舎で赤字覚悟のダンピングをしても別の校舎で賄えるのです。
しかし校舎数が少ない塾ほど、価格のダンピングは不利益を招きます。
教育カリキュラムも同様です。
ITを駆使した通信制度、ネットを利用した学習管理などは、大手が行うとサービスの質がいいと評価されます。
しかし小さな塾が行うと「子供が全然活用しない」「子供がやらないから意味がない」と一蹴されてしまうのです。
大切なのは大手にできないことをいかにやるか。
補習や質問対応、生徒面談できめ細やかな対応を行ったり、学習指導以外に生徒の悩みに正面から向き合ったりなど、塾の価値を高める方法はいくらでもあります。
大手と同じ土俵で戦わず、いかに自塾にしかやれないことをやり切るか。
これは自塾の立ち位置を把握していないとできないことです。
小規模な塾なら質を高めて単価を高める
大手の塾ではもちろん勉強が苦手な生徒や中位クラスの子も通っていますが、優秀な生徒が多い傾向にあります。
一方で小規模な塾では、管轄学校での学年順位上位クラスの生徒は数名の場合が多いです。
これを受け入れることも、ポジショニングを把握するためには大切になります。
小規模な塾では、中位以下の生徒の成績をいかに上げるかが生命線といえるでしょう。
このラインの生徒たちの成績を上げられれば、自ずと地域から認知される塾になります。
しかし中位以下の生徒たちの成績を上げるのはかなり難しいのは言うまでもありません。
もともと勉強に向いていなかったり、勉強嫌いだったりするケースがほとんど。
そのため、こういった勉強に後ろ向きの子供たちをいかに前向きにするか。
これを実行するためのカリキュラムや対応の体制づくりが塾の質を高めるのです。
例えば「勉強をやりなさい」と言わずとも勉強をやらせられる塾。
このような塾が地域で他塾に負けるわけがないですよね。
そして他塾に負けない体制ができれば自ずと質が高まり、価格を上げても生徒は集まります。
小規模な塾は、こうした細やかなフォローを強みとして勝負するべきなのです。
教育理念を中心に考える
教育理念に沿った行動は、生徒や保護者からの信頼に繋がります。
言葉通りの行動は納得感を与えやすいのです。
逆に耳障りのいい理念を掲げていても、現場で実行されなければ不信感に繋がります。
例えば「自力で解ける学力を身に着けさせる」という理念を掲げていたとしましょう。
この理念に基づくならば、家庭学習は多めに出すべきです。
塾という環境で、わからないところをすぐ先生に聞ける状態では効果は得られません。
そして保護者の目に自力で解いている瞬間が映らないのです。
そのため家庭学習を多めに設定し、子供が自力で解いている場面を親に見せてあげなければなりません。
この状況にするためには、塾での下準備が必要です。
分からない状況を生み出さないための解説や定着を図ることや、宿題として課す問題の選別などをしなければなりません。
こういった努力を惜しみなく行い、ようやく理念に基づいた指導を行える塾となるのです。
理念とは「塾の提供するベネフィット」とも言えます。
そのベネフィットを具現化する行動を示すことで、他塾にはない独自の強みとなるのです。
生徒の成績向上を第一に考える

塾の価値を高めるために一番必要なのはやはり成績向上です。
現場での行動のすべては、生徒の成績を上げるための手段にすぎません。
成績を上げられない塾は、自ずと淘汰されてしまいます。
そのため塾の価値を高めるためには、生徒の成績向上を第一に考える必要があるのです。
生徒の成績を上げるために見直すべきポイントは次の3つ。
- カリキュラム
- ITを利用した教材やアプリの活用
- 他塾の良いところを真似る
他にも色々とできることはありますが、この3つが着手しやすいのでおすすめです。
カリキュラムを見直す
多くの学習塾では、一度策定したカリキュラムを長年変更せずに使用しています。
これらのカリキュラムは、経験豊富な講師によって作成され、作成当初は最適なものと考えられていることが多いです。
ただ、教育環境は常に進化しており、生徒の学力水準や学年ごとの学力差は年々変わっています。
現代の教育では新しいタイプの問題が増えていることもあり、昨年までのカリキュラムが必ずしも今年に通用するとは限らないのです。
生徒の成績が特定の単元で低下している場合、それはカリキュラムの見直しを検討すべきサインです。
しかし、多くの塾ではカリキュラムの改訂には消極的な傾向があります。
「あの先生が作成した問題は難しい」「平均点が下がっている」といった理由で変更を躊躇することが一般的です。
しかし、こうした状況こそが、より良い指導への道を切り開く機会です。
一度築かれたカリキュラムを再構築するのは困難な作業ですが、それこそが質の高い教育へのコミットメントを示すことに他なりません。
講師の負担は確かに増えるかもしれませんが、教育の質を高めるためには、カリキュラムの定期的な見直しと更新が必須であることを肝に銘じておくべきです。
ITを利用した教材やアプリを活用する
現代の学習塾において、カリキュラムの改革と並行して、IT技術の活用は極めて効果的な戦略です。
ITツールやアプリケーションを利用することによって、生徒たちの学習量を増やすことができ、それも職員の追加的な労力を必要とせずに実現可能です。
例えば、生徒の苦手分野を特定しやすくするシステムや、定期テストに向けての学習優先順位を明確化するツールなどがあります。
これらは次のような利点を持ちます。
- 生徒が苦手とする特定の問題や単元を明確に特定できる
- 解説付きで、関連問題に即座に取り組むことができる
- 生徒の苦手なポイントが視覚化され、理解の助けとなる
もちろん、「紙とペン」による学習の重要性を否定するものではありません。
伝統的な学習方法もその価値を有しています。しかし、テクノロジーが日進月歩で進化する現代において、学習塾がITの力を無視するのは時代遅れとも言えます。
重要なのは、これらのツールの使用方法です。
多くの塾では、生徒自身にITツールの使い方を委ねきってしまっていますが、これが保護者からの誤解、「ネットでの勉強は効果がない」という誤解を生む原因になっています。
コロナ禍でオンライン学習への認識が変わりつつある今、ITをまだ導入していない学習塾にとっては、このチャンスを活用する絶好の機会と言えるでしょう。
他塾の良いところを真似る
学習塾の講師の多くは、自分たちの指導方法に自信を持っていることが一般的です。
自らの指導法にプライドを持つことは素晴らしいことですが、それだけに留まらず、外部の知見にも目を向ける必要があります。
自塾の環境だけに固執していると、新しいアイデアや刺激が得られず、講師の成長が停滞し、結果として生徒の成績向上にも影響が出てしまいます。
生徒やその保護者は、他の塾の指導方法も耳にする機会があります。
学校や地域社会での会話を通じて、他の塾で行われている効果的な指導法が共有されることも多いのです。
そのような外部の情報に敏感で、それを自塾に取り入れることができる講師は、塾にとって非常に価値のある存在です。
良いアイデアは、まずは模倣から始まることもあります。
模倣を通じて理解を深め、そこから独自の改良や工夫を加えていくことで、オリジナルの方法を生み出すことができます。
このプロセスは、新しいアイデアをゼロから生み出すよりも効率的で、少ない労力で大きな成果を得ることが可能です。
ただし、模倣があからさますぎると問題を招くこともあるので、その点には注意が必要です。
他塾の長所を見極め、自塾の教育方針に合わせて取り入れることは、効果的な手段と言えるでしょう。
塾の環境を整備する

学習塾の価値は、単に提供する教育内容だけにとどまりません。
生徒が学びやすい環境を整えることも、塾の重要な役割の一つです。
生徒が集中しやすく、モチベーションを高めやすい環境を作ることは、成績向上に間接的ながらも大きな影響を及ぼします。
これは、勉強に集中できる雰囲気を作り出すことによります。
塾の環境を整える上で注目すべきポイントは次の3つです。
①清潔で快適な環境を保つ
教室は常に清潔に保ち、整理整頓された状態を維持することが重要です。
生徒が快適に過ごせる環境は、学習効果を高めるための基本条件です。
②教師の身だしなみを整える
教師の外見も生徒に与える影響は大きいため、清潔感ある身だしなみや適切な服装を心がけることが必要です。
教師自身が模範となり、学習に対する真剣な姿勢を示すことで、生徒の学習態度にも良い影響を与えます。
③BCP(事業継続計画)を考える
災害や緊急事態が発生した場合に備え、教室の安全確保や授業の継続計画を立てることも重要です。
生徒や保護者に安心を提供するために、万が一の時の対策をしっかりと準備しておくことが求められます。
これらのポイントを押さえ、生徒が学びやすい環境を整えることが、塾の価値を高めるためには欠かせない要素となります。
①清潔な環境を保つ
清潔で整頓された環境は、生徒の学習意欲を高める上で非常に重要です。
確かに、環境が整っていなくても勉強できる生徒はいますが、学習環境を変えることで集中力を高める生徒も多いのです。
塾の自習室や図書館など、異なる環境で勉強することで気持ちのリセットが可能になります。
自宅という日常の環境では、つい先延ばしにしてしまうことがよくあります。
これは、環境が変わらないために、勉強への意欲が湧きにくいことが一因です。
一方で、塾のような清潔で快適な環境では、生徒は新たな気持ちで勉強に取り組むことができます。
清潔な教室は、生徒にとって最適な勉強スペースとなります。
逆に、整理整頓されていない環境では、生徒の集中力が低下してしまいます。
忙しい日々の中でも、清掃を怠らずに整えた環境を保つことは、塾経営者にとっても重要なポイントです。清潔で整頓された環境が、生徒の学習効率を上げるための第一歩となるのです。
②教師の身だしなみを整える
教室の清潔さと同じくらい、教師の身だしなみも学習塾の品質を示す重要な要素です。
着こなしの乱れたスーツ、整えられていない髪型や無精ひげは、教師のプロフェッショナリズムを損ないます。
教師が清潔で整った身だしなみを心がけることは、ただの外見上の問題ではなく、教育に対する姿勢を示すことでもあります。
きちんとした身だしなみの教師は、生徒にも良い影響を与えます。
教師がしっかりと身を整えていることで、生徒も自然と集中力を高め、真剣に取り組む姿勢になるのです。
生徒は教師の振る舞いや態度をよく観察しており、教師の外見もその一部として意識されます。
身だしなみは教師のプロ意識を反映するものであり、これを大切にする教師は生徒を正しい方向へ導く力があります。
成績向上だけでなく、生徒に良い影響を与えるためにも、教師自身の身だしなみには十分に注意を払うことが重要です。
教師の身だしなみは、教育の質と生徒のモチベーションに直結するため、見た目だけではなく、塾の教育方針の一環として位置付けるべきです。
③BCP(事業継続計画)を考える
新型コロナウイルスの流行は、学習塾の経営にも大きな変化をもたらしています。
収束したと思われる現在でも、今後も変わらず予測不能な状況が生じることは間違いありません。
我々が日常的に享受している教育環境が一変する可能性はいつでもあり得るのです。
このような状況において、教育機関としての柔軟性が問われています。
具体的には、IT技術を駆使した遠隔授業の導入がその答えの一つです。
リモートワークが多くの職場で実施されるように、塾業界でもオンラインでの指導の可能性が高まっています。
この変化には家庭のインターネット環境への対応も重要です。
パソコンだけでなく、タブレットやスマートフォンなど多様なデバイスへの対応が求められます。
教室での対面授業は引き続き重要ですが、非常時にも適応可能なIT環境の整備は、今や必須と言えるでしょう。
全てをデジタル化する必要はありませんが、万が一の状況にも対応できるよう、オンライン授業の準備をすることは、教育者としての責任でもあります。
塾の役割は変わりませんが、その提供方法は時代と共に進化していく必要があるのです。
今、ITを活用し、どんな状況にも柔軟に対応できる環境を築くことが、学習塾の新たなチャレンジとなっています。
まとめ

学習塾の価値を向上させる方法は多岐にわたります。
自塾の位置づけの再検討、教育理念の再定義、他塾からの学び、自塾のカリキュラムやサービスの改善など、これら全てが重要です。
しかし、これらの問題に対する明確な答えを出すことは容易ではありません。
多くの場合、答えを見つけるのは困難ですが、それこそが経営者の重要な役割です。
現場で働く講師一人ひとりがこのような視点を持ち、日々の活動に取り組むことで、塾の環境は確実に良くなっていくでしょう。
生徒たちにも常に伝えているかと思いますが、何より大切なのは諦めないことです。
解答の出ない問題に対して、諦めてしまうと何も変わりません。
常に考え、苦しむことからこそ、成功の兆しが見えてくるものです。
この絶え間ない努力と行動を通じて、塾の価値を高め、より良い教育環境を築き上げていくことが私たちの使命です。
\ビットキャンパスの詳細はこちら/