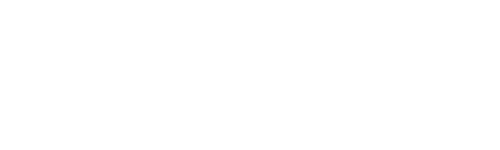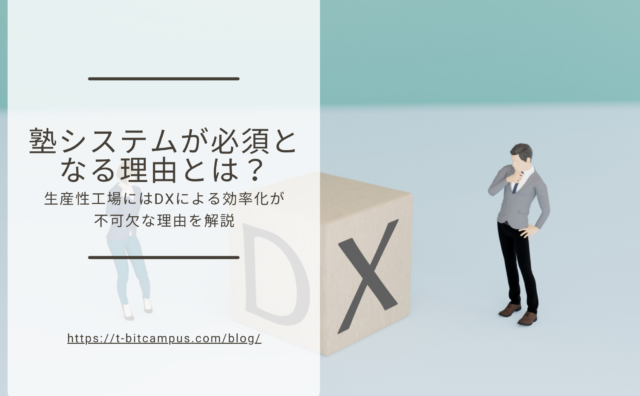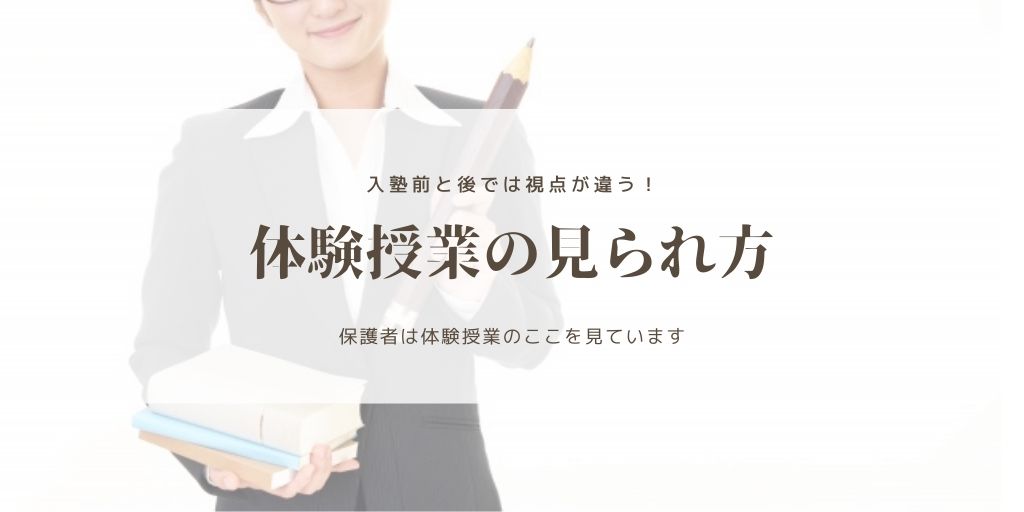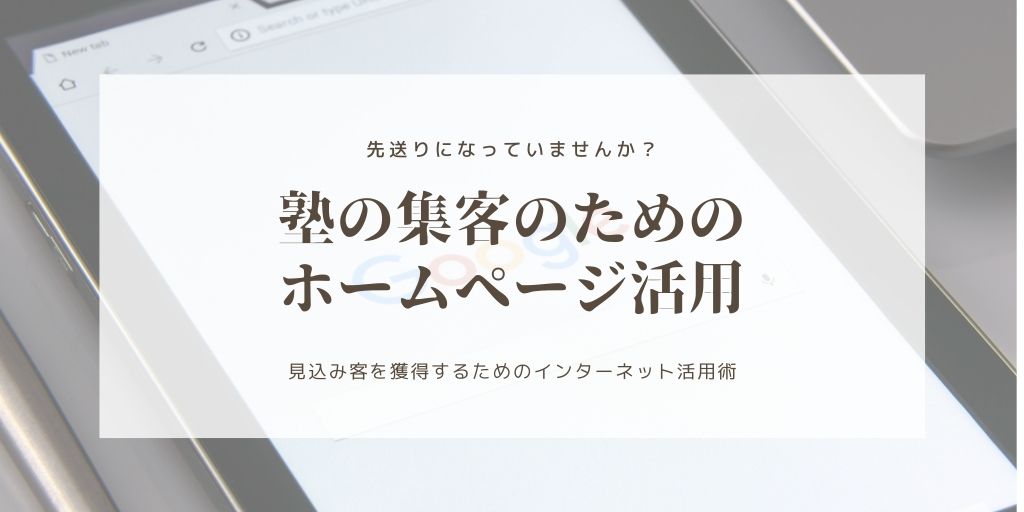2019年に発生した新型コロナウイルスにより、日本ではこれまで約3,300万人が感染しました(2023年4月厚労省調べ)。
これは日本の人口の約26.5%に相当します。
学習塾に通う生徒は10代の若い世代が多いため、感染しても重症化リスクは低いと言われていますが、教室という密な空間が前提になるため、一人が感染すると複数感染するリスクは高いと言えます。
集団授業の塾の場合、クラス担当の先生が感染すると、そのクラスは休講せざるを得ないどころか、教室全体が休校になる可能性もあります。塾経営には大打撃となります。
受験直前期であれば、子どもの人生まで左右することになりますから、慎重に、愚直にコロナ対策を徹底し続けることが重要です。
さらに、2023年5月からは、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されました。
2類から5類移行に伴い、感染防止対策は個人や事業者の判断による自主的な取組が基本になりますので、より一層、各塾の基準の明確化と感染防止対策が求められる時代です。
そこで今回は、塾が取るべきコロナ対策についてご紹介します。
塾業界の状況や、すぐに始められる対策、一歩進んだ感染対策、そして経営的な目線ですべきことをお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
新型コロナで塾業界も厳しい状況に
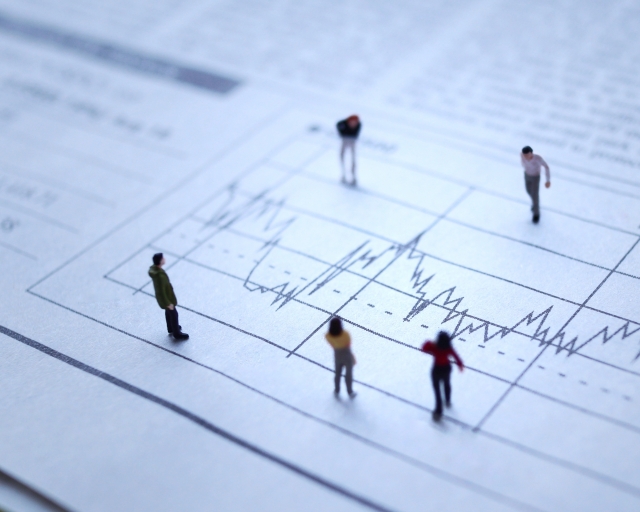
新型コロナで厳しい経営を強いられているのは、サービス業だけでなく、製造業、加工業、農業など、幅広い様々な業界に悪影響が及んでいます。
塾業界も新型コロナにより厳しい状況に立たされています。
全国各地で塾のコロナ倒産が現実のものとなっているのです。
全国で塾のコロナ倒産が現実のものに
5年ごとに調査されている総務省「経済センサス活動調査」によれば、2021年の学習塾事業所で廃業に追い込まれた事業所数は、17,568事業所となりました。2016年の廃業事業所数は9,639事業所でしたので、約1.8倍に急増しています。
ゆとり教育の弊害やリーマンショックの影響が懸念されていた時、「勉強を遅れさせてはいけない」という意識が強くなり、塾に通わせる保護者は増えました。
しかし、今回のコロナの影響は、これまでとは違った様相を示しています。
感染を恐れて通塾を控えた結果というより、他業界の景気が悪化して家計に余裕がなくなり、これまで聖域とされてきた教育費が削られるようになったと見た方が良いでしょう。
経産省の「特定サービス産業動態統計調査」によれば、2023年8月時点になっても、塾の受講生数は前年同月比でマイナスになっています。
もちろん、コロナの影響によるものだけとは限りません。少子化による入試競争倍率の低下、推薦入試の増加等も影響しているものと思われます。
重要なことは、世の中がどのように変化しても、「この塾に通わせておけば安心」という信頼を市場で勝ち得ることです。
まさに「ピンチはチャンス」。今はその信頼を勝ち取り、他塾と差別化する絶好の機会と捉えましょう。
塾が取るべきコロナ対策は至ってシンプル

世の中がどのように変化しても、「この塾に通わせておけば安心」という信頼を勝ち得るチャンスと述べましたが、コロナ対策における地域の信頼は、どのようにすれば得られるのでしょうか。
塾が取るべきコロナ対策は、
- 密の回避と十分な換気
- 手洗い・除菌・マスク着用の徹底
- 健康状態の管理
の3点が重要です。
何事も基本に忠実に、きちんとやりきることで、信頼を勝ち取りましょう。
密の回避と十分な換気
教室内で密を回避するためには、次のようなルールを設ける必要があります。
・座席の間隔を1メートル以上空ける
・授業での生徒の発表はできるだけマスクを着用する
・塾内での食事は地域の学校給食の状況に準じて行う
座席の間隔については、指導形態によって変える必要があります。
集団授業の場合、長机であれば2人掛け、机であれば間隔を1メートル空けて着座するようにすれば良いでしょう。
個別指導の場合、ブースとブースの間隔を1メートル空けるようにします。
塾内での食事は、地域の学校給食のルールに合わせないと、「学校がこうしているのになぜ塾では違うのか?」というクレームを招くことになります。何より、生徒が混乱します。
十分な換気については、下記の点に気を付けましょう。
・少なくとも30分に1回(数分間)窓を開けるようにする
・教室の換気扇は常時作動させておく
・教室のエアコンは「換気モード」「外気取込モード」を定期的に作動させる
換気扇がない教室や、窓が一つしかない教室の場合、扇風機やサーキュレーターを部屋の内側から外側に向かって空気の流れを作ることが大切です。
天井埋め込みタイプの業務用エアコンは、室外の空気との交換が行えないものが多いですから注意しましょう。
手洗い・除菌とマスクの着用
生徒に手洗いやアルコール消毒などの除菌、マスクの着用を徹底させましょう。
そのためには、入口などで講師が生徒をチェックするのが確実でしょう。
例えば、
- 手洗い場付近にアルコール消毒を持った講師を立たせる
- 教室に入る前(玄関でも可)に、講師が実施しているか確認する
- 生徒に教室内での待機を徹底させ、講師がチェックに没頭できる環境を作る
などがあります。
教室に手洗い用の石鹸や消毒液を置く場合、「消毒」と「除菌」の違いにも注意が必要です。
「消毒」は、菌やウィルスを無毒化するものを指します。一方、「除菌」と書かれているものは、菌やウィルスの数を減らすことを指します。できるだけ「消毒」と書かれたものを使用しましょう。
また、トイレ等に手拭き用のタオルを置いている場合は、菌が付着している可能性がありますので、原則使用禁止にしましょう。
マスクについては、「不織布マスク」を使用するにようにします。一時期よく使われたフェイスシールドは、他の人の飛沫から自分を守るものであり、マスクの代用にはなりません。使用する際は、マスクをつけてから使用しましょう。
健康状態の管理
登塾時には、入口で体温をチェックするようにしましょう。飲食店やホテルに常備されているような、顔を近づけると自動で体温が測定されるものが良いでしょう。
生徒も先生も、原則として37℃以上熱がある場合、登塾を控えてもらうようにします。
発熱や咳、倦怠感、のどの痛みなどがある場合、すみやかに病院で受診するよう促してください。
病院で発症が認められた場合、「濃厚接触者」も感染の疑いがあります。病院で発症が認められた日を「発症日」とした場合、その前2日間以内に発症者と長時間接触したことのある人は「濃厚接触者」の可能性があります。その場合、念のためPCR検査を受けるよう促しましょう。
細かい判断基準は、各自治体のホームページにも記載されているので参考にしてください。
大切なことは、健康管理を塾としてしっかり行っていることを示すことです。日頃から健康管理に気をつけ、体調に変化が出た時には塾内の報告・指導体制ルートをきちんと構築しておく必要があります。
「コロナ対策をしっかりしている」と認知されるために、基本的なコロナ対策を100%行うように努めましょう。
>>新型コロナ禍における塾の役割とは?教育分野で社会へ貢献する
更に新型コロナ対策を一歩進める

王道のコロナ対策は、どのような形態の塾でも絶対に行わなければなりません。
加えて、新型コロナ対策として、一歩進んだシステムの導入を行うと、生徒や保護者からの信頼は厚くなります。
大規模の塾では、以前から対応が行われているものもありますが、中小規模の塾では遅れがちになっている、
- リモート授業の導入
- 映像授業の導入
- 基幹システムのクラウド化
の3つを検討し、コロナ対策の先を行く体制を構築しましょう。
初期投資が必要な部分はもちろんありますが、「この塾に通わせれば安心」「勉強を遅れさせない塾」という地域の信頼を得るためには必要な投資です。
塾に行けなくなっても、授業や学習進度を遅らせない体制づくりは、コロナ対策以外にもインフルエンザによる休校や地震等の災害時にも有効ですから、積極的に取り入れるようにしましょう。
リモート授業の導入
スマホやタブレット、PCにより、リアルタイムで授業を受けられるリモート授業が有効です。
空間が教室からネットに変わっただけなので、きちんと生徒が授業を受けているかもチェックできます。
最近は、リアルタイムではないですが、教室内にスマホと三脚を立て、欠席者補習用に授業を動画撮影している塾もあります。
保護者は先生の生の授業を受ける機会はほとんどありません。
そのため、リモート授業を機に保護者に授業を見てもらうチャンスでもあります。
保護者に授業を見てもらい、「良い」と感じさせられれば口コミに繋がる可能性があるのです。
普段、子供から「わかりやすい」「楽しい」だけ聞いているよりも、もっとリアルな口コミが生まれるでしょう。
何かが変われば、マイナスはありますが、プラスも必ず生まれます。
通常授業とは別にリモート授業の体制も準備しておくことは大変ですが、休校は突然やってきます。
「この塾に通わせていれば安心」という信頼感を得るためには、急な変化に速やかに対応できるよう、日頃から取り組んでおくことが効果を発揮するのです。
映像授業の導入
映像授業を取り入れることも非常に有効です。
自塾で映像授業を提供する場合、1人の講師が授業を録画するだけで済みます。
今は機材も、スマホと三脚だけで高画質な映像を制作できますので、コストもかかりません。
授業スキルの高い講師の授業を映像授業化すれば、授業品質の標準化にも貢献します。
外部の映像授業システムを利用するのも、コストはかかりますが選択肢の1つです。
急増している不登校生徒の対策コースとして映像授業コースを開校し、コロナ感染による休校等、不測の事態が起きた場合には、その補完システムとして活用することも可能です。
家庭でも受講できるタブレットAI教材も有効です。AIが生徒の弱点や取り組むべき問題を自動で対応してくれますので、先生の負担が激減します。進捗状況もインターネット経由で離れたところから確認できますので、非常時でも平常時と変わらない指導が実現できます。
基幹システムのクラウド化(自宅待機になってもアクセス可能な環境づくり)
生徒への対応はもちろん、先生やスタッフへの対応もコロナ禍の事業継続には必須となります。
そこで、基幹システムのクラウド化が重要になります。
生徒が塾に来られないときでも学習指示が出せる状況や、担当の先生への指示やアドバイス、業務連絡がいつでも、どんな状況になってもできる環境は絶対に作らなければなりません。
東日本大震災や地方での大地震、コロナ禍の状況が教えてくれた教訓は、「いかなる状況でも事業継続できる体制を構築しておくこと」です。
一般的に「BCP(Business Continuity Plan)」(事業継続計画)と言われるものですが、災害時にもできるだけ損害を最小限に抑えながら事業継続できるよう、日頃から計画を策定しておく取り組みです。
東日本大震災時には、教室のPCに生徒の連絡先や成績情報を保存していたため、津波で流されたり、水に浸かって情報が消えてしまった塾が多くありました。
2009年には、パンデミックと呼ばれた新型インフルエンザによる学校休校が突然発生し、長期間塾を休校にせざるを得ない塾が多くありました。
突然でしたのでどの塾もパニックに陥りましたが、その際も、日頃から自宅からでも業務が遂行できる体制を整えていた塾が、損害を最小限に抑えることができました。
集団授業の塾は、ひと月に授業休講を2回以上すると、年間カリキュラムを消化するのが難しくなります。「塾がないのに授業料をとられるのか」というクレームも多発し、返金処理や売上維持に苦労する塾が多くありました。
いざという時には、塾に来なくても業務が遂行できるよう、システムのクラウド化に取り組むべきです。
先生やスタッフが出社できなくても、指示や連絡等の情報共有を円滑に進めることができれば、Zoomによる自宅からの授業配信や映像授業配信、AI教材の活用等と合わせ、事業を継続することができます。
現在は、生徒の授業管理だけでなく、塾の業務管理も1つのシステムでできるサービスも提供されているため、気になる方はぜひ、一度検討してみてください。
>>ビットキャンパスとは?塾が開発した塾のためのシステムをやさしく解説
まとめ

新型コロナの影響は、塾業界にも大打撃を与えています。
全国各地で倒産が相次ぐ中、対応に遅れた塾から淘汰されていきます。
コロナ対策として、王道の対策を徹底して行い、チャンスがあればリモート授業や映像授業、基幹システムのクラウド化を図り、Withコロナの状態を作ることも必要になっています。
そのことは、「何が起きても安心な塾」として地域の評判につながり、塾のブランド力向上につながるチャンスでもあります。
さらには、塾を存続させていくために、事業継続計画(BCP)を策定する絶好の機会にもなります。
備えあれば憂いなしです。
今から備えを盤石にしておきましょう。
\ビットキャンパスの詳細はこちら/