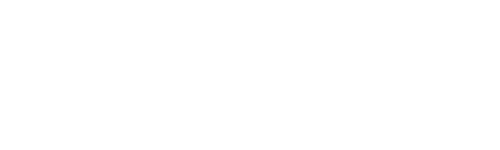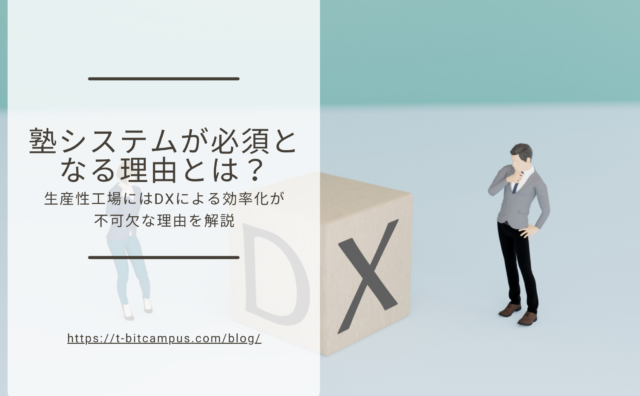塾の料金設定は、健康的な経営や教室運営を行うために必要不可欠です。
なんとなくの料金設定では、地域からの評価を得られるのは難しいでしょう。
塾ではよく1コマ単価で考えられますが、トータルでどのように考えるかが大切です。
そこで今回は、塾の料金設定についてご紹介します。
料金設定のポイントや全国平均をどう考えるか、保護者支店の費用の考え方などをお伝えするので、ぜひ参考にしてください。
料金設定は塾経営の重要事項

塾の経営において、料金設定はとても重要です。
塾の収益は生徒単価×生徒数と、シンプルな計算で算出されます。
その収益を使って、講師を雇ったり、教室の美化を保ったりしなければなりません。
料金設定時のポイントは、
- 低価格路線でいくか、高価格路線で行くか
- 無料戦略
- 小規模の場合は生徒数を絞り高単価にする
の3つです。
平均的な料金にするのではなく、提供するサービスの質に見合った価格設定である点が大切だと言えるでしょう。
低価格路線と高価格路線
たくさんの生徒を集めるのか、一定の人数を確保してサービス提供を行うのか。
まずはここで塾の経営方針が大きく分かれます。
低価格路線の場合は、多くの生徒を集めなければ赤字です。
しかし、価格が安い分、入塾率を高められるメリットがあります。
一方で高価格路線は、少ない人数でも経営が行えますが、よほどの質を確保しなければ、入塾率、継続率を高められません。
まずは自塾の方向性を定め、方針に合った価格設定を行いましょう。
正直なところ、どちらのニーズも高いのが現状です。
安くてしっかり見てくれるところがいいという声もあれば、高くても成績を上げられる塾を選ぶ方もいます。
地域の世帯収入や生徒の学力状態なども踏まえ、地域にフィットした戦略を打ち出し、価格設定を行いましょう。
無料戦略~成功のポイントは内部充実!無料で来た生徒が隣の席の既存生にびびらないといけない~
現在の学習塾では、ほとんどの塾で体験授業や説明会が無料で行われています。
この戦略を具体的に設定するのも、とても大切です。
安い塾の場合、価格が魅力となるので、よりよい授業ができれば、入塾はほぼ決まりになるでしょう。
一方で高い塾だと、価格のハードルはあるものの、授業の質に触れ、入塾したいと思わせられれば入塾させられます。
どちらも「授業がいい」と思わせないと入塾させられないのです。
体験授業では、体験性が既存生に対して「すごい」と感じさせなければなりません。
例えば、
- 同じ学校に通っていて、体験生より成績が悪い子が、自分よりスラスラ解けている
- 既存生の解くペースが速い
- 既存生が静粛に、集中して授業に取り組んでいる
など、学校と違う一面を見せられると、感情を動かせられます。
この「すごい」の感情が期待感へと変わるため、体験授業では周囲を上手に使う戦略も必要になるのです。
小規模塾の理想は生徒数を少なく高単価で(低価格で生徒数が多いと手がまわらない)
小規模の塾の場合、広告費や維持費などの点で大手に太刀打ちできない場合が多いです。
そのため、小規模塾が低価格路線でいくと厳しくなります。
講師の給与、労働条件も大手には適いません。
そうなると、生徒の確保だけでなく、講師の確保、つまり授業の質の維持が難しくなります。
小規模塾の場合は、生徒数の見積もりを少なくし、高単価路線で行った方がうまくいくケースが多いです。
授業や各種サービスの質を高めることに特化し、塾生の満足度を上げていきましょう。
すると、次第に声となり、入塾者が増えてきます。
その際、「満席」「入塾予約」まで生徒を確保できれば安泰でしょう。
軌道に乗せて、経営が安定したら多少のダンピングをするだけでも消費者には良く映ります。
そのため、生徒確保が難しくなっても息を吹き返すまでのスパンを短くできるメリットもあるのです。
塾の料金設定の全国平均とは

塾の全国平均は以下の通りです。
- 中1生 … 10,000円
- 中2生 … 15,000円
- 中3生 … 30,000円
ですが全国平均は、あくまで全国平均です。
ここだけを見て価格設定をするのは危険なので、絶対にやめましょう。
価格平均の考え方は、
- 全国平均は参考程度に考える
- 近隣の塾と比べてどうするか
の2点が大切です。
ネットが普及して情報が得やすくなった現代だからこそ、他塾の動向は必ず押さえるようにしてください。
塾の料金の全国平均は参考程度に考える
塾料金は地方よりも都会の方が高い傾向にあります。
都心部などでは、地方がびっくりするような料金設定が当たり前のケースも多いです。
そのため、全国平均より高くても、地域的に見たら安いケースは多くあります。
逆に、全国平均より安くして、地域的に激安となるケースもあるため、バランスが必要です。
ただし、全国平均は1つの指標として絶対に参考にしなければなりません。
それは、家庭の教育費にかける額の現状を把握する必要があるからです。
現代では上昇傾向にあった教育費も、新型コロナの影響で今後、下がる可能性もあります。
逆に、新型コロナが落ち着いて、教育費にかける額が大幅に増加する可能性もあるのです。
全国平均に固執しすぎてはいけませんが、1つの指標として経営者は把握しておかなければなりません。
近隣の塾より高くするか安くするか?
近隣の塾の価格は絶対に把握しましょう。
サービス形態や質と価格のバランスから自塾の適正価格が見えてくるはずです。
塾経営者の中には、自分の指導が他に負けていないと漠然と考えている方もいらっしゃいます。
授業スキルや理念が仮にそうであったとしても、評価をするのは経営者ではなくあくまで消費者です。
特に塾は結果が出るまでに時間のかかるものでもあるため、本来の力が結果に反映されるまでに時間がかかります。
そのため、地域の口コミを手っ取り早く広げるなら、差別化を図るべきです。
同じ価格なら、よりサービスのいい方を選びますよね。
近隣の塾がやっていないサービスを実施すれば、自塾の強みとして地域に名が知れ渡る時間を短縮できるのです。
価格も全国平均よりも近隣の塾と比べられる傾向にあるため、地域の塾の価格とバランスを考えるようにしましょう。
>>塾の集客に紹介・口コミは欠かせない!在校生からの紹介が増えない理由とは?
保護者の考える塾の費用

塾側の立場として「高い」「低い」はあくまで近隣塾とのバランスの上での論理。
大切なのは、保護者が塾の費用をどう考えるかです。
安さ思考の保護者もいますが、やはり現代は質にこだわる保護者が増えています。
ポイントは、
- 子供の塾にかける費用は年々増えている
- 高額でも質のいいものを選ぶ
- 成績が上がっていれば追加費用も出してくれる
の3つです。
保護者が子供の塾にかける費用は年々増加
学習指導に重きを置ける塾は、第二の学校と呼ばれるほど世間からのニーズを勝ち取る存在になっています。
一昔前までは、「学校の授業を聞いていれば塾は必要ない」という親御さんもいらっしゃいましたが、今ではかなり少数派の意見でしょう。
学校では生活指導も並行して行われているため、学習指導へ尽力できない教師も多いです。
以前は学校の先生が塾の先生を意識してるケースもありましたが、今では塾の評判を把握されている教員の方も増えています。
こういった時代背景もあり、学習指導は塾と言われているのでしょう。
特に今の親世代は、塾に行きたくても行けなかった世代でもあるため、子供が望むのであれば塾に通わせたいと考える親が多いです。
そのため、よりよい教育にお金を出す保護者が依然と比べて増えている実態があります。
高価格でも質が担保できれば納得してもらえる
子供が望むのであれば、塾に通わせる親が多いのは事実ですが、結果が出なければ通わせ続けるのは難しいでしょう。
他業種に比べ、比較的長いタームで待ってくれる保護者の方もいらっしゃいますが、入塾後、1回目のテストで成績が下がって即退塾なんてケースもありますよね。
大切なのは、保護者が教育の質を実感できることです。
保護者が質のよさを実感するのは、成績結果だけではありません。
- 子供が塾の話を楽しそうにする
- 家での学習時間が増えた
- 勉強する様子が変わった(大変そうじゃなくなった、質問が減ったなど)
のように、小さな変化でも保護者は質の良さを実感するのです。
これらがきっかけとなり、成績が上がる生徒は多くいます。
大切なのは、保護者の信頼を勝ち取ること。
そのために、最初の面談で、保護者が求めるものは明確にしておかなければなりません。
子供に目が行きがちですが、お金を出すのは親です。
親のニーズを全うし、納得させられるサービス提供を目指しましょう。
成績が上がる信頼感があれば、追加費用が必要でもかまわない
子供がいい方向に変化し、成績が徐々にでも伸びていれば、基本的に保護者は追加費用を出してくれます。
大切なのは前述の通り、保護者の信頼を勝ち取る状態を作ることです。
このために、日々の授業はもちろん、
- 保護者とのコミュニケート(電話やメール、送迎時の挨拶など)
- 学習報告
- 課題とプランを伝える
など、保護者へのアプローチが大切になります。
成績は上げなければなりませんが、成績がキープの状態でも「この先生は信頼できる」となれば、保護者は追加費用を快く出してくれるでしょう。
信頼とは、成績向上の可能性の有無です。
この塾に、この先生に任せていれば、成績があげられる。
そう保護者が感じるような変化を生徒にもたらせられれば、追加費用はもちろん、生徒募集も安定的に勝ち取れます。
>>自塾の生徒の成績がなかなか上がらない!原因の特定と改善方法とは
まとめ
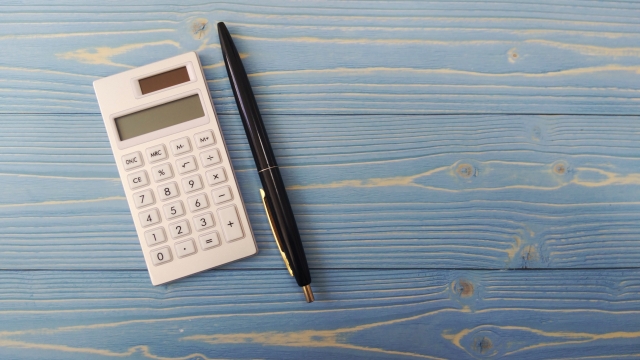
塾の料金設定は、全国平均も参考にしつつ、近隣の塾の価格やサービスとのバランスをとって行わなければなりません。
現在の塾業界は、様々なタイプの塾が乱立する、いわば戦国時代です。
これを勝ち抜くためには、差別化を図るとともに適正な価格での経営が必要でしょう。
ここまでご紹介した内容で、大切なポイントは、
- 塾はサービスを受ける側とお金を出す人間が違う
- 成績が上がるなら高くでも塾代を捻出する親が増えている
の2つです。
サービスを受ける人(生徒)とお金を出す人(保護者)が違うというのが塾業界。お金を出す保護者へのフォローを入念に。
基本的にお金を支払う人がサービスを受けて満足するのがサービス業の鉄則です。
しかし、塾業界は実際にサービスを受けるのは生徒であり、お金を払うのは親であるため、通常のサービス業とは違う形態をしています。
これを現場の講師が理解していないと、子供ばかりに目が向き、親へのフォローを全くしないようになるのです。
これが原因で、
- 子供が塾を気に入っている
- 成績が微上がりしている
- 退塾の予兆がない
など、子供の塾への肯定感が強い場合でも、突然の退塾に繋がるケースはとても多いです。
成績を上げるのは塾の使命ですが、生徒の状況によってはすぐに成績を上げるのが難しい場合もあります。
このような場合、きちんと保護者に話をし、理解してもらうのが必要です。
保護者へのコミュニケートとともに、フォローをきっちり行うと、退塾は激減します。
さらに、そのような誠意ある対応が口コミを呼び、保護者経由でも紹介を勝ち取れるのです。
現場の講師は、指示なしでも生徒には迎えます。
そのため、長期的な目線で、対保護者へのアプローチをバックアップするのが、経営者の仕事ともいえるのです。
成績が上がるのであれば塾代が多少高くとも捻出するのが親心
子供が望むなら塾に通わせる親が増えていることは、成績が上がっていれば塾に通わせ
続ける親は間違いなく多いということです。
様々な理由で子供を塾に通わせまずが、やはり一番は成績効果。
これが実感できていれば、簡単に退塾にはならないはずです。
さらに、多少塾代が高くとも、成績さえ上がっていれば保護者は納得します。
それは、成績が上がる=子供に合っていると判断するからです。
成績が上がるためには、同じくらいの学力の子よりも、
- 効率的に勉強する
- ポイントをつかむ
- よりよい学習環境がある
- 取り組み(集中力や勉強時間)
など、どれかが突出していなければなりません。
同じくらいの学力の子と、同じ勉強をしていても成績なんて上がりませんよね。
こういった環境をいかに提供できるかが塾が生き抜いていくためのポイントなのです。
いくらお金を出しても、子供にあった環境はなかなか手に入りません。
親もそのことを理解しているため、成績が上がっていれば多少高くても塾に通わせ続けてくれると言えるのです。
価格設定を強気に行う場合は、サービスの質をとにかく重視する。
低価格路線で行く場合には、サービスで賄えない部分をいかにフォローするか。
価格だけで生き残れる時代は終わりを迎えています。
子供だけでなく、保護者の満足度を上げ、高くても集まる塾を目指し、様々な部分で改革を行っていきましょう。
>>塾業務におけるマニュアル化の必要性とは?IT化への第一歩
\ビットキャンパスの詳細はこちら/