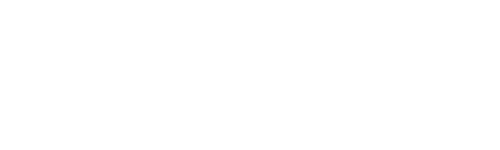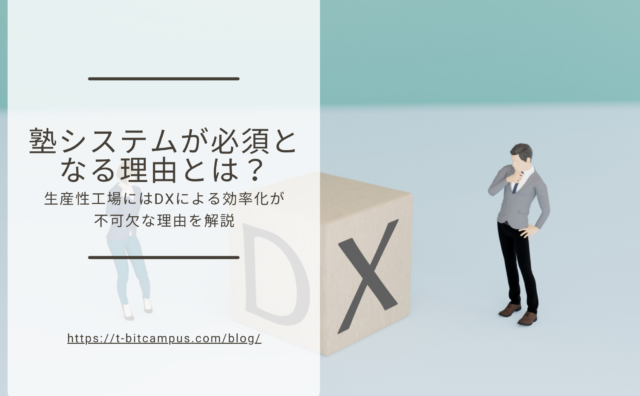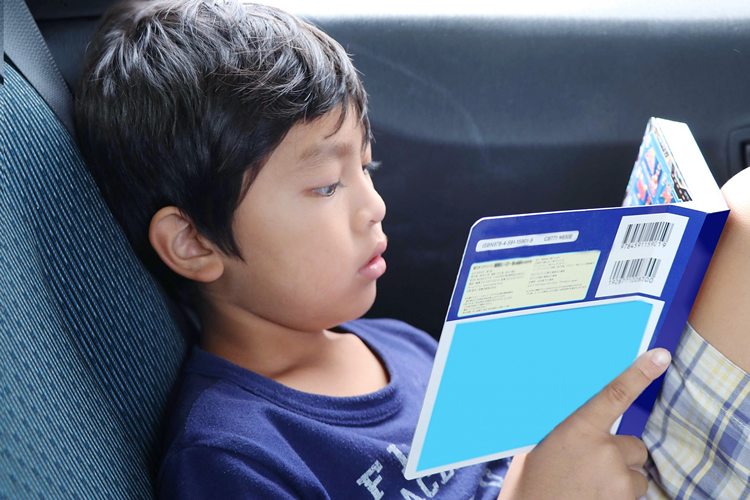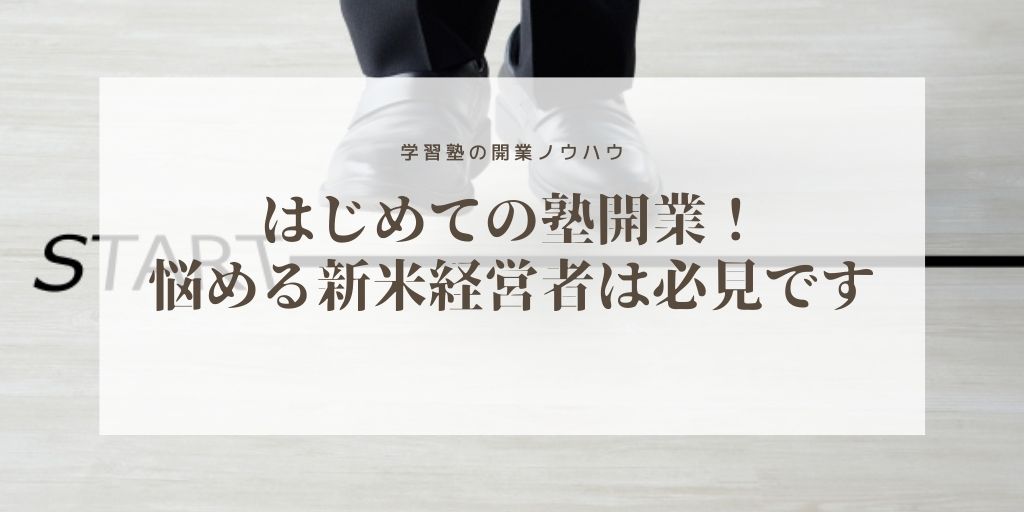一般的に学習で重要なことは「アウトプット」だと言われています。
しかし日本では、過去からの慣習のためかどうしても「インプット」ばかりに重きが置かれる傾向にあるのが実状です。
こうした問題を解決し、子供たちが効率的・効果的な勉強を実現するためには、塾講師もアウトプットの大切さを理解しておく必要があります。
勉強・学習にアウトプットは不可欠
子供たちの勉強・学習に、アウトプットは不可欠なプロセスです。
アウトプットとは、文字通り蓄積した知識を活かして、何かに出力するための作業を意味します。
人の脳は、インプットだけでは知識の定着に限界があると言われ、アウトプットを繰り返してはじめて自分の知識として消化できるものなのです。
しかし現在の教育システムでは、どちらかといえばインプット偏重。
つまりアウトプットする機会よりも、インプットに重きを置かれていますが、これでは学力の向上に効率的だとは言えません。
インプットとアウトプットの違いは?子供たちをやる気にさせるために
「インプット」とは、知識を入力する作業です。書籍を読んだり、授業を受けて内容を理解するといったことを指します。
一方で「アウトプット」は、蓄えた知識を組み合わせたりして出力する作業です。
学習した知識を活用して応用問題を解いたり、ディベートなどで自分の意見を発表することが該当します。
子供たちの悩みの一つに、「授業ではわかるけど、家で勉強するとできない」ということがあります。
いわゆる『「わかる」と「できる」の違い』です。
「わかる」=インプット、「できる」=アウトプット、と言い替えてもいいでしょう。
「ああ、なるほどわかった」と思っても、いざテストとなると自分の力で解けないのは、アウトプットする力が低いからでしょう。
アウトプットにも2種類あります。
ひとつは、芸術等の創作活動のように、自分の中にあるものを自分の方法で出力する、というアウトプットです。基本的に、他人がどう思うかや、何が求められているかを考えてアウトプットするわけではありません。その意味で独創性の高い、クリエイティブなアウトプットです。
もう一つは、何が求められているかを視野に入れながら、自分の考えや学んだことを整理して出力するアウトプットです。原理原則の理解や、論理的思考、物事を俯瞰して出力する能力が求められます。
テストや演習問題で求められるアウトプットは、2つ目のアウトプットです。何が求められているかを考えて出力する能力です。
例えば、数学で「√5の小数部分を求めよ」という問題があったとします。学校で「√5-2」と授業を受けているのに、家で「√5=2.2360679・・」と目にし、それを「ふじさんろくおうむなく」と覚えて「わかった」と理解した生徒は、答えを「2360679…」と考えて解答に窮してしまいます。
正解を確認すると「√5-2」と出てきます。「そうか、2.2360679・・から2を引けば、確かに小数部分になるな」と考えます。考え方としては間違っていません。
でも次の問題で「√10-√2の小数部分を求めよ」と出てくると、「できない」とお手上げになります。前述の「√5の小数部分を求めよ」の問題がわかっただけに、子供たちは落ち込み、「数学は難しい」とやる気を失くしてしまいます。
この単元で求められているのは「2<√5<3であるから、答えは√5-2」という本質的な考え方で、その本質がきちんとインプットされることで、その後の応用問題も解け、「できる」と子供も自信がつき、やる気が出てきます。
先生の役割は、この単元では何をアウトプットさせようとしているのか、それはなぜなのか、という本質的なことを子供たちに理解させることです。
本質的なことを理解して学習する、問題を解く、という習慣をつけることで「自分で問題を解決する力」が子供たちに身につくようになります。
この力は勉強に限らず、社会に出ても必ず役立ちます。勉強する意味もここにあると言えます。
「何が子供たちのやる気を失くすのか?」という視点で、インプットとアウトプットの違いを理解しておくことが重要です。
仕事・ビジネスにもアウトプットは必要不可欠
ビジネスパーソンを対象にしたアンケート調査によると、インプットにかける時間は7割で、アウトプットにかける時間は3割程になっています。
アウトプットに4割を費やす層は全体の1割程で、実に9割のビジネスパーソンがインプット中心で仕事をしていることになります。
アウトプットの効果の一つは知識を定着させることです。人間の脳にある海馬と呼ばれるところで、2~4週間に渡って情報が保存されます。
この期間内にその情報をアウトプットし、何度も情報を引き出すことで、脳は重要な情報だと判断し、側頭葉に長期記憶として刻まれることになります。
したがって、知識を定着させるためには「2週間に3回はアウトプット」する必要があります。
生徒に対しても、同じ単元を「学校で習って演習する」、「塾で習って演習する」、「家で宿題をする」、という3回の流れをきちんと指導しないといけません。
「定期テスト前にワークを3回繰り返す」という指導が効果的なこともここにあります。
先生にとっても、繰り返しアウトプットしてこそ血となり肉となりえます。
>>やり抜く力・グリッドはどう鍛える?塾教育と自己制御的要素の関係性
アウトプットで『伝える力』を増幅させてモチベーションを持続させる
ただ知識を定着させ引き出すだけでは、アウトプットとしては不充分です。
さらに「知識を使って創造する力」、「自分の意見を伝える力」が大切になってきます。
インプット中心のビジネスパーソンは、「会議で自分の主張を述べるのが苦手」、「自分で創造して行うプレゼンが苦手」という話をよく耳にします。
ビジネスの世界では、「ただ伝えればいい」という考えでは、同じ職場においても「ミスコミュニケーション」が発生しますし、プレゼンをしても伝えたいことが伝わりません。
ただ生徒に知識を伝えればいいという意識で授業を淡々と行う講師もいれば、伝えるだけでなく「伝わる授業をする」という意識の講師もいます。
その人は、アウトプットを重視できる講師です。
ではどうすればこのような力を育成していくことができるのでしょうか?
伝わる授業をする講師は、わかりやすさが工夫されていたり、生徒の興味をひくような例え話や生徒に響く言葉を上手く利用しています。
講師は授業を通じて、「どうすれば相手に伝わるのか」といったアウトプットのコツを実践し、生徒に伝えていくことができるのです。
そして自分の持っている知識を伝えることがうまくでき始めると、子供たちのモチベーションも自然と継続するようになります。
講師が意識すべきアウトプットのポイント・方法
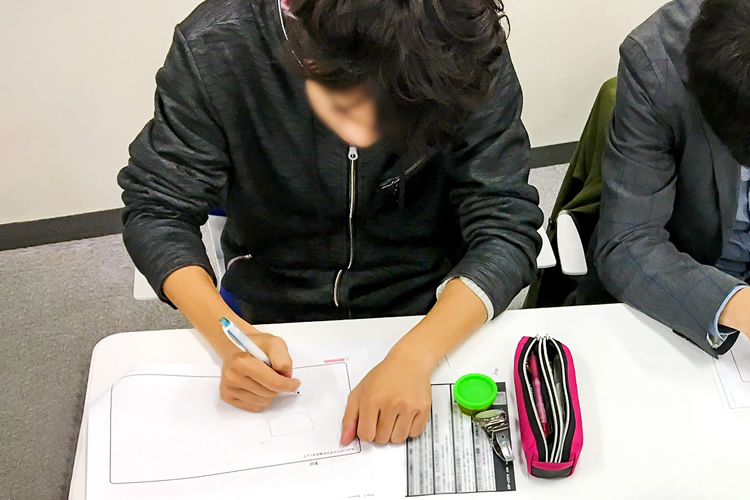
相手に伝わるアウトプットというのは、話の内容だけで決まるものではありません。
「何を話すのか」と同じくらい「どう話すのか」が重要になってきます。
非言語的コミュニケーションの重要性は、「メラビアンの法則」が有名です。
自分の認知と矛盾したメッセージを聞いたときに、人は何の影響を受けて信用するのかというものですが、「視覚情報」が55%と最も高く、次いで「聴覚情報」で38%、「言語情報」は7%という結果になっています。
これには諸説あるものの、「相手に伝わるように話すためには、非言語的コミュニケーションがとても重要である」というのは確かです。
無表情でぼそぼそ話をするよりも、「笑顔で堂々」と話した方が相手に伝わります。
こういったアウトプットのコツも、講師自体が実践し、その重要性を生徒に伝えていく必要があるのではないでしょうか。
アウトプットの習慣を定着させるアイコンタクト
話をしている最中に相手の目を見る「アイコンタクト」の有効性も多くの大学で研究され、その結果が発表されています。
ベルギーのルーヴァンカトリック大学の研究によると、話を聞いている人は、話をしている人のアイコンタクトを受け、脳内で「ドーパミン」が分泌されます。
ドーパミンは幸福物質です。楽しい、嬉しいという感情を高め、さらに記憶を増強するのにも役立ちます。
もちろん、多くの講師がアイコンタクトを交えながら、授業を行っていることでしょう。相手の目を見て話しをした方が、伝わりやすいからです。
しかし、多くの生徒を相手にする集団指導では、生徒全員にアイコンタクトをとっていくのは難しく思えます。
イギリスの心理学者であるアーガイル氏は、様々な研究結果から「アイコンタクトは1秒間でも効果がある」と発表しています。集団指導であっても、生徒一人ひとりを1秒ずつアイコンタクトをとっていくのであれば難しくありません。
伝えたい話をする場合、重要な点だけでもしっかりアイコンタクトをする習慣をつけていくことが大切です。
>>人間力を高めるために学習塾で貢献できることは?現場で育てる人間力
アウトプットの苦手を克服するために
アウトプットが苦手な場合、どうすれば克服できるのでしょうか。
「アウトプットを鍛える」または「アウトプットに慣れる」ためには、アウトプットを繰り返すしかありません。
頭で理解することと実際にできることには、大きな違いがあります。前述した「わかるとできるの違い」と同じです。
これまで述べてきたアウトプットの本質や重要性を理解した上で、繰り返し「演習」するしかありません。
実際に行動しない限り、いつまで経ってもアウトプットできるようにはならないのです。
コロンビア大学の心理学者であるゲイツ氏の実験によると、9分間でどのくらいの人物のプロフィールを覚えられるか試みたところ、インプットの時間に3割費やしたグループの成績が最高でした。
つまりアウトプットに7割の時間を費やしたことになります。
このように知識の定着には、インプット3割、アウトプット7割が理想とされています。
「アウトプット中心に切り替えていくことで、自己成長の速度は加速していく」のです。
それは大人になっても同じです。
国際社会で通用する人材を育成していくという視点においても、子供の頃からアウトプットの重要性を知っておくべきです。
またそれを伝えられる学習塾こそが、今後より存在感を増していくことになっていくでしょう。
まとめ:子供の学習には正しいアウトプットの理解が重要
闇雲に演習を重ねていても成績は上がりません。
「何のために演習しているのか」「この演習が何につながっているのか」というアウトプットの本質を、講師は生徒にきちんと理解させる必要があります。
丸暗記型より理解型、量より質、の指導が重要です。
そのためには、講師も授業や生徒指導というアウトプット経験を数多く積み、講師自身がアウトプットの本質を体得しておかなければいけません。
子供たちを待ち受けている社会は「答えのない」社会です。求められているのが何かさえわからない社会です。
その中で幸せに生きていくためにも、まずは求められているものが何かを本質的に理解し、自分の力で納得のいく答えをアウトプットする訓練が必要です。
求められているのが何かさえわからない社会で、自分が求めているものは何かを理解し、その求めているものをきちんとアウトプットできる力は、勉強で成績を上げていく過程で身に着けられます。
生徒たちのアウトプットの力をより伸ばせるように、講師自身もアウトプット経験を多く積み、工夫していくことが大事になってくるのです。
>>塾がタブレット学習を取り入れる意義は?メリットとデメリットを解説
【▼関連記事】
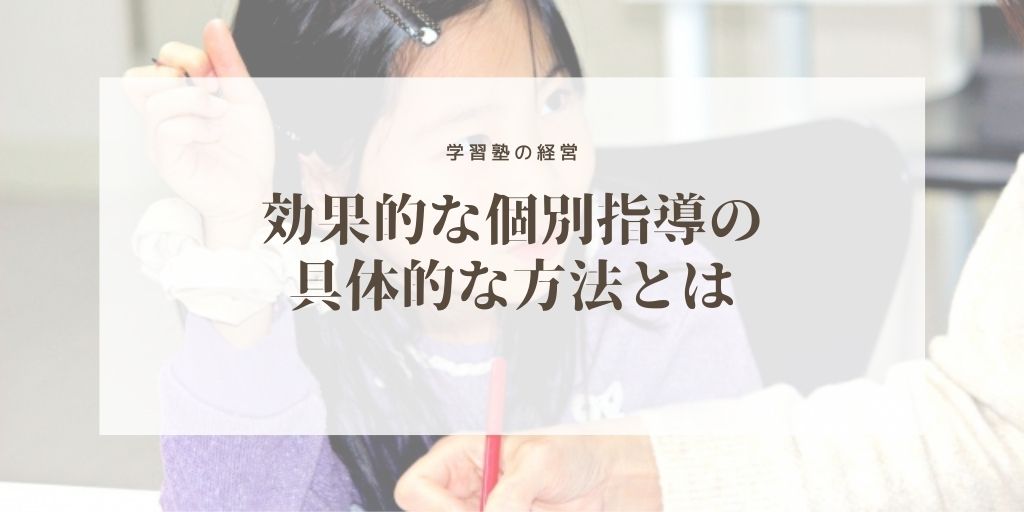
\ビットキャンパスの詳細はこちら/