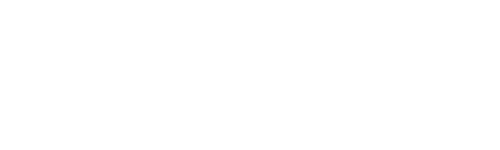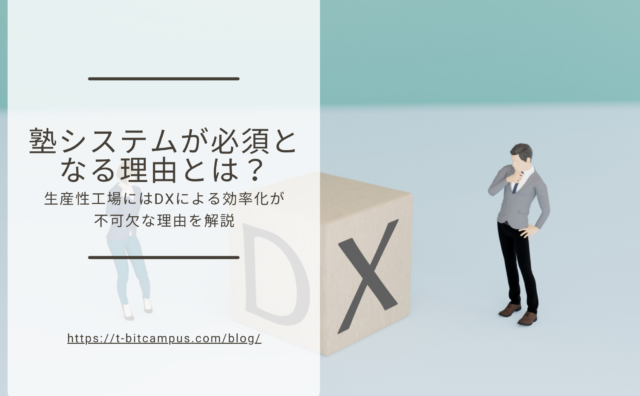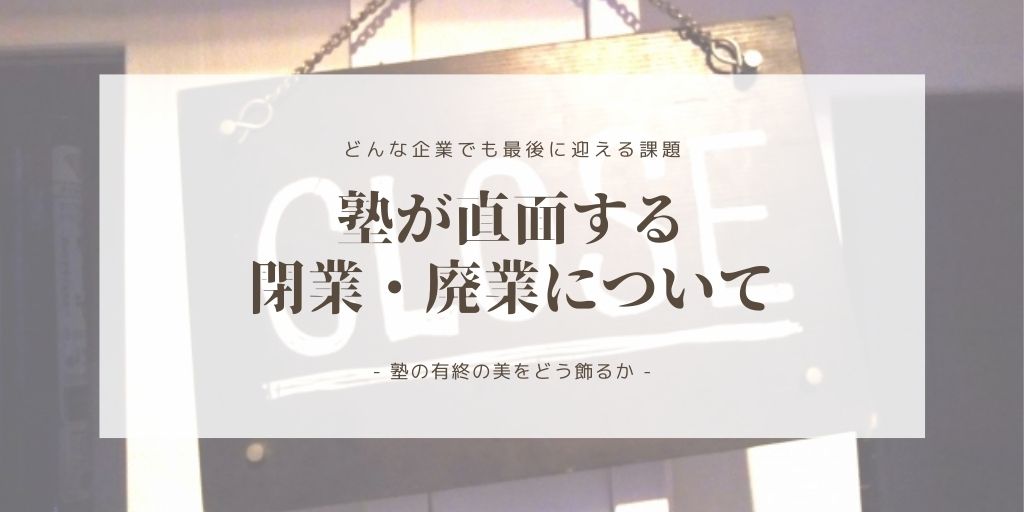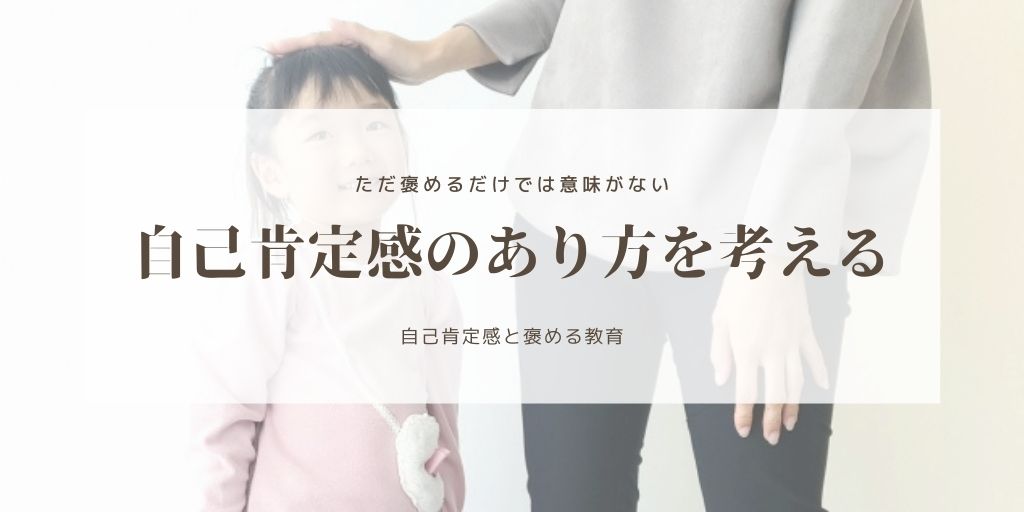物販と違い、学習塾は教育という、目に見えないサービスを提供する業界です。
目に見えないサービスの対価は、生徒や保護者の信頼感、安心感、やる気に支えられており、言うまでもないことですが、それらはさらにコミュニケーションによって支えられています。
しかしながら、その対価を払う保護者は塾で授業を受けるわけではありませんし、形のあるサービスを受けるわけでもありません。
つまり、コミュニケーションをとることによって、目に見えないサービスを評価していただくのが学習塾業界と言っても過言ではありません。
コロナ禍によるコミュニケーションの希薄化、共働き家庭の増加、SNSの普及に伴い、コミュニケーションの方法や質も変化を余儀なくされています。
ここでは、学習塾におけるコミュニケーションの大切さと、時代の変化に合わせてコミュニケーションの質を変えていく必要性についてご紹介します。
塾内の問題はコミュニケーション不足から

アメリカの心理学者ロバート・ザイアンスは、繰り返し人に接すると好意度や印象が高まるという「単純接触効果」を提唱しました。
コミュニケーションをとることで人との接触回数が増え、結果として信頼が増していきます。単純に思えますが、接触回数を増やすことは容易ではありません。
入塾申込の意思を保護者に確認するために電話をする等、コミュニケーションに何らかの目的があれば容易なのですが、目的もなくコミュニケーションを取り続けるのは難しいことです。
なぜなら、生徒や保護者の要望は何かを常に意識し、ほめる、叱る、報告するといったコミュニケーションの内容を集めていかないといけないからです。
ある塾の退塾分析では、入塾してから半年~1年目の退塾者はコミュニケーション不足が原因ということがわかりました。挨拶や声がけといった軽めのコミュニケーションさえ不足していました。
コミュニケーション不足の多くは、先生やスタッフ側が単純接触効果を意識していないことから生じます。
いつでもできる単純接触だからこそ、1つ1つ丁寧に行うように心がけましょう。
単純接触効果はバカにできない
上司と部下、先生同士の人間関係は、競争力の高い組織をつくる上で非常に重要になります。
上司の意図をスムーズに組織に浸透させるには、コミュニケーションの回数を増やして単純接触効果を高め、部下の信頼や相談しやすい職場環境を構築しなければなりません。
今は様々なハラスメントに注意しながら接触しないといけない時代ですが、相手が好意的であれば、多少厳しい指摘をしてもハラスメントと受け取られません。
したがって、「元気ないね?」とか「この前の授業良かったよ」といった小さな声掛けや単純な接触効果は馬鹿にできないわけです。
また、競争力のある塾の特徴として、塾の理念や指導方針がスタッフ全員に浸透しているということが挙げられます。
いわゆる「合意形成」が重要になってくるのですが、合意形成にもスタッフ間でのコミュニケーション回数がカギになります。
ある塾長が合意形成についてこのように述べていました。
「塾長、ブロック長、教室長、がいるとすると、役職が下になるほど1回しか言わなくなる。一番多く、何度も同じことを言うのはトップである塾長です。なぜなら、1回言っただけでは伝わらないことを知っているからです。」
コミュニケーションの大切さは誰でも知っていることかもしれません。
しかし、コミュニケーションの大切さを、他塾との差別化、競争力、強い組織構築、までつながっていることを意識する必要があります。
先生と生徒間のコミュニケーションの大切さ

先生と生徒のコミュニケーションはとても重要です。
それは、コミュニケーションがやる気のきっかけとなるからです。
心から言葉が出るように、言葉から心同士のつながりが生まれます。
ポイントは、
- コミュニケーションとやる気は関連する
- 行動するからやる気が出る
の2つです。
コミュニケーションとやる気は関連する
生徒指導に悩む講師から、「どうすれば生徒がやる気を出してくれるか?」「どうすれば授業を聞いてくれるか?」「どうすれば教室の雰囲気をよくすることができるか?」といった相談がよくあります。
わかりやすい授業のために多くの準備時間を費やし、話しかけやすいよう教室の入口でいつも挨拶するようにしていても、なかなか関係が深まらない。
まずは生徒の話をどれだけ聞けるかが重要です。
人間関係ができていない時に話だけ聞こうとしても難しいかもしれません。
そんな時には、生徒のために何かを一緒にする、ということが突破口になります。
例えば、定期テスト対策時に準備が進まず、不安に思っている生徒がいれば、授業で理解度を確認し、すぐに対応してあげる「面倒見の良さ」があれば、生徒は先生を信頼してくれます。
そうすれば、「先生、あのね、本当はね」と生徒の方から話しかけてくれるようになりますので、その時もしっかり聞いてあげます。
そこまでコミュニケーションを深めていくと先生の話にも耳を傾けてくれるようになるでしょう。そこからやる気が生まれます。
教室中にやる気が満ち溢れ、活気のある状態。
この雰囲気を作るのが、塾にとっての使命と言えるでしょう。
大切なのは、やる気を与えるのではなく、やる気のきっかけを与えることです。
- ちょっと頑張ってみよう
- もう少しやってみよう
いかに生徒をこの気持ちにさせるかが勝負になります。
些細なコミュニケーションから、生徒は心を開いていきます。
成績が上がらない生徒ほど、コミュニケーションが大切になります。
1つ1つのコミュニケーションを通じて、生徒の日常生活や興味・関心を知り、やる気を与えるきっかけ作りを行う組織を作りましょう。
やる気があるから行動するのではなく、行動するからやる気が出る。
「やる気」というものが形としてあるわけではありません。
脳科学では、脳の奥にある「線条体」という部分が、行動と快楽を結び付けて人間を動かしていることがわかっています。
つまり、「これをするとこんないいことがある」「これをすると前もいいことがあった」という心地いい予測が生じると行動し、行動するからさらに心地よくなって、行動し続けるわけです。
「やる気」という物質があるわけではありません。
したがって、勉強を始める前に机の周りを掃除したり、得意科目から始めて自己肯定感を高めたり、先生に褒めてもらった問題を復習したりして、行動と快楽を意図的に結びつけることが大切です。
ということは、先生の役割としては、いかに勉強が心地いいことか、楽しいことか、を授業やコミュニケーションを通して数多く体験させる必要があります。
何か行動をし、その結果、先生から褒められた。
自分でもできたと実感し、達成感を味わえた。
こういった体験が次の行動理由となり、やる気が生まれていきます。
やる気がないのは悪ではないのです。
それを、本人の問題と責任転嫁せず、教育者としていかに前を向かせていくか。
ここが先生の腕の見せどころです。
この状態に誘導するためにコミュニケーションができる環境を作り上げていきましょう。
塾と保護者間のコミュニケーションもとても重要

退塾防止、良い口コミを地域に流すために必要なのが、保護者とのコミュニケーションです。
しかし、講師の中には、保護者とのコミュニケーションが苦手な方もいます。
それでも、保護者とのコミュニケーションなくして、塾は成立しません。
講師には、生徒と同様に保護者との関係構築を促していきましょう。
ポイントになるのは以下の通り。
- 不満足の多くはコミュニケーション不足から生まれる
- 信頼度は接触回数に比例
- 電話連絡はつきにくい
この3つです。
不満足の多くはコミュニケーションが原因
保護者の不満の多くは、以下のような漠然とした理由から表出します。
- 成績が上がらない
- 家で勉強しない
これに対し、塾側が以下の通り、保護者と共有しているかどうかがポイントになります。
- どう指導しているか
- どこを目標にしているか
- できるようになったこと(指導の成果)
- 現時点の課題
コミュニケーションがしっかり取れていれば、保護者の不安は緩和されるでしょう。
しかし、コミュニケーションが取れていない場合、保護者の不満足に直結します。
保護者にとって、塾での子供への指導はとても見えにくいのです。
成績はもちろんですが、以下のことを通し、子供のことをどれだけ理解しているか。
- 塾での取り組みの様子
- 私生活(学校での様子)
- 将来の夢
そういうことが伝えられていれば、多くの保護者は安心して子供を任せてくれるでしょう。
保護者のニーズにこたえるのもまた、塾の使命なのです。
塾への信頼度は保護者との接触回数に比例する
保護者との情報共有は、1回で済むものではありません。
何度も保護者に伝え、状況と課題、今後の方針を粘り強く伝えていく必要があります。
前述した「合意形成」を保護者と築くには、表現を変えて何度も数多く伝えることが重要です。
ある塾では、授業中に気づいた子供の良いところをポストイットにメモし、授業後に電話やLINEで短く褒める連絡を入れています。
「今日、恥ずかしがり屋の○○君が初めて授業中に質問してきまして、それが嬉しくて連絡しました。」とだけ報告するのです。
そうすると、仕事から疲れて帰ってきたお母さんも、自分の子育てを先生に褒めてもらった感じがして嬉しくなります。
子供にも「今日、塾の先生があなたのこと褒めてたわよ」とうれしい言葉を投げかけるでしょう。
こういった短い接触を数多く行うと、保護者の塾への信頼度が上がっていきます。
つまり、塾の信頼度は保護者との接触回数に比例して大きくなるのです。
「量でなく質」という方もいらっしゃるでしょう。
もちろん、1回のコミュニケーションで満足される保護者のいらっしゃいます。
しかし、長時間中身の濃いコミュニケーションを1回とるよりも、簡単でも定期的な複数回のコミュニケーションの方が保護者は満足します。
それは、「子供のこと」だからです。
自分の大切な子を、塾も大切にしているかどうか。
それは、子供についての報告の接触回数が多い方がよく伝わります。
塾への満足度を高めるためには、やはり多くのコミュニケーションの機会が必要になります。
特に、保護者対応が苦手な先生は希薄になりがちなので、管理者側がリードするか、システムでコミュニケーションを増やす体制を整える必要があるでしょう。
共働き家庭が前提の時代!固定電話には出ず携帯電話では仕事中のことが多い
保護者とのコミュニケーションといえば、電話と答える方が多いでしょう。
一昔前までは、様々な塾で積極的に行われていた電話連絡。
しかし今は共働き家庭が増え、固定電話、携帯電話での連絡がつきづらい時代です。
大切なことは、電話をしたかどうかではなく、保護者とコミュニケーションを取ったかどうかです。
保護者への連絡手段は電話だけではありません。
- 保護者面談
- LINEなどのSNS
- 塾内HP(システムによって閲覧可能にする)
など、様々な方法があります。
電話や面談が最も効果的かもしれません。
しかし、保護者の負担になってしまっては逆効果です。
前述の通り、接触回数が増えれば、1回の電話や面談に匹敵する効果もあげられます。
そのため、意図的に保護者とのコミュニケーション回数を増やせる体制をシステム化する必要があるのです。
>>塾の集客に紹介・口コミは欠かせない!在校生からの紹介が増えない理由とは?
塾の先生・スタッフ同士のコミュニケーションは緊密に

ある大手塾の経営者に、生徒が増える教室かどうかを何で見極めているかを聞いたことがあります。
答えは「先生の表情が明るいかどうか」ということでした。
職場のコミュニケーションが活発で、上司と部下、先生同士の心理的安全性が高まれば、先生の表情も明るくなります。
先生の表情が明るい教室には良い空気が流れ、生徒の気持ちも明るくさせます。
先生やスタッフ同士のコミュニケーションが円滑な教室では、生き生きとした空気が流れます。
- 満足度が上がる
- 授業にも好影響
以上の2点について、相乗効果があるのです。
先生・スタッフの満足度はコミュニケーションと関連する
コミュニケーションが活発な教室では、講師の満足度も高い状態になります。
もちろん、仕事ですから、一定の規律は守るべきですが、先生やスタッフとのコミュニケーションがしっかり取れていると、以下のようなメリットが生まれるのです。
- スタッフや講師が辞めない
- 指示実行力が上がる
- 報告・相談がしっかりされる
- ミスが起きにくい
話しやすい間だからこそ、様々な情報共有が緊密に行われます。
これらが円滑に行えるのは、組織にとって大きな強みとなります。
満足度が高ければ、多少無理な相談も快諾してくれるようになるでしょう。
- 急なシフト変更
- チラシ配り
- 時間外の質問対応
このような対応も積極的に行ってくれるかもしれません。
満足度が高いと、スタッフの動きはとてもよくなり、結果、教室に勢いが生まれます。
間接的な手法ですが、生徒にとっては直接的に大きなメリットになるため、ぜひ先生やスタッフ同士のコミュニケーションがとりやすい環境を整えましょう。
先生・スタッフの満足は授業にも影響する
先生やスタッフの満足度が高いと、授業の精度向上に繋がります。
講師が仕事に対してやる気を持っている状態だからです。
教室運営で一番大切なのは、教室内のスタッフの意思疎通を図ること。
- 指導、対応の一貫性
- 情報共有による生徒の認知
- 教室長の指導が行き渡る
このような様々なメリットが生まれます。
また、生徒の情報共有もされやすく、指示通りにスタッフが動くため、生徒の満足度向上にもつながるのです。
つまり、先生やスタッフ間のコミュニケーションは、それぞれのモチベーションを上げるだけでなく、授業にも好影響を与え、生徒に対してプラスに働きます。
この状態ができると、先生も自主的により良い指導を求めます。
- 指導法の勉強
- 生徒対応をどうするか
- 次のテストに向けた目標設定
以上のように、さらに自主的な行動につなげやすくなるのです。
逆に、コミュニケーションが希薄だと、受動的な行動ばかりで教室の雰囲気は悪くなります。
そのため、スタッフとのコミュニケーションが密にとれる環境を目指しましょう。
生徒・保護者・先生のコミュニケーションにシステム化を

学習塾の運営にあたり、コミュニケーションはとても大切です。
対象となるのは、生徒、保護者、先生そしてスタッフ。
これらがいかに円滑なコミュニケーションを行える環境を整えるかが、塾の生命線といっても過言ではありません。
そこで、そのような環境を生むためにはシステム化が必要不可欠です。
- スマホによる状況活用
- 社員間での情報共有
- 先生一人で複数対応
システム化のポイントは、以上の3つがあります。
スマホによる情報活用を強化していく
昔は紙面や会話などが主流だった情報共有。
今でも大切なコミュニケーション方法の1つですが、それだけでは不足しています。
- 働き方改革の波についていけない
- 先生やスタッフは早く帰りたい場合もある
- やる気を奪う逆効果になる恐れもある
時代の変化を受け、過去のやり方だけではうまくいかなくなっています。
そこで、スマホによる情報活用強化が必須になるのです。
いつでもどこでも見られる環境は、一昔前にはなかった環境でしょう。
それも、本人が見たい時に見られればいいので、活用しない手はありません。
スマホでの情報活用強化の注意点は、下記の通りです。
- 見たかどうかの確認
- 情報に対してどのように思ったか
- 情報を受けてどのように行動するか
このように、組織として押さえるべき部分もあります。
情報を共有する目的だけであれば、電話やSNSで十分です。
同じ職場で働く人が、どのようなスピードで確認し、同じ情報をどう理解・解釈しているか、どのような行動に結びつけているか、といった仕事への情熱やプロ意識までも共有することが、人や組織を成長させることにつながります。
社員間で成功・失敗事例を共有化する
社内で発生した成功事例、失敗事例は、上手に共有できれば社の財産になります。
成功事例を参考に、教室運営、対応を行うと、成功率が上がりますよね。
特に、経験年数の短い講師の場合、成功事例から真似ていけば成長スピードが速くなります。
そこで成功しても失敗しても、自らの経験となるため、次につながるのです。
また、失敗事例を全員で共有することで、下記のメリットがあります。
- 同じ失敗を回避できる
- ケーススタディによって先生やスタッフの対応力が上がる
- 理念を浸透させやすくなる
これも、月に一度の定例会議などで発表させるよりも、毎日コンスタントに共有させた方が高い効果が得られるでしょう。
失敗事例の共有を上司があきらめずに行っていくと、先生やスタッフの能動的な動きに繋がります。
働き方改革が叫ばれる現代だからこそ、社員たちがイキイキとし、効率的に成長できる環境を整えなければなりません。
一人の先生が対応できる生徒数には限界がある
講師1人に任せきりの状態は、経営にとって非常に危険です。
特に現場の教室長にゆだねるケースが多いですが、もし仮に教室長が、下記のような不測の事態に見舞われた際に、対応ができなくなってしまいます。
- 退職した
- 体調を崩した
- 事故にあった
教室長の存在は、現場の生徒にとって大きなものであるのと同時に、会社にとっても大きい存在なのです。
そのため、講師1人に依存しない環境と整えなければなりません。
もちろん、教室長以外の先生やスタッフも同じです。
先生一人が抱えられる生徒数には限界があります。
そのキャパを広げていくのが講師としての力量に繋がりますが、なかなか思うようにはいかないものです。
そのため、生徒や保護者、指導法などの情報を簡素化し、コミュニケーションをとりやすくする必要があります。
まとめ

学習塾は教えるだけが仕事ではありません。
- 生徒とのコミュニケーションを通じてきっかけを与え結果を出させる
- 保護者とコミュニケーションを密に取り保護者の満足度を上げる
- 先生やスタッフ間のコミュニケーションを通じて満足度の向上を図る
このように、コミュニケーションはより良い教室運営を行うための、とても重要な要素の1つです。
これらは一朝一夕でできるものではなく、システム化してしまうのが手っ取り早いでしょう。
しかし、自社でシステムを作るとなると、多大な時間と資金が必要になります。
そこで、コミュニケーション強化のシステムならビットキャンパスがおすすめです。
ビットキャンパスは、実際に現場での経験から生み出されたシステムなので、より現場に必要なシステムが詰め込まれています。
気になる方はぜひ一度、ご覧になってみてください。