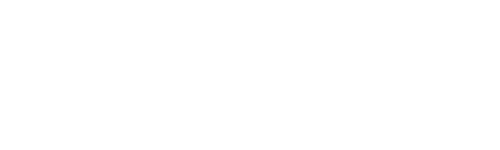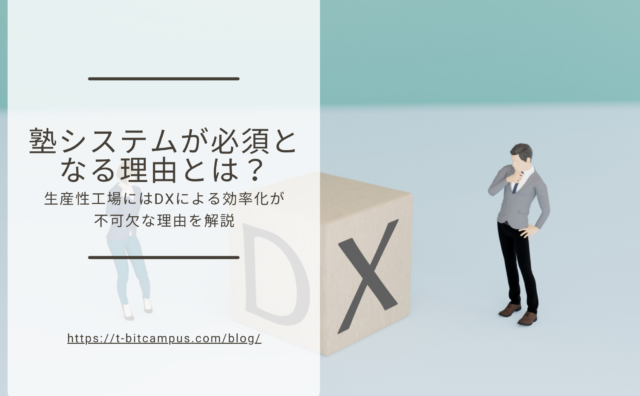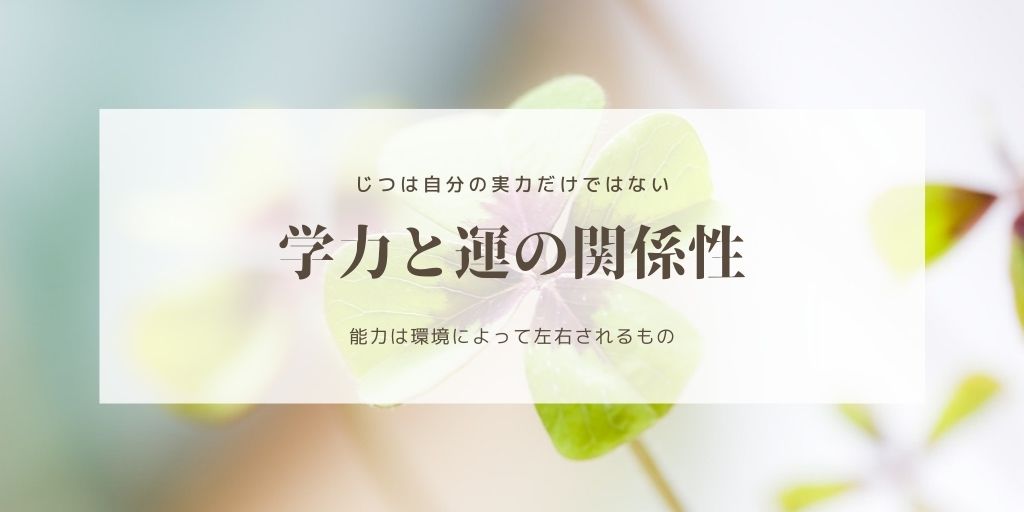DX(デジタルトランスフォーメーション)の動きが教育業界でも盛んに取り上げられるようになりました。
DXは、2004年にスウェーデンウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が初めて提唱した概念で、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」と定義されています。
学習塾では、DXをどのように考えれば良いのでしょうか。
GIGAスクール構想

学校において、生徒一人1台端末と高速通信ネットワークの一体的な整備が前倒しで実現されました。
また、デジタル教科書やAI教材をはじめ、様々なデジタル教材が端末に導入されれば、個別最適化された生徒中心の学習指導も可能になります。
そうなると、一人ひとりに合った面倒見の良い指導を強みにしてきた学習塾の特長が薄れる可能性を秘めています。
DXの成功要因
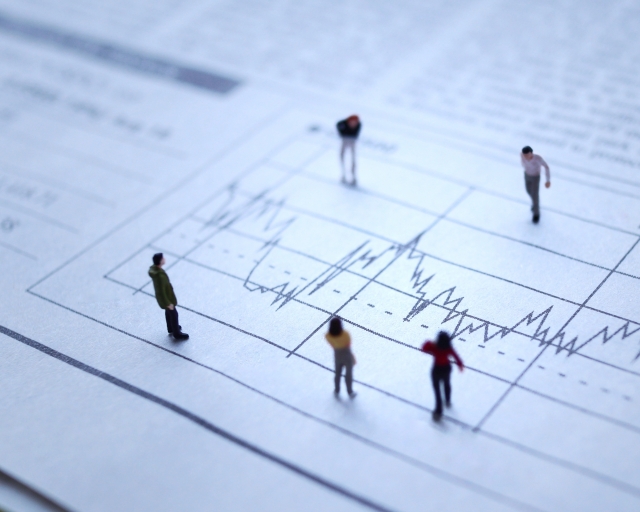
実は、そのような強い危機感を持つことがDXの成功要因としてあらゆる業界で認識されています。
独立行政法人情報処理推進機構の企業アンケート調査によると、DX成功要因の第1位は「経営層の強い危機意識」が挙げられています。
2位は「経営層のリーダーシップ」、3位は「外部企業・組織との効果的な連携」となっています。
そして、サービスに高い付加価値をつける要因は、「変革や挑戦を好む」組織であると指摘しています。
学習塾業界で言えば、デジタル教材やICTシステムといったD(デジタル)に関連することは「外部企業や組織と効果的に連携」すればよく、むしろトランスフォーメーションのX(変革)を考える人材育成の方が重要になります。
イノベーションを起こすもの

知識経営の権威であり、一橋大学名誉教授の野中郁次郎著「共感経営」によれば、イノベーションを起こすものは論理や分析ではなく、人の「共感」にあると指摘されています。
顧客への共感、トップの社員に対する共感、メンバー同士の共感、顧客から企業への共感など、様々な関係性で生まれる共感です。
本の中で、あるホームセンターでの実験が紹介されています。
人間とAIのどちらが売上を伸ばせるかという実験です。
人間は、流通業界の専門家でデータを駆使し、注力商品を適切な売り場に配置する策を考えます。
一方、AIは、スタッフやお客様にセンサーをつけてもらい分析しました。
結果、AIに軍配が上がります。
AIが出した答えは意外な答えで、店の入り口正面奥の売り場に、スタッフが10秒間長く滞在すれば、客の購買金額が平均145円向上するというものでした。
勝因は顧客とスタッフとの出会いの増加にありました。
顧客は問合せに対応するスタッフの姿に共感を抱き、スタッフは「出会いこそが購買欲を刺激する」という本質を直観できるようになり、スタッフの配置を工夫するという仮説が生まれ、イノベーションが起こります。
顧客と共振、共感、共鳴しながら本質を直観できる人材がイノベーションを起こします。
中学教科書改訂やデジタル教科書の登場で、学校指導がどうなるか、定期テスト問題がどう変わるかまだ見えてきません。
むしろ今は、生徒や保護者との出会いを増やし、共に共感し、物事の本質を直観できる人材や変革を好む組織風土づくりを急ぐことがDXへの備えになると考えます。
\ビットキャンパスの詳細はこちら/