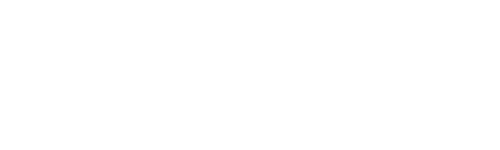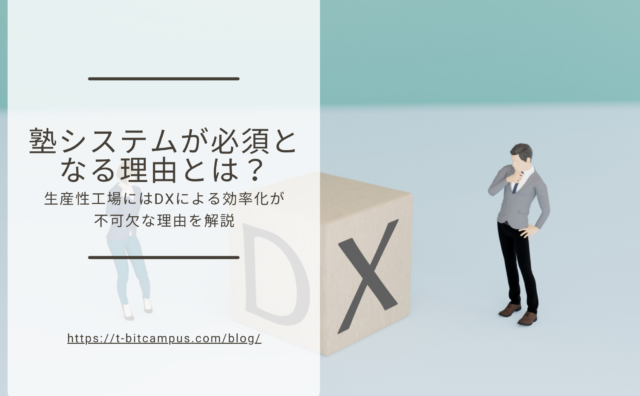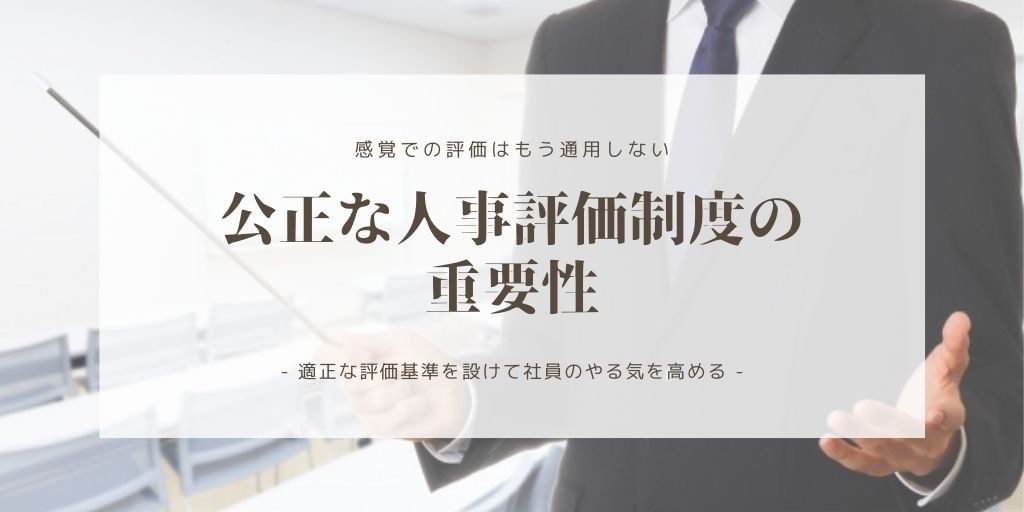学習塾で大きな問題の1つでもある人材。
子供相手だからこそ、他業種以上に「人」が大切になるのが塾です。
しかし、現代の学習塾はいい人材が集まらず、なかなか定着もしません。
そこで今回は、塾の人材採用、育成、人事評価制度についてご紹介します。
いい環境はいい人材を獲得し、優秀な人材を育成するもの。
そしてその結果、企業に大きな利を生み出すのです。
人材集めや人事評価のポイント、組織づくりに必要な体制など、詳しくお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
学習塾にとって人材は最も重要な要素

「優れた人材がさらに優れた人を育成する」というのは、古くから伝わる言葉です。
特に、感受性豊かな子供たちを相手にする学習塾にとって、人材の重要性は計り知れません。
講師の優しさは子供たちの困難な状況を救い、講師の情熱は子供たちのモチベーションを高めます。
また、子供たちと正面から向き合い、彼らが心を開くような関係を築くことが重要です。
昔も今も、教師は子供たちを良い方向へ、または悪い方向へ導く影響力を持つ存在です。
学習塾における人材の重要性が際立つ理由は、以下の2点に集約されます。
- 講師の能力によって塾の評判が左右される
- どんな教材やシステムを導入しても、最終的には「人」が決定的な役割を担う
優秀な人材は、優れた指導者を育成するだけでなく、新たな生徒も集める力を持っています。
これは、学習塾にとってなくてはならない、非常に重要な存在であることを意味しています。
講師の実力次第で評判は変わる!
他の業界と同様、学習塾も地域での評判が新規出店において重要な役割を果たします。
しかし、塾には特有の現象が存在します。
それは、担当講師が変わるだけで塾の評判が劇的に変わることがよくあるという点です。
前任の教室長の評判が良くなかった場合でも、後任の教室長が優れた実力を持っていれば、評判が良くなることがあります。
これは、学習塾が「人」によってその評価が大きく左右される職業であることを示しています。
塾の評判が、特定の講師によって構築されることは珍しくありません。
例えば、「新しい〇〇先生がとても良い」とか、「〇〇先生の授業はわかりやすくて面白い」といった声が、塾の名前ではなく、講師個人の名前を通じて評価されます。
このように、学習塾では、一人の講師が塾の評判を大きく変える力を持っています。
地域によっては、一人の講師が塾全体の状況を好転させる可能性もあり、これが塾経営におけるユニークな特徴の一つと言えるでしょう。
どんな映像教材やシステム教材を導入しても結局は「人」
新型コロナウイルスの影響を受けて、多くの学習塾ではオンライン授業や映像授業、さらにはシステム教材の導入が進展しています。
時代の変化に伴い、塾業界も大きな変革期を迎えています。
集団授業から個別指導、そしてオンライン授業へと、教育の形態は多様化してきました。
また、予習型から復習型、学習管理重視など、さまざまな教育スタイルが登場しています。
現代は、他の業界から参入する教育機関も増え、多種多様な塾が共存する時代となっています。
しかし、この競争が激しい塾業界で生き残るためには、昔も今も「人」が重要であることは変わらないでしょう。
どれほど優れた教材やシステムを導入しても、指導する「人」の質が低ければ、子供たちは成長しません。
子供たちが伸びるためには、ただの解法指導以上のものが必要です。
それは、教師や仲間からのパワーを受け取ることです。
先生の励ましの言葉や友達の姿からやる気をもらい、困難な時には支えてもらい、褒められた時の喜びを感じることで、子供たちは前向きな行動をとるようになります。
人の心を根本的に動かすのは、やはり人の力です。
たとえIT技術がどれだけ進化し、便利なシステムが登場しても、学習塾で「人」の役割が不要になる時代は来ないでしょう。
学習塾が人材を集めるために必要なこと

塾においては、優秀な人材が何よりの財産です。
これらの人材が、質の高い講師となり、生徒たちの学力向上に貢献します。
しかし、塾経営における大きな挑戦は、こうした優秀な人材をどう集めるかにあります。
専門的なスキルが求められる職業であるため、人材の確保は塾の最重要課題と言えます。
塾にとって優秀な人材を集めるためのポイントは以下の4つです。
- 適切な待遇の提供 優秀な人材を集めるためには、適切な待遇が必要です。これには給与、休日、役職、評価制度などが含まれます。小規模から中規模の塾では、これらを高水準で提供することが比較的容易です。大手塾では年功序列が残る場合もありますが、小規模ならではの柔軟な対応が可能です。
- 活躍できる教育システムの整備 優秀な講師が活躍できるような教育システムを整えることが重要です。これには、彼らの意見や提案が反映されやすい環境作りが含まれます。
- アルバイト時代からの育成 人材の育成は早期から始めることが望ましいです。アルバイトスタッフから優秀な講師を育て上げることは、長期的な人材確保につながります。
- 経験豊富な人材の採用 実績と経験を持つ講師の採用は、即戦力としての価値があります。
さらに、優秀な人材が自身の意見やアイデアを提案しやすい環境を作ることも重要です。
彼らが持つ豊かな感受性と現場経験から生まれる提案は、生徒を最優先に考えたものが多いでしょう。
そのため、提案されたアイデアを単に否定するのではなく、改善点を指摘し、一緒にブラッシュアップしていくことが肝心です。
人材に見合う十分な待遇を設ける
優秀な人材を確保するためには、適切で納得感のある待遇を提供することが重要です。
これにより、彼らのモチベーションを高め、長期的な貢献を促すことが可能となります。
主要な待遇のポイントは以下の4つです。
- 適正な給与の設定
- 十分な休日の確保
- 役職や責任の明確化
- 公正な評価制度
これらを高水準で提供できるのは、特に小規模から中規模の学習塾が有利です。
大手塾では年功序列の体系が残ることもありますが、小規模ならではの柔軟な対応が可能です。
また、これらの待遇に匹敵するのが、講師の意見を尊重することです。
優秀な人材は豊かな感受性を持ち、彼らが提案する企画やアイデアは現場での経験に基づき、生徒の利益を考えたものが多いです。
たとえ完璧でなくても、彼らのアイデアを一蹴せず、改善点を指摘し、一緒にアイデアを磨き上げることが、長期的な組織の成長と人材の育成につながります。
人材が活躍できる講義の仕組み化を行う
講師にとっての主戦場は、間違いなく授業そのものです。
各講師が持つ得意分野を活かし、彼らが最大限に能力を発揮できる環境を提供することが大切です。
講師一人ひとりには異なる特性があり、同様に生徒たちにも多様なタイプが存在します。
個別指導の場合、講師と生徒の相性を考慮して授業を割り当てることで、より効果的な教育が行えます。
担当する学年の選定も重要なポイントです。
優秀な講師であっても、経験が浅いうちは熱意のこもった指導が難しい場合があります。
例えば、小学生や中学1年生など、比較的若い年齢層の生徒を担当させるのが適しています。
受験生の指導を経験させたい場合でも、最初は少なめにするのが望ましいです。
現代の子供たちは、意図せずとも反抗的な態度や否定的なコミュニケーションを取ることが増えています。
そのため、新入社員が授業を担当した後に、ベテラン講師がフォローアップを行うなどのサポート体制を整えることも重要です。
優れた人材が無理なく成長できるよう、授業の運営方法には細心の注意を払う必要があります。
これによって、講師の能力を最大限に活かし、彼らが長期的に塾に貢献できる環境を作り出すことができます。
アルバイト時代から人材を育てる
多くのアルバイト講師は、子供への愛情、教えることへの情熱、または将来の教師を目指しているという理由から、塾での仕事を選んでいます。
子供に対する熱意は、優れた講師になるための重要な要素の一つです。
そのため、アルバイト講師も重要な戦力として考えられるべきです。
アルバイト時代からの育成は、非常に効果的です。日々の授業を通じて下記の手法を用いましょう。
- うまくいった点を褒めて励ます
- 改善が必要な点を建設的なアドバイスで伝える
- 彼らの人格を認め、尊重する
- 正しい受け取り方を褒める
これらの肯定的なフィードバックは、講師が塾の授業に魅力を感じ、長期的に働きたいと思うように導きます。
また、学校の先生を目指していないアルバイトでも、心変わりすることは珍しくありません。
アルバイトは、塾の教え方や授業スタイルを日常的に学んでいるため、新たに教育する内容を減らすことができます。
これにより、新入社員として即戦力となり、教室で早くから活躍することが可能です。
基本的な内容を飛ばして、スキルアップに集中できるため、早い段階で更なる育成プロセスに進むことができるという利点もあります。
実力のある経験者を探す
塾講師の職場では、人の出入りが激しいことがよくあります。
講師としての仕事が充実していても、体力的な問題、精神的な負担、残業の多さなど、さまざまな理由で職を変える方が少なくありません。
正社員として塾講師を務めた経験がある人材は、その貴重さから高く評価されます。
中には教室長レベルの指導力を持つ優秀な講師もいるため、こうした経験豊富な講師を見つけ出せれば、塾にとって大きな戦力となることは間違いありません。
中途採用で優秀な人材を獲得するためには、適切な待遇を提供することが重要です。
前職の塾と比較して、より良い労働環境、十分な休暇、高い給与などの利点をアピールできれば、その人材を確保する可能性は高くなります。
同じ意欲を持ちながらも、未経験者と比べて正社員として数年間の経験を積んだ講師は、その能力に大きな差があります。
転職市場の需要が高まる中で、競合他社よりも優れた待遇を用意し、実力派の人材を確保することが、塾経営における重要な戦略となるでしょう。
学習塾は公正な人事評価を考慮すべき

優秀な人材を組織内に留めておくためには、効果的な人事評価システムが不可欠です。
職員の満足度を高めるためにも、公平かつ受け入れやすい評価制度の導入が重要です。
塾講師の場合、各教室での活動が主な業務であるため、彼らの努力や成果が適切に評価されないことがしばしばあります。
効果的な人事評価を行うための主要なポイントは次の3つです。
- 公正性を持った評価を行う 評価は単に平等ではなく、公正であるべきです。それぞれの講師の努力と成果が正しく評価されるようにしましょう。
- 評価基準の明確化 何をもって良い成績とするのか、評価基準を明確にし、全員が理解しやすい形で提示することが重要です。
- 昇進の基準を明確にする 昇進や昇格の基準も、透明性を持って明確にする必要があります。これにより、職員は目標に向かって努力する動機付けを持てます。
適切な評価制度を確立し、職員のモチベーションを高め、組織全体の士気を向上させましょう。
これにより、長期的な組織の成長と人材の定着を図ることができます。
平等ではなく公正な評価をする
平等な評価システムとは、全員に対して同一の基準を用いて評価を行う方法です。
これには、例えば生徒のアンケート結果、担当生徒数、退塾数など、数値データに基づく評価が含まれます。
この方法は一見公平に見えますが、実際にはその評価基準が各教室の特性や状況を考慮していないことが多く、必ずしも公正とは言えない場合があります。
特に学習塾の場合、地域の口コミが大きく結果に影響することが多く、講師の頑張りが結果に現れるまでに半年から1年の時間を要することがあります。
このような一律の基準による評価では、講師の持つ個別のスキル、授業力、対応力、日常の校舎での活動などが適切に評価されません。
そのため、経営者や上層部は、データだけでなく、実際の教室の様子や講師の働きぶりを自ら目で見て、公正な評価を行うべきです。
数値データに基づく評価は、生徒をテストの点数だけで判断するのと同様で、これでは生徒の本質的な成長ややる気の向上には繋がりません。
講師に対しても同様で、一人ひとりに対して公正で個別化された評価を行うことが、彼らのモチベーション向上と組織全体の成長に繋がります。
評価基準を明確化する
評価基準の設定は、従業員に公正な評価を提供し、その満足度を高めるために必須です。
しかし、評価基準を単に設けるだけでは十分ではありません。
重要なのは、その基準を明確にし、従業員全員に周知することです。
これにより、評価の公正性が確保されます。
実際に多くの職場では、評価基準が曖昧なことがよくあります。
例えば下記があります。
- 数値データに基づく平等評価
- 上層部の主観や好き嫌いに基づく評価
- 経営者の個人的な感覚による評価
このような不明瞭な評価方法では、従業員からの不満が生じる原因となります。
真に公正な評価が行われていれば、従業員は次のように感じるはずです。
- 「私たちはしっかりと評価されている」
- 「自分の努力や成果が理解されている」
- 「評価は妥当で納得できる」
これを実現するためには、経営者が評価の基準を明確にし、従業員がそれを理解しやすい形で提示する必要があります。
これにより、塾の理念や目指す方向性が従業員に明確に伝わり、全ての教室で一貫した、高品質な教育が実現します。
従業員が進むべき道が明確になると、教育の質が向上し、塾全体の成長に貢献することになります。
昇進の基準を明確にする
昇進は従業員にとって大きな喜びとなり、キャリアアップへの動機付けとなります。
昇進に関しては、「成果があれば昇進する」「能力が向上したら昇進させる」といったあいまいな基準ではなく、具体的かつ明確な基準を設定することが重要です。
昇進基準の一例としては、下記が考えられます。
- 生徒からのアンケート評価
- 定期テストの成績向上率
- 受験合格実績
ただし、講師によっては特定の学年やクラスが比較的容易に成果を出しやすい場合もあるため、短期間の成果ではなく、半年や1年といった長期間にわたる成果を評価基準にすることが望ましいです。
特に塾の現場では、成果が出ないときに生徒の資質を理由にする傾向があります。
例えば、「生徒が勉強に苦手意識を持っている」「指示に従わない」といった理由を挙げることがありますが、これでは公正な評価とは言えません。
そこで、前回の成績や順位と比較して改善が見られたかどうかを評価基準にするとよいでしょう。
勉強が苦手な生徒の方が成績向上の余地が大きく、得意な生徒の場合はその維持や僅かな向上でも評価すべきです。
このように、明確な昇進基準を設けることは、従業員のモチベーションを高め、組織全体の成長に寄与します。
評価と昇進のプロセスを明確にすることで、従業員が望ましい方向に努力を重ねるように促しましょう。
仕組み化・優秀な人材の確保・評価制度を構築しよう

現代の厳しい塾業界においては、単に生徒数を増やすだけではなく、塾の経営そのものに工夫を施し、持続可能な運営を目指す必要があります。
また、従業員のモチベーションを高め、優秀な人材を確保・育成することも重要な要素です。
従業員のモチベーション向上と人材育成には以下のようなアプローチが有効です。
- 教室の拡張に依存しないキャリアアップの道筋を設ける 従業員が役職を上げるために必ずしも教室の数を増やす必要はありません。様々なキャリアパスを提供し、教室拡張以外の方法で役職昇進が可能な環境を整えることが大切です。
- データ管理を活用して若手講師の成果を可視化し、適切な評価を行う 効率的なデータ管理システムを導入することで、若手講師の成果を正確に把握し、その努力と成果を適切に評価することが重要です。これにより若手講師の成長を促し、モチベーションを高めることができます。
- 安定した職場環境と充実した待遇で、長期的なキャリアを支援する 従業員が結婚や家庭を持っても働き続けられるような職場環境を整備し、安心して長く働ける体制を作ることが重要です。これにより、従業員はプライベートとのバランスを保ちつつ、仕事に専念できるようになります。
このように、従業員が自身のキャリアと生活において満足感を得られる環境を整えることで、塾の経営全体が安定し、成長していくでしょう。
教室を増やさないと役職が上がらない仕組みにしない(教室長だけ等)
組織の構築において、役職の設定は非常に重要な要素です。
特に学習塾では、教室長の役職が若手講師にとって初めて手にすることができる責任あるポジションとなります。
入社1年以内に教室長に昇格することも珍しくありません。
しかし、組織が適切に構築されていない場合、教室長を超える昇進の機会が限られてしまうことがあります。
単に教室数を増やして教室長のポストを増設するだけでは、従業員のモチベーション維持には不十分です。
これを解決するためには、全体の組織構造を考慮した組織づくりが求められます。
- 各教科の責任者や担当者を設定する
- 地域やエリアごとにマネージャーの役職を創設する
- 人材育成部門の設立し、研修担当者としての役職を設ける
- 広報、総務など、教育業務以外の部門の役職を創設する
これにより、教室数を増やさなくても昇進の機会を提供し、従業員が自らの得意分野や興味に合わせてキャリアを積むことが可能になります。
多様な業務を持つ学習塾では、各部門ごとに多くの役職を設定することが容易であり、これが従業員のやる気とキャリアの成長に大いに貢献します。
組織全体のバランスを考慮しつつ、積極的に様々な役職を創設することをお勧めします。
データ経営をしなければ、古参の社員の経験則に優秀な若手が勝てない。
学習塾における講師の経験は、その業務遂行において大きな役割を果たします。
確かに、若手講師が熟練した古参講師のレベルに迅速に到達するのは容易ではありません。
しかし、もし企業のシステムを用いて経験のギャップを埋めることができれば、状況は変わるかもしれません。
若手講師にも活躍の機会を提供し、同時にベテラン講師にも若手に負けないような刺激を与えることができます。
つまり、データに基づく経営が理想的な解決策となり得るのです。
塾の蓄積されたデータは貴重な資産です。
このデータを有効に活用することで、塾の成功に大きく貢献できます。
ベテラン講師は豊富な経験から得た知識を持ち、新人講師はデータの収集に励むことが求められます。このような状況では、新人講師の早期の挫折が危ぶまれます。
企業として競争を促進し、社員の能力向上を図ることは重要です。
特に優秀な若手講師は学習能力が高く、時にはベテランを上回る成果を出すこともあります。
その才能を最大限に活用し、各人が能力を存分に発揮できる環境を整えることが、変動の多い現代においては特に重要です。
力を持つ者が活躍し、適切に評価される体制を構築することが、これからの時代を生き抜くために必須であると言えます。
結婚時の不適切な待遇が優秀な社員を逃すことに
学習塾の業務は、忙しさの極みと言えます。
働き方改革の流れの中でも、塾の実情は大きく変わらないのが現実です。
いくつかの企業では労働環境の改善が進んでいるかもしれませんが、テスト対策や受験シーズン、期別講習の時期には業務量が一時的に増大します。
その結果、下記のような労働者としての基本的権利が行使しづらい状況になりがちです。
- 育児休暇の取得が難しい
- 有給休暇の消化ができない
- 体調不良時の休養がとりにくい
- 休日返上での授業担当
特に、家庭を持つことを考えた場合、このような環境は職務の継続を難しくします。
塾講師は一般の職種と異なる勤務時間であるため、家庭の事情とのバランスが取りづらいのも事実です。
給与だけでなく、従業員の権利を十分に保障することが、良い待遇を提供する上で重要です。
また、結婚や家庭を持つ従業員に対して有益な福利厚生を導入することで、離職率の低下にも寄与します。
結婚は人生の大きな節目です。
従業員の人生を支え、彼らの大切なイベントを支援する体制を整えることは、従業員に対する深い配慮の証となります。
他塾にはないユニークな待遇制度を導入し、魅力的な職場環境を構築していくことが、塾の経営成功に繋がる鍵となるでしょう。
まとめ

学習塾における人材は、その存続と発展の核心です。
最先端のシステムを導入しても、質の高い人材がいなければ、成果を得ることは難しいでしょう。
ただし、優れた人材を見つけ出すのは容易ではありません。
このため、外部からの人材獲得に加えて、社内での育成にも力を入れる必要があります。
社内で職員間の競争意識を醸成し、若手でも能力を発揮できる機会を提供し、適正な評価体制や明瞭な昇進基準を設けることが大切です。
このような取り組みによって、優秀な人材を内部で育て、企業の強化を図ることが可能になります。
社員が誇りを持ち、離れがたいと感じるような企業文化を築くことは、経営者にとって重要な役割です。
過去に会社員として経験した不満や課題を反映させ、同様の不満を社員に抱かせないことが重要です。
社員が活気に満ち、前向きに仕事に取り組めるような環境を整えることで、企業全体が成長し、繁栄する道を切り開くことができます。
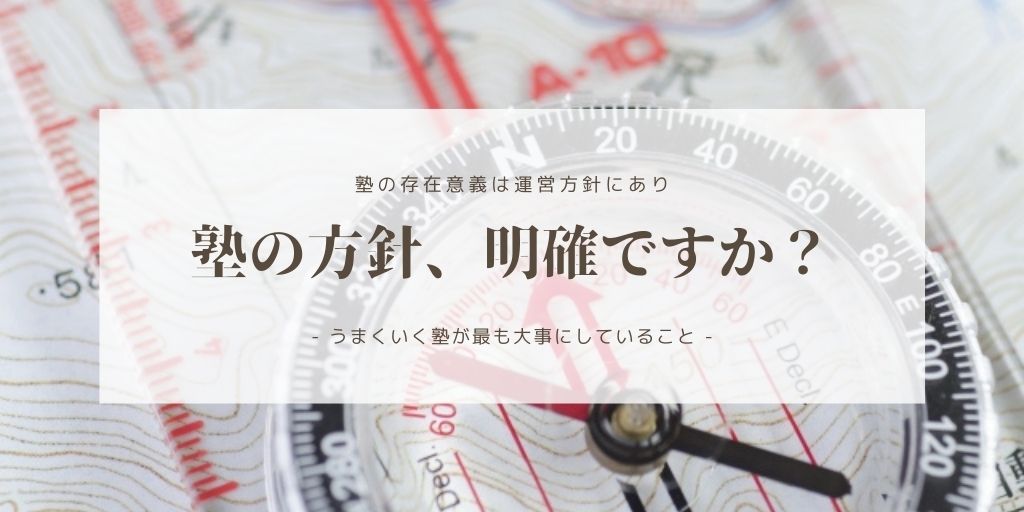
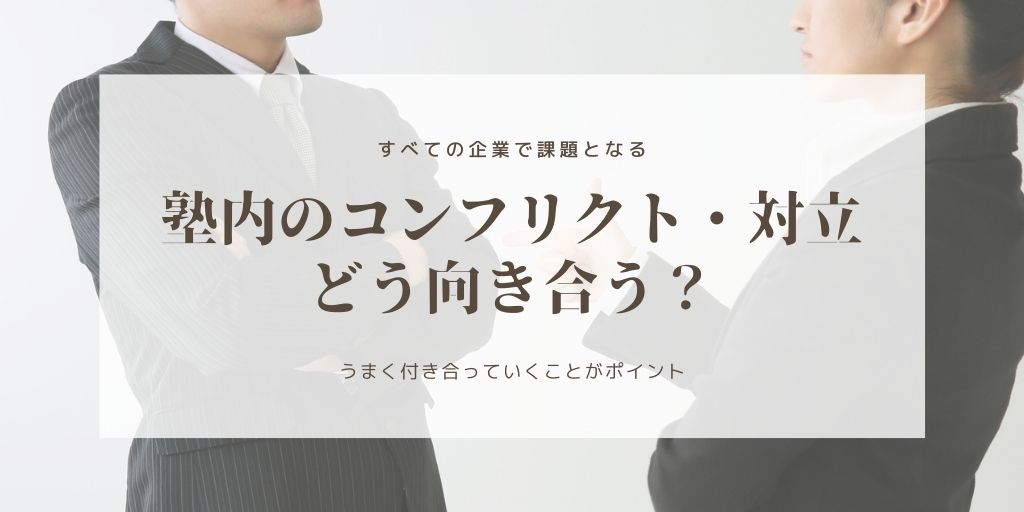
\ビットキャンパスの詳細はこちら/